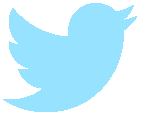中日ある記1「中国の多様性と日本の単一性」
BBパートナーリレーコラム「日中コミュニケーションの現場から」第1週

Billion Beatsで「中国と日本」をテーマに新連載がスタートすることになった。このリレーコラムの最初の書き手を担当させていただく。
絶えず歩き続けることを中国語で「終日行走」と言う。だが私は「終日」ではなく、まず「中日」、自身が中国と日本を往来する中で感じたことを書きたい。(訳者注:「終日」と「中日」は中国語の発音が同じです)
中国から日本を見た際に最も感じられるのがその「単一性」だ。
近ごろは日本で「爆買」する中国人観光客が目立つ。自国では財布の紐が固い彼らも、日本では何かに取り憑かれたかのように買い物をする。場所も価格も品質もお構いなし、我先にと買い漁っている。
そうした中国人は「日本は何でも素晴らしくて、どんなものでも中国より安い」と信じて疑わない。東京の露天で売られている商品と高級デパートで売られている商品は同じで、価格もさほど変わらないと判断する一方で、北京の秀水街では、売り手の言い値の一割からディスカウント合戦を始める。日本人観光客がためらいつつも意を決して値切るのとは大違いだ。商業的な習慣の問題もあるが、おそらく単一性と多様性という違いがより色濃いのではないだろうか。広大な国土と多くの民族を有する中国の多様性は日本と比べてはるかに複雑であり、その中国から日本を見れば単一性が際立つ。
食事に関する例を挙げよう。私が中国の各地を取材で訪れる際、その土地の郷土料理を試そうと思うことは稀だ。だが日本では逆なのである。
四川で本場の四川料理を食べた時のことである。私は絶えず咳こみ、水を飲みつつその食事を終えた。あまりに辛いその料理は野菜と肉、肉と魚の区別さえつかなかった。真っ赤な唐辛子にまみれた、その肉か魚のようなものを箸でつまみ口に送る。辛さで咳は止まらず、水を飲んでも全く治まらなかった。
広東でもまた別の苦難を経験した。白いおかゆには異臭を放つ黒いピータンとピンク色の肉でんぶ。広東人はそうしたおかゆを好む。30年前、香港にほど近くまだ漁村だった深圳に行った際、現地の人びとがそのおかゆをすするのを見て思わず吐き気を催したのを覚えている。今ではすっかり大都市となった深圳だが、理解しがたいことにそのおかゆは健在だ。
日本なら話は別である。Billion Beats発起人の1人は熊本県出身で、私も熊本を訪れた。あちらでは馬刺をよく食べると知り私も試してみた。その時思い出したのは、日本で初めて魚の刺身を食べたときのことだ。あれは長年アメリカで記者をしていた知人と一緒だった。彼はいささか躊躇している私に「レアに焼かれた牛肉と思って食べれば大丈夫」と言った。その赤身のマグロを味わってみると、本当に牛肉のようだった。そんな経験があった私は熊本でも馬刺を抵抗なく試すことができたのだ。
刺身が食べられるようになればあとは簡単だ。それは日本に入国するのと似ているかもしれない。入国審査で向き合う無表情な担当官以外、ほぼ全ての日本人はとても親切で温かい。入国審査さながらの「刺身」というゲートをくぐってしまえば、生の魚でも馬刺でも、困難であるどころか楽しみにさえなるのだ。
中国の四大料理あるいは八大料理は、今後数百年を経ても変化しないだろう。これが中国の多様性だ。日本料理の中には懐石料理や郷土料理などの細かい違いはあるにせよ、日本文化に詳しくなければそれらを区別することは難しい。
だが最近日本に行った際、20年前とは明らかに違ってきていることを感じた。以前は主に焼き魚の匂いがしていたところで、時折韓国料理のニンニク、更にはインドカレーの匂いが感じられることがあるのだ。だがそれでも日本の中華料理が日本料理に組み入れられることがないのと同様、韓国料理やインド料理も日本料理の一部になることはないだろう。中国における洋食もよく似た状況だ。洋食はあくまで独立した存在で、今もこれからも中国料理の一部になることはできない。
それぞれの国の料理という観点から、中国の多様性と日本の単一性というコントラストが見て取れる。
文・写真:陳言 | 翻訳:勝又依子
関連記事:
投稿者について
ChenYan: 会社経営者 1960年北京生まれ。 1978年に大学に進学して日本文学を専攻した。卒業後に日本語通訳などをして、1989年に日本へ留学し、ジャーナリズム、経済学などを専攻し、また大学で経済学などを教えた。 2003年に帰国し、2010年まで雑誌記者をした。 2010年から会社を経営している。 主な著書は、「中国鉄鋼業における技術導入」、「小泉内閣以来の日本政治経済改革」など多数。