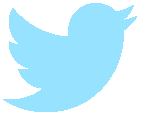第2回 ハンセン病 – 生きざまの現れる病気
生きる場所は選べなかったが、生き方は選べた人たち
JIAの活動が対象としている「ハンセン病」という病気そのものを身近に感じる人はあまりいないかも知れない。しかし、ハンセン病と歩んだその人の「生きざま」に焦点を当てるとき、それは普遍的に人々に響くと想う。
ハンセン病はらい菌の感染によって発症する病気だ。現在では早期発見、早期治療によって後遺症を残さずに治癒する。1981年より世界保健機関の推奨する多剤併用治療により、数日から数週間以内に菌の伝染性を抑えることができ、6ヶ月から2年で治癒するようになった。
そもそも、人口の99%の人々がらい菌に対して免疫を持っている。感染するケースとして考えられるのは、例えば、免疫のない1%の人が、戦後のように食べ物がない栄養状態で、身体を洗う水もないような衛生状態のとき生まれたばかりの嬰児で、かつ、未治療のハンセン病患者である家族にお守りをされている場合、飛沫感染する可能性があると言われている。感染しても潜伏し続け、発病しないで終わることもある。
有効な治療法のなかった時代、ハンセン病を病んだ人々は山奥や孤島のハンセン病隔離施設に隔離された。当時はらい菌が皮膚や神経をおかすのを防ぐことができず、身体に変形を引き起こした。この変形は治癒後(つまりらい菌が身体からいなくなった後)も元に戻らず、後遺症となった。一目で「ハンセン病元患者」であることがわかってしまう。「遺伝病」という誤解もあっため、後遺症を持った「元患者」が実家に帰ってくれば、家族ごと村八分にされてしまった。そのため、治っても実家に帰ることができない人が多かった。
つまり、ほとんどの場合、ハンセン病を病んだ人々は「生きる場所」を選ぶことができず、ハンセン病隔離施設にとどまらざるを得なかった。
しかし、彼らは、その場所で「いかに生きるか」は選ぶことができた。そこに、その人の生きざまが現れる。
「強靭な者だけが生き残った」。
広東省清遠市のハンセン病快復者・オウ・ジンジャオ(男性)はそう語る。オウ・ジンジャオが6歳のとき、父がハンセン病を発病し、錯乱状態となって行方不明になり、一家は離散した。オウ・ジンジャオ自身も9歳で発病し、隔離される。隔離病院では有効な治療法もなく、病気であっても食べるために労働をし、途中息絶える人も少なくなかった。病院内では恋愛も禁止され、見つかると吊るし上げられ、その後自殺した人たちもいた。そんな中、オウ・ジンジャオは自分の能力を向上させるために学び、周りの患者・快復者をいたわり、病院を管轄する理不尽な政府部門と闘いながら、生き続ける。
ハンセン病と共に歩んだ何十年もの間、生きるということをあきらめなかった彼らに出逢うとき、僕たちは自分の生き方を見つめ直さざるを得ない。
ハンセン病とそれへの誤解
ハンセン病には様々な誤解がつきまとい、それが差別につながった。
まずは、身体の変形が元に戻らないことから生まれる、「不治の病である」という誤解がある。人によって症状は異なるが、らい菌が汗腺をつぶすと汗や油が出なくなり、皮膚が乾燥する。乾燥した皮膚は冬のあかぎれのように傷を受けやすい。らい菌は末梢神経をもおかすため、知覚が麻痺する。傷を受けても痛みを感じない。痛みを感じないと傷を保護することが難しい。治りかけた傷がまた傷になり、雑菌に感染して大きく、深く、潰瘍となることもある。
らい菌がもし指の神経をおかせば指を伸ばす動作ができなくなり、指がずっと曲がった状態になることがある。手首や足首を持ち上げることができなくなったり、口やまぶたを閉じられなくなったりすることもある。まぶたが閉じられなくなると、寝ている間にふとんやほこり、虫などで目を傷つけやすくなり、失明することもある。知覚を麻痺した上に失明すれば一人で生活することが困難になる。足の裏の麻痺が重ければ、釘を踏み抜いても痛みを感じないこともある。傷が潰瘍となり、足を切断せざるを得なくなる人も多い。
このような身体の変形はハンセン病が治った後(つまりらい菌が身体からいなくなった後)も元の状態に戻ることはない。その身体を見れば、知らない人は思うだろう、
「この人の病気は治っていないんだ」。
こうして「ハンセン病は不治の病である」と誤解された。
「感染力が強い」という誤解もあった。
広西壮族自治区桂林市のハンセン病快復者・陸憲貴(男性)はハンセン病と診断されると即、「あたかも怪物になってしまったかのよう」だった。家族は彼を恐れ、村中の人々はさらに恐れ、彼を見るなり遠くに逃げていく。陸憲貴は涙にむせびながら言う、
「おれは忘れられないんだ。病院からの診断書を受け取ったときの情景、故郷を去るときの情景、住んでいた家が焼かれ、持ち物が投げ捨てられる情景を。おれは遠くへ、遠くへ逃げた。そのひとつ一つの情景を見て、心の中で泣いたんだ」。
このような情景は人々の間に「ハンセン病の伝染力が強い」という誤解を根強く植えつけた。
と同時に、家族内感染が多かったことから「遺伝病である」という誤解もあった。そのため、身体に変形があるハンセン病快復者が家族と暮らしていれば、家族・親族全体が「らい血統」と言われて差別を受けた。兄弟姉妹や親戚の結婚が破談になることもあった。そのため、隔離村で一生を終えざるを得なかった。
広東省潮州市のハンセン病快復者・蔡玩卿(女性)は40歳のときハンセン病が治り、実家に帰りたいと思った。しかし甥たちがまだ結婚していなかった上に実家に住む部屋もなかったので、甥たちは蔡玩卿が隔離村に住み続けるようにと言った。そうでないと甥たちの結婚が難しくなる。
「こう言われたとき、感情がかき乱され、死のうと思った」。
そして、隔離村に住み続けた。家が貧しかったこともあり、蔡玩卿の甥たちはなかなか結婚できなかった。蔡玩卿の兄が亡くなったとき、兄の古い戦友たちが葬式をあげに来てくれた。そのとき蔡玩卿の甥たちがまだ結婚していないのを見て、急いで結婚を世話してくれた。
しかし、上の甥の新妻は叔母である蔡玩卿がハンセン病患者だと知ると、甥がそれを黙っていたことをずっと責め続けた。
「それを知ったとき、心の痛みは極みに達した」。
ふたり目の甥が結婚するとき、婚約者は親族にハンセン病患者がいることを知ると、甥との関係を断絶した。
「この時もまた心に重くのしかかる打撃を受けた」。
3人の甥がすべて結婚したとき、やっと心が解き放たれる想いだった。
中国のハンセン病
中国では1957年、ハンセン病隔離施設を建設し、患者を隔離することが決定された。全国800ヶ所にハンセン病隔離施設が建設され、1950年からの統計によると患者50万人を隔離した。1980年代に入るとMDTの普及に伴い、患者の在宅治療が行われるようになり、隔離は行われなくなった。それ以前も日本のように終生絶対強制隔離政策は取られず、治癒後は実家に帰って社会復帰することが許された。しかし、根強い差別のため、実際のところ実家に帰ることができず、隔離施設にとどまり続ける人たちがいた。現在、ここはもはやハンセン病隔離施設ではなく、ハンセン病「快復者」の住むただの「村」、つまり「ハンセン病快復村」となった。現在では全国に約600ヶ所の快復村が存在し、そこに快復者約2万人が住むと言われている。
ほとんどのハンセン病快復村は辺鄙な山奥や孤島に位置する。その後の経済発展に伴って工業地帯に囲まれたような村や公道のすぐ脇に位置するような村もあるが、それは沿岸地域の一部の村に過ぎない。経済的に恵まれた地域では療養所や病院のような施設もあるが、多くの場合、ただの村にしか見えない。
十数年前までは1950年代、60年代に建設された家屋が残り、トイレやシャワー室、台所がない村も多かった。村に井戸もしくは貯水タンクが1ヶ所しかなく、後遺症のある身体で水くみが必要な村や、電気がない、もしくは使用時間が制限されているところもあった。
政府が支給する生活費もギリギリ生活ができるかできないかという程度で、タバコを買うお金もままならなかった。炊事はまきと七輪で自炊するほかなく、まきを割るたびに後遺症で麻痺した身体に傷をつくり、やけどを負った。
傷の手当をする医師も看護師もおらず、何度も洗って黄色くなった包帯やガーゼを使って自分で治療していた。それすらしないで放っておく人も少なくなかった。
表情は普通、暗く、笑顔がないのは顔面が麻痺しているからだけではなかった。結婚が禁じられていたため、村に通常子供はいない。家族との往来も少ないか全くない場合もあった。外から人が来ることはほんとんどなく、あるとしても政府の慰問などで、役人たちはあからさまに嫌そうに、義務として援助物資の米や油を置くと、証拠写真を撮り、急いでその場を離れる。外出してもバスに乗車拒否されたり、食堂に入れてもらえなかったり、市場で現金の受け渡しを嫌がられたりした。
多くの人々が絶望のあまり自ら命を断っていった。ほとんどの村でそうささやかれる。

(写真)多くの人々が絶望のあまり自ら命を断っていった。© Kosuke Okahara
関連記事:
投稿者について
Ryotarou Harada: NPO「家-JIA-」創設者。 1978年生まれ、2002年2月広東清遠楊坑村ワークキャンプに初参加。2003年早稲田大学政治経済学部卒業。快復村に卒業直後の2003年4月から1年半住み込み、2004年に日中韓の発起人6名でJIA創設、事務局長就任(2004年~2015年)