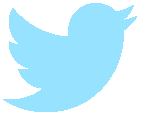第4回 ハンセン病元隔離村を開く ―差別をいかになくすか

(写真)30年ぶりに町並みを眺める村人
差別しない人間がいるなんて、夢にも想わなかった
とはいっても、当然ながら、最初から「人と人とのツナガリ」があるわけではない。
初めてやってきた日本人ボランティアを見て、村人たち(ハンセン病快復者)は思った、
「こいつらには何か裏の目的があるはずだ」。
1年半の間、そう思い続けたと後に話してくれた村人もいる。
ハンセン病にかかって以来、外の人間は基本的にすべて差別者だった。何の見返りもなしに村に来るはずがない、と。
しかも、僕らは日本人だ。僕らが活動するほとんどすべての地域で、日本軍の影響が見られる。村人にとって日本人は即、かつての日本軍だ。肉親を殺された人たちもたくさんいる。
その日本人が、また来た、のだ。
「昔はあの山に日本軍がいてな」。
日本人だとわかるとたいてい、この地域の人は山を指差しながらそう言う。
ただ、今回の日本人はちがっていた。中国の人々を殺しにきたのではなく、村にトイレをつくっている。
「おれたちハンセン病快復者を差別しない人間がいるなんて。おれたちと飲んだり食べたりするなんて。そんなこと、夢にも想わなかった」。
驚いたのはハンセン病快復者だけではなかった。
ワークキャンプ中、ボランティアたちはハンセン病快復村の村人のバイクの後ろに載せてもらって、市場へ買い出しにでかける。日本人の女の子と手をつないで歩くハンセン病快復者を、市場の人々は身を乗り出して見つめる。この日以来、市場でのハンセン病差別は劇的になくなった。むしろ、快復者が買い物に来ると、市場の人たちは彼を引き止め、「日本人」について様々な質問を浴びせる。
快復村周辺地域の子供たちは、日本人を見物するため、普段は寄り付かないハンセン病快復村にやってきた。次第に日本人と仲良くなっていく。夕方になっても帰ってこない子供たちを心配し、その親が快復村にやってくる。すると、そこで目にするのは、日本人ボランティアや自分たちの子供たちがハンセン病快復者と話したり、お茶を飲んだりしている姿だ。
「あんたたち、ハンセン病になるのが怖くないの!?」
「皆さんの病気はもう治っていますから」。
「治っているって、あの曲がった指を見なさいよ」。
「あれは後遺症なんです」。
こうして、周辺地域の人々の間にハンセン病への理解が進んでいく。
ハンセン病啓発のちらしを何万枚撒くよりも、「客寄せパンダ」としての日本人の行動ひとつの力は大きい。
いつしか、町で日本人だとバレると、こう言われるようになった、
「あの、ハンセン病村で活動している日本人だろう」。
村人が「自分自身への差別」を徐々に解消
こうして、ワークキャンプを開催し続けると、周辺地域からあからさまな差別はなくなっていく。
その一方で、村人たちは、「自分自身への差別」を拭い去ることが難しいようだ。
リンホウ村でワークキャンプを初めて開催して以来、1年が経ち、キャンプ開催回数は3回になった頃、僕はリンホウ村の人々に、市内一日観光に行こうと提案する。村人たちは口々に言う、
「バスに乗れない」
「差別の目で見られる」
「レストランで食事ができない」
…
しかし、僕は見たことがある。ハンセン病とは無関係だが、片目のない人が、指のない人が、義足で松葉杖の人が、外の世界で普通に暮らしているのを。僕が観察する限り、その人たちのことを嫌な目で見る人に出あったことがない。中国では「人とちがうこと」が直接排除へとつながるわけではないようだ。少なくとも、日本よりは。
まして、僕の提案する市内観光は、地元のキャンパー(キャンプ参加者のボランティア)と一緒に行くものだ。さらに、チャーターするバスの運転手は、活動初期にこそ「リンホウ村」と聞くと嫌そうな顔をしたり、運賃をぼったくったりしたが、今では村でお茶を飲んでいく人だ。
そう説明しても、村人たちは「いかない」を繰り返す。
その後、僕の執拗な説得に折れた村人たち6名は市内観光に出かける。30年ぶりに見る街の変化に何とも言えない表情を見せる村人もいた。
指のない村人は始め、ポケットから手を出そうとはしない。が、次第に、周りの人たちは自分たちのことを特に気にしていないことに気づき始め、そもそもポケットに手を入れたままでは不便なので、いつの間にか、ポケットに手を入れることは忘れてしまった。中国では、若者が老人と歩いていると、基本的に皆、普段以上に優しくしてくれる。席を譲ってくれたり、先に通してくれたり、微笑みかけてくれたり。そんなちょっとした優しさに村人も癒やされていく。憧れの開元寺にも行くことができ、村人はみんな大満足で村に戻る。
彼らがハンセン病を病んだことを知っている実家の近所では、同じようには行かないかもしれない。それにしても、村人たちは、「差別しない人」がキャンパーだけではなく、街にもいることを知った。
海南省のある村人は語った、
「キャンパーと手をつないで市場から帰ってくるとき、ふと、初めて、自分に尊厳を感じた」。
広東省のべつの快復村の村人は語った、
「村の近所の健常者が言ったんだ、『大学生がハンセン病村に泊まるくらいだ。おれがおまえらを恐る必要があるか?』と」。
こんなちょっとした出来事の積み重ねが、徐々に村人の「自分自身への差別」を減らしていく。
「私は人間じゃないから」。
リンホウ村の蔡玩卿はかつてそう語り、僕以外の外の人間とは、キャンパーであっても食事を共にしようとしなかった。それでも、活動の度に誰かしらが蔡玩卿と仲良くなり、一緒に写真を撮って、それを蔡玩卿のうちの壁に飾る。あるとき、滅多に来ない蔡玩卿の姪が村に来て彼女の部屋に入り、驚いた。これほどたくさんの写真が貼ってある。日中の若い学生たちと彼女が一緒に写っている写真だ。リンホウ村にはトイレもできた。家も新しくなった。道路も舗装されている。村人たちには「またあいたい人」「また必ずあいに来る人」ができ、表情にも張りが出てきた。
家族は、以前に比べれば来やすくなったと語る。

(写真)村にやってきた周辺地域の子供たち

(写真)村人たちはどんどん開放的になっていく
関連記事:
投稿者について
Ryotarou Harada: NPO「家-JIA-」創設者。 1978年生まれ、2002年2月広東清遠楊坑村ワークキャンプに初参加。2003年早稲田大学政治経済学部卒業。快復村に卒業直後の2003年4月から1年半住み込み、2004年に日中韓の発起人6名でJIA創設、事務局長就任(2004年~2015年)