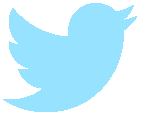第3回 「ワークキャンプ」が生み出す人と人とのツナガリ

(写真)村のニーズに応じて、ボランティアが1-2週間村に住み込んで活動する
ワークキャンプの起源
そのような中国のハンセン病快復村にて、僕らは「ワークキャンプ」と呼ばれる活動を行っている。
ワークキャンプは1920年、スイス人ピエール=セレゾールによって提唱される。良心的兵役拒否者であったセレゾールは第一次世界大戦後、「真の和解は議論によってではなく、無償の労働によって果たされる」という信念のもと、史上初のワークキャンプをフランスのヴェルダンで開催する。
ヴェルダンは第一次世界大戦中、ドイツ軍によって徹底的に破壊されたフランス北部の町だ。セレゾールはそのヴェルダンの再建を行うワークキャンプの開催を決め、ヨーロッパ中から参加者を募る。参加希望者の中にはドイツ人の若者も含まれていた。
ヴェルダンの人々はワークキャンプ参加者にドイツ人を見つけると、石を投げつけて罵る。しかし、それでもヴェルダンの再建のために黙々と働くドイツ人青年を見、ヴェルダンの人々は次第に、彼らを「ドイツ人」という集団として見るのではなく、「◯◯さん」という個人として接するようになる。
このように、ワークキャンプには、インフラ整備としての意味だけではなく、「集団と集団」の関係を徐々に越えて「個人と個人」の関係を築く力がある。一群の人々を集団としてくくると、人間は残虐な行為に及ぶことがある。しかし、その集団の中にいるひとり一人の顔が見える場合、そして、その人と個人的な関係を結んでいる場合、状況は変わってくるだろう。セレゾールはこのワークキャンプの力に、平和な世界をつくる糸口を見る。
この活動はアメリカを経由して第二次大戦後、日本に伝わる。アメリカ人が広島で家屋や集会所を再建するワークキャンプを行っていた。「鬼畜米英」と罵っていた国の人々が日本のために活動する姿に打たれ、日本人は活動に参加し始め、1953年にはワークキャンプ団体を日本に設立し、活動を根づけていく。1960年代になると、奈良での「交流の家建設運動」(http://leprosy.jp/people/plus03/)以後、ハンセン病を活動のテーマとする。1970年代になると日本人が韓国のハンセン病定着村にもたらし、韓国人も参加するようになり、韓国にワークキャンプ団体が設立される。そして、2001年、日本人と韓国人が中国のハンセン病快復村に活動をもたらした。
自発意志という意味での「ボランティア」
このワークキャンプという活動は、「ボランティア活動」のひとつだ。日本語の「ボランティア」という語には様々なイメージがついているが、ここでは英語の“Volunteer”の意味で使う。“Volunteer”はもともとは「志願兵」を指す。国家などの巨大な権力によって強制的に徴兵された兵士ではなく、自らの意志で志願した兵士だ。つまり、ワークキャンプに参加する人々は誰からも強制されたのではなく、自らの意志で活動への参加を決めている。自発意志で参加するのであれば、国籍、宗教、思想、性別、年齢、障害の有無などの背景は一切問われない。
ちなみに、ワークキャンプでは活動参加費用も自分で負担する。活動地までの交通費、期間中の食費、生活費はすべて手弁当であり、手当は一切出ない。その分だけ、自主的に活動に参加しようという意欲が高まる。また、誰からの援助も受けていないので、援助者の意向を気にする必要はなく、活動の方向性や内容を自ら考え、決定することができる。
現場に住み込む
また、ワークキャンプでは、活動参加者は社会問題に直面しているその現場に住み込む。スマホによって社会問題について調べるだけではない。活動地の最寄りのホテルから現場に通うのではない。現場に住み込んで、現地の人々と生活を共にし、話したり、触れたり、嗅いだり、味わい、笑い、怒り、泣きと、自らの五感を使って直接体感していく。
そこで、ワークキャンプを準備する「ボランティア」たちは、活動準備の第一段階としてまずハンセン病快復村を訪れ、村のニーズの下見調査をする。そこでハンセン病快復者たちの生活を見、また話し合ってプロジェクトを共に決定する。そして、プロジェクトの必要期間に合わせて、ワークキャンプ本番では1-3週間村に住み込む。村の空き部屋を宿舎とし、村の台所やかまどを使い、市場で買い出ししてきた食材を大釜で料理し、快復者と共に食べ、飲み、寝る。その間はスマホやパソコンを離れ、原始的な生活を村人と共に送る。
ワークキャンプで生まれる人と人とのツナガリ
中国のハンセン病快復村でのワークキャンプは、主にインフラ整備を行ってきた。それぞれのハンセン病快復村のニーズに合わせ、トイレを建て、水道を引き、家屋を建て替え、道路を舗装する。
しかし、ただトイレを建てることが目的であれば、素人の学生ボランティアたち20名、30名が快復村に泊まり込み、建設業者1-2名の指導のもとに建設を行う必要はない。そもそも、ボランティアたちの交通費や食費、生活費などを寄付に当て、プロの業者が立派なトイレを建設すればよい。なぜ、あえて、ワークキャンプという方法を採るのか。
広東省潮州市の快復村でトイレ建設のプロジェクトを無事終えた僕は、それを村人の蔡玩卿(第二回参照)に報告し、どう思うかを訊いてみた。蔡玩卿はこう答える、
「確かにトイレがあれば便利ね。でもね、私はね、これでもいいの」。
そう言って蔡玩卿は自分の座っている木のベッドの下を示す。そこにはバケツがおいてある。
「トイレよりも大切なこと、私にとって嬉しいことはね、おまえさんがここにいることなんだよ」。
蔡玩卿はこのころ、ほとんど眼が見えず、その後全盲となった。キャンプの初日、初めてあったときは、薄暗い部屋で爆音でラジオを聴いていた。僕の存在に気づくと怯えるように後ろを向いた。しかし、毎朝水くみを手伝いながら彼女の家を訪ねると、徐々にあいさつをかわすようになり、爆音のラジオを止めてくれるようになり、タバコをくれるようになり、お茶を飲ませてくれるようになる。覚えたての潮州語を僕が少し話すと、腹の底から笑ってくれるようになる。
彼女を訪ねて部屋をのぞくと、背筋をピッと伸ばしてタバコの煙をくゆらす姿があった。そのたたずまいからは、どこか高貴な、気高さを感じた。
ワークキャンプにおける共同生活・共同作業を通し、そんな関係が生まれていく。それは、快復者に物資を届けて集合写真を撮ったら即帰るような活動では味わうことができない。集団と集団の関係ではなく、支援者と弱者という関係ではなく、健常者と病者という関係ではなく、「蔡玩卿と原田燎太郎」という関係ができる。
そこに、ハンセン病差別は存在しない。

(写真)ワークキャンプで生まれる人と人とのツナガリ
関連記事:
投稿者について
Ryotarou Harada: NPO「家-JIA-」創設者。 1978年生まれ、2002年2月広東清遠楊坑村ワークキャンプに初参加。2003年早稲田大学政治経済学部卒業。快復村に卒業直後の2003年4月から1年半住み込み、2004年に日中韓の発起人6名でJIA創設、事務局長就任(2004年~2015年)