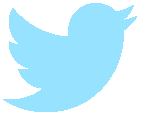第6回 地元の学生ボランティアによる自主的・継続的な活動

(写真)中国人初のワークキャンパー・朱佳栄
このようにして、徐々にハンセン病快復村は社会に開かれていく。そうする上で、鍵となるのは、地元の学生による自主的な活動の継続だ。とにかく、人が来続けることによってのみ、ハンセン病への偏見と差別は解消されていく。
しかし、地元の学生にとって、同じ地元人とはいえ、ハンセン病快復者の存在は「他人事」だ。それをいかに「自分事」と思ってもらえるか。自分事と思えなければ、活動を行い、継続することはありえない。
2002年9月、初めて広東省潮州市リンホウ村を訪れたとき、リンホウ村まで案内してくれた広東省のハンセン病関連NGOの職員に、「地元の大学に行ってワークキャンプ参加者を募りたい」と話した。その答えは、
「中国人の学生はこういったボランティア活動には参加しないので、大学に行っても無駄だ」。
ハンセン病快復者自身もこう語る。
「中国人の大学生は15年経っても活動に参加することはないだろう」。
無理だと言われると余計にやってみたくなる性分の僕は、何とか潮州市の大学に案内してもらい、先輩の西尾雄志と共に活動の説明を行う機会を得る。僕らは50名ほどの学生の前で、「ハンセン病」や「ボランティア」、「ワークキャンプ」などについて下手くそな英語で語る。僕らが話終わると、学生たちは机と椅子を鳴らして教室を一斉に去って行った。
ひとりだけ残っている。朱佳栄という名の彼は、「ボランティアはできないけれど、通訳ならできる」と言ってくれる。2002年11月に3週間かけて行う第一回リンホウ村ワークキャンプにて、最初の6日間だけ通訳として参加してくれることになる。
「ホントに丁寧で、話していて心地よく、村の外の人より親切だった。人を気遣う方法を知っているみたいだ」。
朱佳栄は初めて「ハンセン病快復者」と話した感想をこう語った。彼らが何十年も隔離されてきたことを伝えると、
「わかってる」
と朱佳栄はうつむき加減に横を向き、何度もうなずいていた。
それ以来、朱佳栄はリンホウの人々と打ち解けている。しかし、決して村人に触れようとはしない。中国の人々はよく握手や肩を組むなど肌が触れ合うものだが。
そして、ワークキャンプ最終日。朱佳栄は僕らを迎えに来てくれた。僕らは村人ひとり一人に別れをつげて回る。最後は、蔡玩卿(第2回、第3回参照)のところだ。
「ハア、ハア、ハア、ハア……」
薄光が射し込む部屋で、蔡玩卿は薄い布団をかぶり、うつぶせに横になっていた。蔡玩卿が搾り出す言葉を、入り口にたたずむ朱佳栄が通訳する。帰路の安全を祈る言葉だ。
時々、苦しそうに息が高くなる。蔡玩卿は、彼女の手をさすっている島倉陽子(日本人キャンパー)に、おまえさんは親切だね、と泣く。蔡玩卿の涙を拭く松村泉(日本人キャンパー)。

(写真)蔡玩卿(右)と日本人キャンパー
僕はいたたまれなくなり、外に出て座り込み、尾てい骨を震わせて、泣いた。
村人の郭聯浩は僕の肩に腕をおき、
「蔡玩卿は姉のような存在だ。みんな死んでいく……」
と涙を流し、声をあげて泣いた。
朱佳栄はしゃがみこんで郭聯浩の肩を抱き、うつむく。部屋から蔡玩卿の声がする。
「私のことは心配しないで、幸せに日本に帰りなさい。謝謝、多謝……」。
朱佳栄は彼女の部屋に入り、しゃがみこんで蔡玩卿を見た。陽子はひざをついて蔡玩卿の手をさすりつづけている。と、朱佳栄は、木の板のベッドに近づき、指が小さくなった蔡玩卿の手を両手で包み込んだ。しばらく動かない朱佳栄と蔡玩卿。
「謝謝你、多謝你」。
蔡玩卿はそう繰り返す。
帰国後、朱佳栄から手紙が届いた。
「初めはワークキャンプのことを何も知らなかった。燎太郎が助けを必要としていたし、日本の文化を知りたかったからキャンプに来てみたんだ。最初は、通訳だけやっていればいいと思ってた。でも、想像を超えた現実が待っていた。村は街から遠く離れていて、村まで行くのは大変だった。そのうえ村の生活状況はとても苦しかった。
初日、荷物を置いた後、村人の家に一緒にいったね。何人かの村人は足がなく、指がなく、目が変形していた。僕は少し恐かったが、敬意を払った。それでも、僕はまだ病気を恐れていた。だから、燎太郎が村人と握手するのを見て本当に感動した。
君たちと一緒にいればいるほど、だんだん深く君たちのことを知るようになった。協力の精神―例えば食器を一緒に洗うこと。独立の精神―例えば、言葉もわからないのに市場に自分たちだけで行くこと。働き方―歌を歌いながら食器を洗ったり、汗を流した後にビールを飲んだり。
キャンプ最終日のことは忘れられない。人生における重要な教訓を学んだよ。あの時、蔡玩卿が死にそうになってたよね。彼女のうめき声を聞いたとき、彼女の手を君たちが握ったとき、君たちの涙を見たとき、僕は人生って短いんだなと思った。僕たちは気遣いを示さなければいけないと思った。いつか僕たちも年を取り、病気になり、助けと愛を必要とする。今では家族のことが前よりも好きになったよ。僕は人を愛することを教えてもらったと思う。
僕たちのワークキャンプに参加する人をどんどん増やそう。僕のように、ワークキャンプは人の人生を変える。初めはまったくわからなかったけれど、今、僕はワークキャンプの精神を理解し始めた」。
朱佳栄は「君たちのワークキャンプ」ではなく、「僕たちのワークキャンプ」と書いた。
これを見たとき、僕は確信した、
「中国人の学生たちはワークキャンプをやるようになる」。
2003年3月大学を卒業し、僕はその4月からリンホウ村に住み込むことに決めた。リンホウ村の人々から人生について学びながら、リンホウ村の地元の学生がリンホウ村で自主的・継続的に活動するその芽を育てていくためだ。
日本人が下手くそな英語で活動を説明するのではなく、朱佳栄が中国語でクラスメートに活動の説明をするようになると、多くの中国人学生が活動に関心を持ち始め、2003年8月には師範学院の学生11名がリンホウ村ワークキャンプに参加し、10月にはワークキャンプ団体が設立された。その中でもとりわけ熱心に活動する学生・蔡潔珊は他のハンセン病快復村にも行きたいと言い、僕は広州の学生を誘って広東省清遠市にあるハンセン病快復村・ヤンカン村を訪れ、2003年8月に日本と広州の学生が合同でヤンカン村にてワークキャンプを開催する。広東省湛江市出身の広州の学生は湛江でもワークキャンプを行いたいといい、2004年2月、湛江、広州、日本の学生が湛江市トゥーグアン村でワークキャンプを開催する。同じ頃、広州、日本、広西の学生が広西壮族自治区桂林市ピンシャン村でワークキャンプを開催し、2004年8月には広州、雲南、日本の学生が雲南省楚雄州フオシャン村でワークキャンプを開催する。
中国にはハンセン病快復村が600ヶ所ある。そのすべてで活動しようと、僕らは活動する村の数をどんどん広げていった。新しい村を開拓する度に地元の学生を活動に巻き込んでいった。「中国」と一言で言っても、とにかくでかい。地域ごとに言葉も文化もちがう。よそ者が活動を地元に持ち込むことは大切だが、ハンセン病快復者のニーズに基づいて活動を継続的に行うことができるのは、村からの距離も近く、言葉もわかる地元の学生たちだ。
こうして、2004年8月までに僕らは3つの省にあるハンセン病快復村7つで活動するようになった。すると、資金が不足し始める。当時はまだ建設ニーズが高かった。トイレ、水道、家屋、キッチンなどを建てる必要があったので、建設費用がかかる。情報の共有もうまくいかなかった。当時、学生に連絡先を聞くと携帯電話を持っておらず、寮の固定電話の番号を教えられることも少なくなかった。メールアドレスを持っている人もあまりおらず、学生たちはこの活動のために大学の近くにあるネットバーでメールアドレスを取得した。そんな状態だったので、誰がいつどこでどんなキャンプを組織し、その準備状況がどうなっているかを把握するのも一苦労だ。また、ワークキャンプをキチンと組織するノウハウを持った学生も圧倒的に少なかった。ただひたすら想いのみで動いている感じだった。
この状況を受けて、当時中心的に活動していた中国人学生4人と僕はNGOを設立し、資金・情報・人材の不足に取り組み、ワークキャンプを発展させていくことにした。ただ、それを僕らが一方的に決定しても、各地の学生や村人たちが納得しなければ機能しない。そこで、僕らは広州に各地の学生と村人100名以上を招き、当時のワークキャンプが抱える問題についての話し合いを持つ。議論の方向は自然と、資金・情報・人材に向き、結果としてNGOを設立してそれらの問題に取り組むということになった。こうして、2004年8月30日、JIAが設立された。
関連記事:
投稿者について
Ryotarou Harada: NPO「家-JIA-」創設者。 1978年生まれ、2002年2月広東清遠楊坑村ワークキャンプに初参加。2003年早稲田大学政治経済学部卒業。快復村に卒業直後の2003年4月から1年半住み込み、2004年に日中韓の発起人6名でJIA創設、事務局長就任(2004年~2015年)