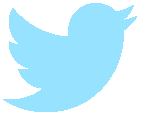The Edge #4

(写真)キルギス遊牧民が暮らす谷。 9時間以上の旅路のあと、ようやく谷に着いたとき谷はすでに真っ暗だった
連載4回:旅1日目ー03
空に明るさが失われ、辺りは青白くなった。寒さが私の不安を駆り立てる。少女UHは疲労困憊だ。バイクを停めて小刻みに手を振っている。ハンドルを固定する握力が限界なのだろう。見ると本当に小さな手だ。辺りは午後4時過ぎの太陽だろうか。出発してすでに5時間は雪道を運転している。心配そうな少女UHを説得して、私が運転を代わることにした。実は数時間前にも私は運転を試みたのだが、川を渡るはめになり、後輪をバキバキと凍った川に沈めてしまい、進行不可能という失態を犯してしまっていた。その後なんとか押して川岸へ着いたが少女UHの信頼を損なうこととなった。そういうわけで、今回は気合いを入れ、相当集中して運転していた、はずだった。しかし、バイクは玩具のように転げ、2人は再び積雪の上へ放り出される。「大丈夫?」と彼女に駆け寄ると互いに顔を見合わせ苦笑した。その後何度か転倒を重ね、段々と要領を体得していった。左下に落差のある崖を目視しながらの走行は、スリルを超えて緊張のため背筋が数センチ伸びる感覚だった。後輪が右に滑り車体が崖へ傾くと、左足で地面を蹴って体制を立て直した。腕も足もパンパンに張っていた。この道のりを少女UHは何時間も運転してきたと思うとつくづく彼女の逞しさに敬服し、また小さな体が疲れ果てている事実を身をもって感じた。
日が沈むか沈まないかの頃に、仲間達が待つ谷越え地点へ到着できた。後部座席の者は歩いて谷を下る。道らしきものを崖下に確認できたが、そのすぐ先は崖に隠れてみえない。私が運転すると言ったけど、相棒は決して譲ってくれなかった。同行中の仲間にも彼女に従えと目で合図を受けた。心配しながら彼女の後ろについて見守っていると、突如ブレイキをかけたせいで、彼女はバイクもろとも滑り出した。目の前は崖。私は焦るよりはやく走っていた。滑るバイクの後部座席を掴んだと同時に両足で踏ん張った。だがいっしょに滑り落ちる。体が倒れると同時にその力を利用して、バイクごと転倒させた。背負っていたカメラが背骨へあたる痛みを感じた。バイクは崖前で停まり、ホット胸を撫で下ろした瞬間、後ろで笑い声が聞こえた。キルギスの人々はどこまで陽気なのだ。必死に人命を救ったと思ったのに、少女UHまでケロッとしていた。とにかく、自分一人胸を撫で下ろした。
しばらく下ると目下に広がる村SRの壮大な景色が一望できた。俗にいうトワイライトの時間帯でそれは美しかった。夕食を仕度しているのか煙が点々と昇り、陽が沈んだ後の数分間の青と紫のなんとも表現しにくい色合いが、雪山の無地に溶け込むように映えていた。長い道のりをここまで来たことが急にうれしくなった。
中腹から約1時間後、さきほど眺めた村を左方向に走り抜けていた。人のお尻以上ある石をバイクで右へ左へ避けながら更に進む。辺りはすでに真っ暗だが、川を渡っていることを耳で確認できた。「後輪沈むなよ」と心のなかで祈っていた。川を渡り終えると先方を行く2台が停車した。近づくと見覚えのある女性と子供が出迎えてくれた。長男JMの奥さんと息子だった。こうして約9時間半の旅は終わった。ソーラーパネルを使い発電させた電球が、細々と皆の笑顔を照らし出した。それぞれ目で確認し合い、笑顔で喜び合った。するとJMが麻の袋から白酒を取り出した。お祝いするらしい。ドンブリになみなみと注がれた酒は、回り回って私のところへやってきた。いっぱいにつぎ足された白酒をほこりで詰まる喉に流し込んだ。胃のほうへスッと冷たくたどりついた白酒が、その後カッと燃えるように熱いのを感じた。2杯目のドンブリはさすがに飲めなかった。私はその夜4回嘔吐した。目を閉じると転倒の恐怖が蘇り、吐き気は治まらず遅くまで寝つけなかった。
関連記事:
- 国境はいきている 1「交易都市・瑞丽市」 BBパートナーリレーコラム「日中コミュニケーションの現場から」第4週 / 0 Comments
- 日中すれ違い4 「民間ビジネスなら、日中相互無関心を突破できる」 BBパートナーリレーコラム「日中コミュニケーションの現場から」第3週 / 0 Comments
- 国境はいきている 2「廃村でなかった拉孟(松山)」 BBパートナーリレーコラム「日中コミュニケーションの現場から」第6週 / 0 Comments
- 国境はいきている 3「新疆再来 #1 : 中継地カシュガル」 BBパートナーリレーコラム「日中コミュニケーションの現場から」第4週 / 0 Comments
- Slice of Life #1 / 0 Comments