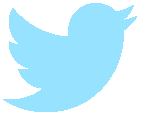Vol.4 日本料理店経営(北京和僑会理事)北京市有薫一心餐飲有限公司総経理 高山貴次氏(34)
1人め:ヤンジュン 閻郡(42)
「これぞ中国」を見せてくれた厳しく優しい老北京

(写真)高山 貴次
<プロフィール>
たかやま たかつぐ。1976年東京都出身。実家は東京・赤坂の九州郷土料理店の名店『有薫』。3人兄弟の二男。95年3月高校卒業後、北京語言大学に留学。97年帰国、サラリーマンを経て、2001年旧正月に再び北京へ。日本料理を提供する北京市有薫一心餐飲有限公司を設立と同時に1店舗目をオープン。現在は北京で日本料理店、バーなど8店舗を展開。2011年春、千葉・幕張にも出店。
高山が高校を卒業した1995年の日本は、阪神・淡路大震災、急激な円高などの外的なショックが重なり、経済が足踏み状態だった。そんな中、改革開放を進めていた中国市場が注目されるようになっていた。
高山の実家は祖父の代から九州、東京で有名九州郷土料理店を営む。90歳を過ぎるまで店に出た祖父も、2代目を継いだ父も、店にこの人ありきと言われるような、存在そのものが店の看板となるキャラクター。高山は、そんな祖父や父の姿を見ながら3人兄弟の二男坊として育った。
「何か人と違ったことをやりたい、人と違ったところで生きていきたい」。大学進学を考えていた高校生の高山は、メディアが盛んに取りあげる中国に惹かれた。
高山:将来を迷っていた時、テレビで「これからは中国だ!」としきりに言っていました。それを見て「中国語を身につけて何かしたい」と漠然と考えるようになりました。それで大学の中国語学科を3つ受験しましたが、全部落ちてしまいました。辛く厳しい浪人生活を覚悟していたのに、なんと親は「浪人は許さない」と。
BillionBeats:なぜ北京に留学することになったんですか?
高山:親父から留学を勧められたんです。正直言うと、その時最初に頭をよぎったのは「これで1年間勉強しなくていい、きっと北京に行ってしまえばいいことがある(笑)」。その頃、僕の中国のイメージというと香港の飲茶。「美味しい飲茶を毎日食べて、きれいな女の子がいっぱい」。まだ高校生ですから考えることと言ったらこの程度でした。

(写真)父と結託して北京留学の
甘い夢を見させた閻さん。
「この笑顔に安心してたのに..」(高山)
BB:すごく若者らしいですね(笑)。
高山:父には中国人の知り合いがいたんです。北京出身の閻さんというその人は、東大大学院に留学中の26歳でした。父に紹介されて初めて会った時「北京なら私の両親が住んでいるので安心してください」と言われました。さらに、彼のお父さんも北京ですごい力を持っているという話もしてくれて、不安がなくなりました。
閻さんは「留学前に日本で中国語は一切勉強しちゃダメ」と言うんです。発音がおかしくなるからとアドバイスされ、その言葉に従って本当に勉強しませんでした。
ついでに「なぜ、留学先に北京を勧めるの」と聞いたら「あなたは上海に行くときっと遊んじゃう。北京でがんばれ」と(笑)。
北京から入学書類が送られてきて、自分が知らない間にどんどん留学の手続きが進んでいました。大学のパンフレットがまたとんでもなくボロボロで、「中国は今、本当に発展途中なんだなあ」と、少し不安になりました。
事前に寮を申し込まなくてはならなかったのですが、寮といっても「2人部屋・風呂なし・トイレ共同」から、ホテルのようなフル装備の部屋まで幅広いんです。さすがにトイレも風呂もない部屋はいやだったので「ルームメイトはいてもかまわない、エアコンもなくてもいいから、テレビ、トイレ、シャワーがある、真ん中ぐらいの部屋にしてください」と閻さんに強くお願いして手配してもらいました。
「異国の地に行く」。同級生とは違う世界に一歩踏み出そうとしている自分が、カッコよくも思えた。高校を卒業してから留学が始まる9月までの半年間、高山はアルバイトをしながら自由な時間を過ごす。
「北京に行ったら、すごいことになるぞ」。北京生活への期待で胸を膨らませていた。
高山:8月下旬、僕と親父と閻さんほか4人で初めて北京へやって来ました。降り立ってから入学までの数日間、閻さんが北京観光や食事に連れて行ってくれました。豪華な料理を食べ、夜はきれいなお姉さんがいるお店にも連れてってもらい、自分が思い描いていた中国がそこにありました。
BB:入学してからは?
高山:一切中国語を話せない僕には入学手続きだって大変なんです。閻さんに電話をかけて来てもらい、助けられながらようやく入学手続きをしたその足で寮に案内されたのですがーー。木の机の引き出しを開けると、驚くような数のゴキブリが……。とりあえず見なかったことにして閉めました。でも部屋を見回せば、ベットの上には体育のマット運動で使ったような古いマット。机には古ぼけた魔法瓶とブリキの洗面器みたいな食器が。刑務所かと思いました。唖然としている僕を横目に閻さんは「次があるから」とそそくさと帰ってしまったんです。
「ちょっと待って、風呂は?」。……。これは騙されたなと思いました。
BB:散々なスタートだったんですね。
高山:天国から地獄です。
食堂のごはんは油が合わず、1カ月くらいお腹の調子がおかしいままでした。そんな時、1年間使えるオープンチケットを持っていたことに気がついたんです。留学前に親父と閻さんが束になって「海外といってもこんなに近いんだから、いつでも行ったり来たりすればいいじゃないか」と僕を諭した時、買い与えられたのは往復のオープンチケットだったんです。
本当に体調が悪かったので、1、2週間日本に帰って調子が整ったらまた戻ってこようと思い、親父に電話したんです。すると、北京に来る前はあんなにいつでも帰ってこいと言っていたはずが「一度志を持った人間がやすやすと帰ってくるんじゃねえ」とガチャン。なぜか、閻さんまで音信不通に……。
後で聞いたところによると、閻さんもだいぶ心配したらしいですが、敢えて連絡をしなかったみたいです。当時の話になると、閻さんは未だに「あれ、そんなことあったっけ?」ととぼけていますが(笑)。(文中敬称略)
2人め:ワンチュエンガン 王全剛(42)
その熱意が、北京に戻らせた
90年代、北京の留学生活は電話をかけるだけでもひと苦労。極寒の中、数少ない国際電話がかけられるボックスの前の長い列に並ぶしかなかった。寮の電話事情はというと、各階に1台の黒電話があるだけ。その電話さえ、荒くれ者の留学生により破壊されていていた。
思い描いていた留学生活とはかけ離れた、寮での過酷な生活。カルチャーショックの中で、高山はーー。
高山:中国にいても、日本の大学でキャンパスライフを楽しんでる友達とつい比べてしまうんです。例えば、大学のサークル活動ひとつとっても中国にいるとイメージが湧かなくて「コンパって、なに?」という感じでした。
「こんなところで羊肉を食べて、オレは何をやってんだろう」と思うこともありました。高校を卒業したばかりで何をするにも不器用で、留学生の輪に入って楽に生きるのすらままならなかったんです。
日本の友達に国際電話しようにも料金が高い上に、国際電話ができるボックスが少なくて。200元(2011年12月現在・約2200円)もするカードを買って、行列に並んで電話をかけてました。北京には日本語ができる閻さんの弟さんがいたのですが、連絡もとれなかった。北京でとりあえず生きてはいるものの、生活、食事、習慣など、いろんなことに耐えていたような気がします。
BB:いちばん辛かったのはどんなことでしょう?
高山:よくお腹を壊したのが辛かったです。
ある時、中国人が購買部で親子丼やかつ丼、チャーハンのような日本食の弁当を売りに来ていたんです。学生食堂がイヤでたまらなかった僕には神様に見えました。大して美味しくはないけれどちゃんとカツ丼。「美味しくない」と文句を言いながらもしょっちゅうお世話になっていました。その弁当を売っていた中国人が、ビジネスパートナーとなる王全剛さんです。僕の実家が日本料理店を経営していると知ってからは、これはどう作ればいいのか、何を売ればお客さんが増えるかといった相談を受けるようになり、僕も喜んでアドバイスしてました。
BB:仲よくなったきっかけは?
高山:留学2年めの冬、寒い日にある店で牛丼のようなものを食べたのですが、どうしても生卵を溶いて食べたくなって。「やばいかなあ」と思いながらも食べたら見事に当たってしまい、部屋でのたうち回っていたんです。ルームメイトが僕の惨状を王さんに話したみたいで、雪が降る中「大丈夫ですか?」と、お弁当と果物を持ってわざわざお見舞いに来てくれた。うれしかったです。彼の方が6歳年上でしたが、いい友達になれるかもと思いました。

(写真)01年、高山が北京に戻って一緒に開業した当時の王さん。事務所にて
2年間の語学留学後は北京大学への進学を考えていた高山だったが、北京に住んでみて感じたのは「中国への失望」だった。「周りが言うほど中国は成長しないのではないか」。これが高山の出した答えだった。中国語も上達し自信をつけた高山は、2年間の留学生活に終止符を打ち、日本で就職する。
その3年後の2000年、「将来は一緒に日本食料理店をやろう」と冗談で話していた王が来日。バリバリのサラリーマンとして働いていた高山を訪ねてきたことから、高山の新たな人生が動き始めた。
高山:王さんは、96年には北京語言学院の近くで日本料理屋を始めていました。ところが、2000年頃になると、北京で日本料理店を経営するのに見よう見まねでは通用しなくなってきていました。危機感を持った彼は、家族や親戚から借金をして、日本料理とはなんぞやということを知るために来日したんです。約2週間、僕の西葛西のアパートに居候し、僕の仕事が終わるとレストランや居酒屋から寿司屋まであらゆる業態と価格帯の日本料理店に連れ立って出かけました。そして、その日体験した店や味を反芻しながら王さんの店づくりについて連日朝まで話し合いました。そんな中で、ぜひ協力してほしいと彼から誘われたんです。
BB:その時に王さんのビジネスパートナーになろうと決めたんですか?
高山:僕自身、97年に帰国してからも中国に関するニュースが流れると知らず知らずに見入っていたりして、ずっと気になっていました。99年頃には街がキレイになってきたなどという報道を見るようになり、中国はこれから伸びていくんじゃないかと改めて思い始めていたんです。
でも、中国で日本料理屋を始めたものの中国人に乗っ取られた、などの日本人と中国人のだまし合いみたいな話は聞こえてきていました。それで、王さんに、僕が聞いた悪い例をくまなく話し、想定されるあらゆる状況を全て話し合いました。そして、それでも一緒にやっていけるんじゃないかと思えた。それで、北京に戻ろうと決心したんです。
BB:サラリーマンを辞めることに迷いはありませんでしたか?
高山:もちろん迷いましたよ。でも、会社員として経験も浅く失うものがなかったので「とりあえず行ってみようか」と、留学と同じようなノリで行動に移しました。
赤坂の店は兄貴が継いでいましたし、二男の僕がちょうど「こいつにとりあえず何かやらせてみよう」と言われるポジションにいたのは家族にとってもよかったようです。海外出店に憧れていた両親は、賛成してくれました。
2001年の旧正月、高山は再び北京へ。今度は北京で日本料理店を始めるために。2008年夏季オリンピックの北京開催やWTO正式加盟が決まるなど、中国が世界から注目され始めた時期でもあった。
「中国は今、俺を求めているんだ。俺が行くしかない」。根拠のない自信を胸に、父親から借りた200万円と自分で貯めた50万円の現金をポケットに入れて北京に乗り込んだ。

(写真)北京語言大学東門前にオープンしたての
記念すべき1号店(当時)
BB:最初から料理人ではなく、経営者としてやっていくつもりだったんですか?
高山:実家の日本料理店は創業者の祖父も二代目の親父も店の主として看板のような存在で、ふたりが僕のロールモデルでした。経営者、プロデューサーとしてやっていくのは僕にとって自然なことだったんです。だから北京でまず事務所機能をつくり、同時に1店舗めを北京語言大学の東門にオープンしたのですが、11月にはオリンピック開催の影響で立ち退きに遭ってしまいました。
ビジネスパートナーの王さんとも最初は意見が合わず、けんかばっかり。日本人と中国人ではこんなにも考えが違うのかと実感させられましたね。
BB:それにしても、王さんは運命の出会いとなりましたね。
高山:本当にそうです。現在、独自でビジネスをしている王さんは、一心グループの株主でもあります。
「どうしたら北京でやっていけるんですか?」とよく聞かれますが、事業の成功に法則はないと思うんです。
僕は人との出会いに恵まれているとつくづく思います。そう言うと「高山さんが人を大事にしているからですよ」と言っていただいたりしますが、仮にそうだとしても、人とのつながりのベースである出会いは運や巡り合わせですし、僕がなぜこんなにいい巡り合わせのもとにいられるのか、これを言葉で説明するのは難しいんです。
ふとした瞬間に心から「お天道様ありがとう」と思うくらい、運がよかったと思うことの連続です。でも今後どうなるか、一瞬先は闇。
僕は、2001年に「これからは中国だ」と思った延長線上にまだいます。もっともっと戦わなければいけないなあと思うと同時に、不安です。

(写真)オープン当時のスタッフと。高山、若干24歳。
BB:この10年で高山さんを取り巻く環境は変わりましたか?
高山:中国の一般の人がお金を持つようになり、プライドをもってある程度のレベルの仕事をするのが当たり前になった今、正直に言って、これから中国ビジネスをしたいという人にたやすく勧められない部分はありますね。
中国で出店して10年になりますが、そもそもこの10年の間に苦境をくぐり抜けて利益を出してきた日本人が果たして何人いるか、チャイニーズドリームをつかんだ人はどれくらいいるかーー。表面上はハッピーに見えても、誰もがひと言では語れない矛盾や葛藤を抱えているんじゃないでしょうか。
僕自身、10年経って今、中国はそんなに簡単ではないと思うようになりました。 (文中敬称略)
3人め:ガンヤンフォン 甘央凰(48)
偉大なるおばちゃんは‘大衆目線’
2001年の旧正月明けに事務所開設と同時に最初のお店をオープンした高山。
1年後、2店舗目を計画するも次第にパートナーと考えが合わなくなり、パートナーと別れ、自分で運営していくことを決意する。その時、パートナーや中国人スタッフのクッション役となった女性がいた。
高山:パートナーの王さんは別のビジネスを始めることになり、日本料理店の事業は僕がひとりでみることになったんです。当時、中国人スタッフが30人くらいいたんですけど、日本人の僕が彼らを束ねるのは大変です。それを一手に受けてくれた偉大なるおばちゃん、その人が今も私の下で働いている甘央凰さんです。
BB:どうやって知り合ったんですか?
高山:1号店の工事の真っ最中のある時、工事責任者がペンキを塗りながら「うちのかみさんを使ってくんないか」と。「昔、国営企業で会計をしてたんだよ」と言われ、ちょうど事務所にスタッフが必要だったので「ああいいよ。連れてきてみなよ」と安請け合いしたら、やって来たのは恰幅のいい、いかにも‘中国人のおばちゃん’。正直「やばいなあ」と思ったんですが、ひとまず事務所で採用しました。声がものすごくデカくて、ドアを閉めているのに甘さんの話し声が聞こえてくるんです。
BB:第一印象は最悪だったんですね。
高山:彼女にとって僕は初めての外国人でしたので、お互い微妙に壁があるかもと思っていたんですが、中国的おばちゃんのいいところで、遠慮なくズカズカと僕の内側に入ってきて、早口で聞き取りづらい北京語を弾丸のように繰り出すんです。
はじめは僕の意向をわかってくれなくて困ることがありましたが、彼女は頭がよく、すぐに理解してくれるようになっていきました。
2店舗目を計画していた当時、できれば3店舗目まで一気に出店したいとも考えていて、僕が経営に集中したい時期に彼女がスタッフとのやり取りを責任を持ってやってくれたのが非常に助かりました。例えばボーナス支給のタイミングで中国人スタッフのテンションを上げるにはどうしたらいいかという時、中国人の感覚を彼女は大衆の目線でわかっています。中国人一般の感覚に基づいて「こういうやり方がいい」と提案してくれました。

(写真)05年10月、北京の友人と全スタッフが参加した、北京市内の中華料理店での高山の結婚式は、甘さんがとり仕切った
BB:たしかに日本人ではわからない部分がたくさんありますよね。
高山:彼女はスタッフの不平不満などを僕の代わりに受けて、スタッフ間の微妙な調整をし続けてくれています。例えば、調理人から副調理長に昇進する場合、副調理長候補という時期があるんですが、その期間もきちんと副調理長待遇の賞与を与えたほうがいいとか、売上目標を3か月連続で達成した場合はスタッフの誕生日会の費用をもっと上乗せしようとか、スタッフのモチベーションが上がるようなアドバイスをしてくれます。
また、年に1回のスタッフとの個人面談には彼女が同席して僕の代わりにスタッフからいろいろな話を聞き出してくれます。例えば、皿洗いをしてくれているおばちゃんの家庭の悩みとか、僕では聞き出せないし相手も僕には打ち明けにくいいようなことも、甘さんがいるとわりと簡単に話してくれます。
そうやってひとりひとりから話を聞くと、それぞれがいろんな悩みを抱えていることがわかりますし、店で会った時に僕からも自然に声をかけられるようになります。若いスタッフはほとんど寮に住んでいるんですが、彼らはまだ精神的に弱い部分もあるので、彼らのお母さん的役割も担ってもらっています。
BB:彼女なしでは現在の一心グループはなかったということですか?
高山:彼女は体調を崩しながらも、自分のことより店を気にかけてくれるような人です。2号店を出した時には僕の代わりに現場を見てくれるなど、信頼関係という言葉では言い表せないくらいです。彼女がいなかったら、多店舗展開は実現していません。
中国で飲食業を経営していく現場には、日本とは違う難しさがあります。マニュアルなどなく、出会いの運やタイミングの問題もあります。そんな中で外国人の僕が抱える矛盾を全部受けとめてくれる。こんなやさしい中国人が本当にいるのかという中でやってこられたのは幸せです。
現在、高山は更なる事業拡大を目指し、事務所機能を強化するとともに、店舗では調理長とフロアリーダーを同じ権限を持つポジションにする、インセンティブ制を導入するなどの組織改革を行っている。
高山:漠然と、6店舗までは自分のテリトリーの中でなんとかなると思っていました。でも、7店舗以降になると、組織本部を強化しなければ広範囲に対応しきれなくなります。そこで事務所を会計部5人、仕入れ部3人、主任1人、秘書1人の構成に強化し、各店の幹部には権限を持たせて店の運営を任せてみることにしました。
そもそも、中国人の幹部たちは非常に独立心が強いですが、資金や営業許可許可などの問題で、自分で店を出すのは大変です。そこで、彼らに独立せずとも起業に近いチャンスがつかめる舞台を提供し、活躍に比例して年収が上がるようなインセンティブ制を導入しました。
BB:店舗ごとに競わせることにもなるわけですね?
高山:インセンティブ制を導入してからは、店舗によっては自分たちで工夫して原価率の低い材料で開発した商品が中国人のお客様に好評で、ひいてはリピートにつながったというケースもあります。まだ試行錯誤中ですが、確実にいい方向に動いていて、売上げも前年比で伸びています。
2001年、24歳の高山が、ホールスタッフ5人、裏方8人、事務所は24歳の高山と3人のスタッフで始めた90平方メートルの1号店を皮切りに、3店舗目でスタッフは50人を超えた。2007年には「和一心」と経済貿易大学店の2店舗をオープンし、現在、一心グループは6店舗を展開する。130人を越えたスタッフの団結力を強めるために、高山は年に3回、従業員が参加するイベントを開催している。
高山:毎年5月1日には朝7時から開店前の時間に、各店舗対抗の大運動会を行っています。入賞チームには賞品が出るので、店舗ごとに1カ月前から練習を始めて、面白いことにスタッフ全員でお揃いのTシャツをつくったりするんです。夏には全店休業にして従業員全員参加の遠足も開催しました。郊外でみんなで川下りをして、お昼を食べて、山に登って。そして、1年目から開いているのが大遊技会です。旧正月前に店舗ごとに2つの演目を披露してもらいます。このほか、3カ月に一度、誕生日会活動手当を支給しています。みんなでひとつの目標に向かって困難を克服するというのが狙いです。学生街にあるお店が多いので、暇な時期はスタッフがまとめて辞めたり、ケンカになったり、何かと問題が起きやすいのですが、それを回避するためにも役立っています。

(写真)圧巻、一心大運動会!
BB:これから中国という荒野に飛び込もうとしている起業家にアドバイスをお願いします。
高山:今、中国人スタッフを100人以上雇って事業を展開しているとは言っても、実力のある中国企業や中国人に同じことをされたら負けるのはわかっています。今後、僕の事業を真似されることもあるだろうし、真似した方が伸びる可能性も高いです。資金力、コネクション、どちらをとっても、外国人は中国人の足元にも及ばない。
それでも中国市場で闘っていくには、僕が甘さんという中国人を味方に得られたように、信頼できる中国人のパートナーを持つことは不可欠です。ビジネスパートナーでなくて妻や夫などプライベートのパートナーでもいいんです。
要は、自分が中国側に立てるかどうか。ここは中国ですから、中国人の視点に立って物事を考えられるかがポイントです。(文中敬称略)
関連記事:
投稿者について
BillionBeats:
- Vol.1 建築家(北京和僑会副会長) SAKO建築設計工社代表取締役 迫慶一郎 (41) / 0 Comments
- Vol.2 美容サロン経営(北京和僑会理事)北京朝倉時尚形象設計有限会社C.O.O・ディレクター 朝倉禅(34) / 0 Comments
- Vol.3 テニススクール経営(北京和僑会会員)レインボーテニスガーデン代表 藤本龍一郎氏(27) / 0 Comments
- Vol.4 日本料理店経営(北京和僑会理事)北京市有薫一心餐飲有限公司総経理 高山貴次氏(34) / 0 Comments
- Vol.5 リサーチ会社経営・安田玲美(北京和僑会理事) ー 北京世研伝媒広告有限公司・北京世研信息諮訽有限公司・等、CRCグループ10社およびエンジェルエンジェル服装服飾有限公司の総経理 / 0 Comments