Vol.1 建築家(北京和僑会副会長) SAKO建築設計工社代表取締役 迫慶一郎 (41)
1人め:ジャンシン(张欣) ディベロッパー・SOHO CHINA,CEO
「洗練と革新の35歳の女性社長。
堂々と確信を持って中国の現代建築を創造する彼女が中国への扉を開いてくれた」

(写真)迫慶一郎
<プロフィール>
さこ・けいいちろう:1970年福岡県生まれ。東工大大学院修士課程修了後、96年山本理顕設計工場に入所。2000年、山本理顕がコンペで勝ち取ったプロジェクト「建外SOHO」の担当者として赴任。04年、山本事務所を退職し、文化庁派遣芸術家在外研修員として米国コロンビア大学客員研究員に。同年、北京に事務所を開設。2008年、四川大地震被災地への学校寄贈プロジェクトを開始。2011年、東日本大地震被災地復興プロジェクト「東北スカイビレッジ」を開始。
迫が初めて中国に来たのは2000年。中国がWTOに加盟する前年である。めっぽうケンカに強い建築家として知られる社会派建築家・山本理顕のもとで2つの公共建築を担当し、ちょうど30歳になる年だった。
建築系大学のトップ・東工大で学んだ迫が建築家を目指した時、意識したのは欧米が主流の現代建築だった。香港を訪れたことはあったけれど、大陸は初めてという中国へは全く関心が向いていなかった迫が、その後、山本のもと、北京経済地区の開発プロジェクト「建外SOHO」のプロジェクトリーダーとして北京に駐在する。
2004年、「建外SOHO」第3期工事の終了を機に山本事務所を退職し、コロンビア大学客員研究員のポストを得てNYに渡ろうとしていた迫が、北京に事務所を開くことになったのは、ほんの偶然の出来事による。
それから7年。プロジェクト数は70を超え、現在は中国国内で300万平米スケールのスマートシティのプロジェクトも進行中。2人でスタートした事務所は、「建てたい」という意欲だけで海を渡ってきた20代の日本人を中心に38人の大所帯になった。
欧米の現代建築に憧れていた迫だが、中国での活躍が今では日本国内でも注目される。その迫に転機をもたらした中国人との出会いとは。

(写真)現場に常駐していた頃。北京の冬はとてつもなく寒かった
BillionBeats:11年前、2000年の北京は迫さんの眼にどのように映ったんでしょうか。
迫:カルチャーショックでした。それまで、北京がこんなに発達した都市だと思ってなかったんです。返還直前の97年に行った香港は、あれだけの高密度な都市に人とエネルギーが溢れているという印象でした。香港に現代建築デザインの先端があるわけではなかったけど、オルタナティブな都市のエネルギーに惹きつけられました。でも大陸にはステレオタイプなイメージしかなくて、人民服、自転車の波、万里の長城、カンフー。それぐらいのイメージしかなかったんです。
僕らがいるこの経済区・国貿は、今と比べると全然違いました。こんなにビル群はありませんでしたし、CCTVのビルだってもちろん影も形もありませんでした。ただ、東三環道路と天安門広場へと続く片道8車線の長安街はできていて、国貿の交差点には高層オフィスビルが建っていて、既に都市の姿は現れていました。車もけっこう渋滞していて我先に行こうとする車のクラクションが鳴り響き、エネルギーが溢れ返っていました。僕が想像していた京劇のような優雅な時の流れとは違うものがそこにはありました。
BB:迫さんの会社が入っている、この建外SOHOのコンペのために東京から来たんですよね?
迫:そうです。
磯崎新さんと香港の建築家・ロッコーイム、僕のボスの山本さんが指名コンペに誘われていて、その内容を聞き取るというのが僕の役割でした。
後輩を連れてケリーセンター(注:シャングリラ系列の高級ホテル併設のオフィス棟)のオフィスのデザインされた受付に行くと、お約束通りに美人の受付嬢がいるんです。間もなく出てきたブラジル人の秘書が流暢な英語で僕に話しかけてきました。中に通されてから会ったベネズエラ人のアントニオというインハウスの建築家は、英語もスペイン語も中国語も話す。スタッフ全員が英語でコミュニケーションをとり、イングリッシュネームで「クリスティーナ」などと呼び合うわけです。
なんとなく「素朴な中国」というイメージをもっていた僕らは、まずそのインターナショナルな雰囲気に圧倒されました。日本のアトリエ事務所勤めの建築家のたまごが、そんな洗練された場で1人前の扱いを受けることなんて、それまで日本では経験がなかったんです。ケリーセンターの高層階に紛れ込んでいくのと同時にインターナショナルな雰囲気に迷い込んでいった、そんな感じでした。
そもそも、迫がボス・山本理顕から「北京に飛んで来い」と言われたのも唐突だった。山本は2000年9月、北京大学の招待で北京を訪れていた。東雲のSOHOプロジェクトについての山本の講演を聴衆として聴きに来ていたジャンシンは、その場で山本さんを食事に誘い「コンペに参加しませんか」と持ちかける。
当時ジャンシンは35歳。見た目より若く見えるチャンシンは、山本からすれば「よくわからない小娘」。翌日、もっと詳しい話をと自宅に招かれた山本は、すでにジャンシンが建てていた高層マンション最上階のペントハウスの自宅に招かれ、度肝を抜かれる。そして、ジャンシンから「70万平米のプロジェクトだ」と言われ、ようやくジャンシンの本気度を理解し、担当として迫を、急遽北京に呼んだのだった。
ビザの申請をしてようやく迫がやってきたのは、2000年の国慶節だったのだ。
BB:ジャンシンがはじめに言ったことを覚えていますか?
迫: 彼女が言ったのは、このSOHOプロジェクトでは本当にいいものをつくりたいということでした。中国はこれから生まれ変わろうとしていて、これまでは企業といえば国営ばかりだったけれど、これからはどんどんベンチャー企業が出てくるからSOHO(small office home office:職住接近)スタイルにはニーズがあるんだという彼女の言葉には説得力がありました。
BB:ジャンシンとのミーティングはどういうものだったんでしょう?
迫:ある時、風水についてのジャンシンの意見を聞こうとしたんです。僕たちは普段設計をする時に風水を取り入れることはありませんが、施主は中国人なので、一応考え方を聞いておこうとしたんです。するとジャンシンは「風水なんて言ってる!」と、笑い出したんです。その後真顔でこう言ったんです。「わたしたちは古い慣習にとらわれて建築をつくっているんじゃない。SOHOというライフスタイルをつくろうとしているんです」
山本さんが日本の公団と共同で東雲のプロジェクトを2003年に建てた時、当初山本さんが提案していたSOHOの本来の考え方に基づく提案は、今後働く場と生活の場を同じスペースでというライフスタイルはもっとニーズが出てくるはずだから、ゲストが空間に入るとすぐにワークスペースがあるような空間のとり方が必要だというものでした。でもその提案は当時の日本では斬新過ぎたのか、結局公団に受け入れられず、旧来型のマンションとそれほど違わないものになってしまっていました。
ジャンシンの言葉は、そのお蔵入りしたプランを北京で実現するチャンスが巡ってきたということでもあり、山本さんも僕も興奮しました。
実際、「建外SOHO」は、入居者のニーズ次第で居住空間としてもオフィスとしても商業空間としても使える「マルチスペース」という考え方を軸に完成しました。

(写真)建外SOHOは北京の経済地区・国貿エリアの新しい顔となった
BB:ジャンシンのどういう点に施主として魅力を感じるんですか。
迫:SOHO CHINAとジャンシンはまだ全国区の知名度はありませんでしたが、デザインが大好きだということはよくわかりました。完璧主義で短気。打ち合わせで素材や質感、コスト、耐久性にまで全部専門レベルで話ができる人なんて、ふつうディベロッパーの社長にはいません。建築の素人なのに、図面の意図を汲み取って打ち合わせができてしまう、それくらい建築とデザインが好きな人です。施主がそれくらいデザインにこだわりがあるということは、僕ら設計をする人間はうれしいに決まってます。
彼女は新しいものや未知のものに対して、それが不可能だとか、手に入らないとは全く思わない人なんです。その、何事にも限界をつくらない姿勢は、僕らつくる側を大いに刺激するわけです。
彼女の実行力のすごさといったら、「長城の別荘群」というプロジェクトでは、あらゆるコネクションをつかってアジアから選りすぐりの建築家を集めて別荘群を建てるという極めてアグレッシブな試みで、ベネチアビエンナーレの特別賞を受賞しているんです。
現代建築の世界において全くプレゼンスのなかった中国を一気に世界レベルにひきあげようとするパワーを僕は見習いたいと思いました。その後ジャンシンは「TIME」誌の「世界に影響力を与える女性100人」にも選ばれました。
彼女が北京に戻ってきた当時の中国には建築やデザインの動きはまだなかったといってもいいと思いますが、ジャンシンは中国にチャンスを感じ、自分が中国でデザインを切り拓いていこうとしていました。そのモチベーションを僕は中国で生きていく「手本」だと思いました。
中国有数のディベロッパーを率いる女性富豪となったジャンシンは、その魅力的な笑顔とカリスマ性もあいまって最も有名な女性経営者のひとりとして知られる。生まれは北京。文化大革命の影響を受けた幼少期のことは詳しく語られていないが、14歳の時には香港で女工をしていた。そこで同級生が成功しているのを聞き、自分も女工で終わりたくないと一念発起し、渡英。ケンブリッジ大学を卒業後、アメリカに渡りゴールドマンサックス等で働いたあと、95年に北京に戻り、SOHO Chinaのチェアマンでもある夫と同社を起業している。
BB:迫さんは4年でプロジェクトの3期が終了すると山本事務所を離れましたが、その後はジャンシンとどんなふうにつき合っているんでしょう。
迫:建外SOHO4期、三里屯SOHOオフィスタワーの内装やクラブハウスの内装などで声をかけてもらっています。
ぜひいつかは大きなプロジェクトをやりたいです。
SOHO CHINAほどに時代を引っ張っていく建築をプロデュースするという意欲にあふれたディベロッパーはほかにないんじゃないかと思います。それを端的に表しているのが2008年秋のリーマンショック後の売値への影響です。中国の最大手ディベロッパーでさえ価格を下げて対応していた時、SOHO CHINAのプロジェクト・三里屯SOHOはさらに価格を上げて発売し、もちろん完売しました。その理由は、プロジェクト数が他社に比べて多くなく、ひとつひとつのプロジェクトを展開していくことで、土地を抱える不安が少ないというのが第一。それに加えて、SOHO独自のデザインと品質へのこだわりに価値が認められていることを示しています。
デザインとつくることに手を抜かずにやり続けることは、建築を巡る環境が日本や先進国とは異なる面のある中国では非常に根気が要ることですが、それは経済価値上も正しいということを証明しているディベロッパーだといえます。
10年前、北京が都市として萌芽したあの時期にジャンシンが北京にいたということ、そしてジャンシンに巡り会ったということは、僕にとって大きな転換期となったのは確かです。(本文中敬称略)
2人め:ファン・ジェンニン(方振宁) アーティスト・美術評論家
「無名の若者を地方政府のプロジェクトに推薦。中国を拠点にするきっかけをくれた」
2000年、30歳で初めて中国に来た迫は、ボス・山本理顕が「建外SOHO」のコンペに勝つと、2002年からプロジェクトリーダーとして北京に赴任。建築に対する考え方も技術レベルも異なる現場で、施工会社のおやじ達とケンカ腰でやり合う毎日が始まる。日本ではあって当たり前な建材が中国にはないために話が通じない。そのため仕方なく建材の製造から自前で手配する。そんなことの繰り返しを延々続け、2004年、3期工事が終了。迫は、これを機に山本事務所を退職し、米国コロンビア大学の客員研究員として1年間の予定でNYに飛ぶばかりになっていた。現代建築の先進国であるアメリカへ行くことは、迫にとって念願だった。
そんな時、思いも寄らない話が降ってくる。浙江省金華市の政府庁舎の設計をしないかという話だった。日本の建築界では、公共施設のプロジェクトを手がけると一流建築家としてのステージに一歩近づくことができる、そして話が受けられるようになるのは早くても40代半ばというのが定説だ。
若干34歳の、まだ事務所も持たない迫に願ってもないチャンスを与えようという奇抜な発想をした中国人はーー。
BillionBeats(以下BB):34歳でNYに行くことは前から決めていたんですか?
迫:いいえ。現代建築に関わっていくために、山本事務所の次はアメリカの設計事務所を体験したいと思っていたんです。僕らのようなアトリエ設計事務所勤務の若いスタッフは、1カ所に留まらずいくつかの事務所を体験することも珍しくありませんし、30歳を過ぎればそろそろ独立も視野に入れるのも当たり前です。僕はアメリカの建築への憧れもあったので、スティーブン=ホールという世界的建築家のNYのアトリエに行きたいと思っていたんです。ところが、ボスの山本さんが、それより研究の立場になってみたらどうだとアドバイスをくれて、それで文化庁の制度にも応募して、2004年秋から1年間、コロンビア大学の客員研究員のポストを得ることができました。
BB:それなのに、同じタイミングで中国に事務所を設立したんですね?
2002年、僕は建外SOHOの現場の事務所に詰めていて、毎日ディベロッパーや施工会社、メーカーの人たちといった中国人の人たちを相手に毎日ケンカ腰で打ち合わせをしていました。「なんでできないのか」「なんでないのか」といったレベルのケンカです。今思えば、自分の価値観がひとつしかなかったのかとも思いますが、山本事務所としても海外のプロジェクトは初めてだったし、70万平米規模のプロジェクトなんて山本事務所だけでなく日本中のアトリエ事務所が受けたことのないスケールなので、初めて尽くしの現場でした。これを成功しないといけないという気持ちが強かったんですが、たとえば当時の中国には「バリアフリー」の概念がなかったので、それを実施するための材料も技術もないし、そもそも理解しようとしない。それに対して「絶対にやるんだ」という気持ちで毎日戦っていました。そこへ「現場を案内してほしい」と取材に来てくれたのが、ファンさんとの初めての出会いです。
ファン・ジェンニン氏は紫禁城で学芸員を務めた後、90年代にアーティストとして日本で10年間活動し、2002年に北京に戻る。北京を拠点に表現活動以外に現代美術や建築の分野の批評家としても優れた見識を持つ。キュレーターとしても活躍している。
迫:モデルルームと敷地を案内し、ファンさんに敷地全体の計画を説明したのを覚えています。後で本人から聞いたんですが「こんな若くて小柄な日本人が大変な中国人相手に現場を仕切ってるのか」と驚いたそうです。ファンさん自身は当時40代の前半だったと思います。それ以来、時々建築家の集まりなどで顔を合わせることはありましたが、特に深く話をする機会などはありませんでした。
ところが、2003年の年末に突然ファンさんから電話がかかってきたんです。
「辞めるって聞いたけど、いつ辞めるの?そのあとどうするの?」
といつもの早口で矢継ぎ早に聞かれました。その頃には、建外SOHOの三期工事が終わる2004年1月で山本事務所を辞めることについて山本さんの了承を得て、少しずつ周囲の人にも話し始めていたので、ファンさんの耳にも入ったようでした。僕のひと通りの説明を聞き終えると、ファンさんが「ひとつ紹介できる仕事があるよ」と言うんです。それが金華の交通局の1万3千平方のプロジェクトでした。
金華市が開発区をつくり市政府が移転してくるにあたり、交通局が一等地を押さえ、
ランドマークにふさわしい設計をしてくれる人を探すよう、ファンさんに依頼していました。ファンさんは「中国の実状を理解していて若くて実力のある条件で考えると迫が真っ先に浮かんだ」と言ってくれました。
BB:ファンさんはどうして迫さんを推薦したんでしょう?
迫:まず、スケールの大きい建外SOHOプロジェクトを、建築をつくるレベルもやり方も考え方も中国で、中国人と中国語で交渉しながら進めてきた推進力を評価してくれたんだと思います。金華市政府側は、その地方として初めて海外の建築家を起用することについて非常に期待感がありました。でも一方で、あまりにエラくなった建築家では地方の役人とぶつかってしまう心配もある。ということで、中国の事情を理解する若い実力のある建築家が必要だったんです。といっても、僕はまだアトリエ事務所のスタッフでしかなかったんですが。
先方からの条件は、外貨を送金するのは手続きが面倒だから中国に事務所を持っている建築家でなければならないということでした。こうして、ファンさんに導かれるように北京に事務所をつくったんです。

(写真)中国で事務所をつくることになるとは夢にも思わなかった迫。金華市のこのプロジェクトは「金華キューブキューブ」
BB:でもNY行きも決まっていたんですよね?
迫:そうです。ただ、NYに行くからってこれを諦める理由もないわけで(笑)。両方やれると僕は思いました。金華のプロジェクトは1万3千平米で、それだって決して小さくはありませんが、それまでやってきた建外SOHOは70万平米でしたから、NYからでもコントロールできないスケール感ではなかったんです。
また、僕としては、せっかくアメリカに行くために準備もしてきたのにという気持ちもありました。当時の僕は「現代建築の主流は欧米」という考えだったので、中国でキャリアをスタートすることには不安がありました。こんなに中国べったりになってしまって建築設計のメインストリームから離れていくんじゃないかという怖さがあったんです。
だけど、無名の僕が公共建築を建てるチャンスがいきなり巡ってきたという幸運をみすみす手放すのはあまりにもったいないという気持ちもあって、結局そちらが勝ったということです。
結局、NYに行っている間も2週間ごとに北京に通っていました。
BB:NYと往復、ですか?
迫:ええ。秋からNYに行くことになっていたので、その前に北京で事務所を設立し、スタッフを3人確保してから出発しました。ひとりは、日本の大学の建築学科を卒業したばかりの女子でした。彼女は現在も事務所の主力として働いています。
NYと北京を2週間ごとに往復する生活を1年続けました。時差がちょうど12時間なので、NYの夜中に北京に電話やビデオチャットで指示をしていました。インターネットが普及したおかげで、やることができたんです。
ファン氏は、2000年に入って中国で世界的な建築家たちによる建築ラッシュが起きる前から、数多くの海外の著名な現代建築家を中国に紹介してきている。CCTVの設計をしたオランダのレム=コールハースも、中国で作品紹介と批評をさきがけて手がけたのはファン氏だ。批評家としてのファン氏は極めて率直。いいと思ったら「すごくいい!」と言い、ピンとこないと反応しない人だという。
迫:ファンさんは全くウソがつけない人です。でもその建築や芸術への敬愛はとても純粋なんです。だから好き嫌いやいいもの悪いものへの見方がとてもはっきりして、とにかく本音で批評してくれます。
作品についてはもちろんですが、中国での仕事の仕方も「迫はわかってない」と辛辣に指摘されたこともあります。たとえば、施主へのプレゼンでは最初にインパクトを打ち出すことが重要だというのを教えてくれたのはファンさんです。「日本の奥ゆかしさの美学を持ち込んでも中国では理解されない」と教えられました。
中国でのメディア露出を力強くサポートしてくれたのもファンさんです。僕らはコネも予算もなく、受注のための営業スタッフなどいません。だいたい、アトリエ系の建築事務所は営業という概念があまりないのです。でも中国で、仕事をとっていかなくてはならないという時、メディアは僕がどういう建築家で何を目指しているのかを伝える貴重なツールです。建築やインテリア、アートの雑誌での取材が増えたのもファンさんの協力が大きいんです。
四川のボランティア(BB注:四川省幼稚園寄贈プロジェクト)を始めようと思った時も、最初に僕はファンさんに相談しました。ファンさんは、四川の有名な建築家に連絡して、すぐに一緒に会いに行ってくれました。
そう、2005年にはファンさんと二人で約10日間かけてアメリカを旅しました。NYからLAまでアメリカ大陸を西へ横断しながら世界的な建築を見て回る旅です。
BB:中国で出会った中国人と一緒にアメリカの建築を見る旅をするという時間の共有もおもしろいですね。

(写真)ファンさんを助手席に乗せて、レンタカーで砂漠の一本道を突っ走った
迫:テキサス州マーファというところにミニマルアートの聖地と呼ばれている建築やデザインに携わる人にとって巡礼の地のような場所があるんです。最寄りの空港から300キロ離れているそこまで、テキサスの荒野の1本道をレンタカーで時速100マイルでぶっ飛ばしました。壮大な大地と空に抱かれ、静かに、しかし力強く存在するドナルド・ジャッドの作品を目の前に、ファンさんと僕はただ言葉を失って立ち尽くすばかりでした。クリエイターとして一生心に刻まれる瞬間を、ファンさんと二人で共有したんです。
建築の世界のスケール感や目指すべき高い地点はどこにあるのかといった認識を共有できるファンさんのような人が中国にいるということも、僕が中国で建築をやり続けることを後押ししてくれているのかもしれません。(本文中敬称略)
3人め:ソンチー(孫池) 書店「光合作用」店主
「子どものような存在の店の再生に、デザインの力を信じる」
2004年に北京に事務所を開いてから、迫の事務所では300平米規模のスマートシティからブティックのインテリアデザインまで、70以上のプロジェクトをつくってきた。そのうち、インテリアデザインは37。2004年から7年連続でJCDデザインアワードに入賞するなど、実はインテリアデザインの評価も高い。
建築とインテリアデザインという対照的なスケールのふたつのクリエイティブ。迫のインテリアデザインは、多彩な色や素材とともに雄弁に語りかけてくる。子どものための虹色の書店、白色の網の目を張り巡らした有機的なブティックなど、時にユーモラスな、時にミステリアスな空間。見る人に、きっと迫は楽しんでアイデアを練っているのだろうと思わせる。
今回は、インテリアデザインを迫に発注した中国人の施主との出会いを語る。
BB:最終回はインテリアデザインを手がけた時の施主のお話ですね。
迫:ソンチーは「光合作用」という書店のオーナーです。この書店は彼女が30歳くらいの時にスタートし、現在は北京にも10店舗近く展開していますが、アート関連や小説など、「光合作用」独自の視点で選ばれた本がデザインされた空間に並ぶ、いわば本のセレクトショップのような、一般の書店とは違うスタンスの展開をしてきた書店です。
その「光合作用」の本店のリニューアル(のほうが一般的では?)をすると決めた時、彼女は北京の僕の事務所に訪ねてきたんです。2010年の夏です。
本好きのための空間として既に特長のある店づくりを展開してきた「光合作用」が本店をさらにリニュアルすると決め、僕を指名したいというので、彼女の僕のデザインへの期待値の高さは話しぶりからもすぐに伝わってきました。
ソンチーはおそらく40代半ばだと思いますが、いかにも文学少女がそのまま大人になったような雰囲気の女性です。彼女は、これまで一軒一軒の店を自分の分身のような気持ちで大事に育ててきたと切々と話し始めました。中国の都市部にはデパートのような大書店がいくつもありますが、彼女がオーナーとして10数年経営してきた「光合作用」では、本のセレクト、インテリアデザインなどを自分たちで工夫を重ねながらやってきた、その目的は、素晴らしい書籍と心地よい空間を読者という本好きの人たちに提供することだったと彼女は言いました。中国語では本を読むことを「閲読」と言いますが、彼女は「悦読」という言葉を使う、それほど本を読むことの喜びと素晴らしさを書店を通して伝えたいという思いに溢れた人です。
僕は映画「You’ve got mail」を思い出しました。ニューヨークの大手書店の経営者と街の小さな本屋さんの経営者がお互い反目し合っているにも関わらず、メール上のやり取りで書店づくりにかける思いにおいて意気投合するという話ですが、彼女の書店は街の本屋さんなんです。
「光合作用」は、北京市内でも清華大学の近くや高級百貨店、ショッピングモールなど、15店近くを展開する。ゆったりとした空間には本が空間の余白を生かして配置され、本そのものの美しさも楽しむことができるような店づくりが印象的な書店である。中国では、大型書店が経営難で閉店したという話を聞く一方、「光合作用」のような個性的な書店が支持されるという現象が起きている。
BB:中国で本のセレクトショップを10数年前から展開してきたこと自体、驚きです。
迫:これまでは店のインテリアなども自分たちがやってきたけれど、ここでもっと高いレベルに持っていきたいという説明のあと、彼女はこう言ったんです。「自分の育ててきた子どもを託す気持ちでデザイナーを探した。そしてあなたに頼みたい」
BB:設計者冥利に尽きる言葉ですね。
迫:そういう施主のために仕事をする時、僕らのモチベーションはすごく高くなります。ディベロッパーの建築とのスタンスは、つくったものが売れたら終わりですが、書店オーナーの場合、空間ができあがった時が長いつき合いの始まりなんですね。僕に託して新しく生まれ変わった空間が、そこにすてきな本が常に入れ替わりながら本好きに愛される豊かな空間に育っていき、結果として書店のブランドも売上げも上がる、そのゴールまでの過程まで含めて、僕はデザイナーとして責任を持つことになるわけです。
設計して終わりではなく、設計した空間を一緒に育てていく感覚を持つことができることに喜びを感じました。
BB:デザインへの具体的な注文はあったんでしょうか。
迫:あったといえばひとつだけ、「一切を新しく。これまでの雰囲気はひきずらなくていい」。それと「社名は変えない」。というのも、空間デザインだけでなく、書店のロゴサイン、書棚のサイン、コーヒーコーナーのカップ、紙袋まで一切のコミュニケーションツールのデザインを依頼されたんです。
僕は、彼女がこれだけは変えないと言った「光合作用」をそのままデザインに翻訳すればいいと考えました。空間デザインもそうですが、光合成に必要な水と光を、「地球」(アポロン)と「太陽」(ポセイドン)の化身というふうに捉え、「APODON」という新たなキャラクターもつくりました。

(写真)「光合作用」という名前をデザインで表現することを考えた
その後、プレゼンと打ち合わせが何度も繰り返された。そして2ヶ月半の施工期間、担当スタッフがアモイの現場に常駐して作業を続けた。
BB:完成した「アポドン」への施主の反応はどうだったんでしょう。

(写真)初日を祝うゲストが詰めかけたオープン当日、笑顔のふたり
迫:いくら僕に任せたといっても彼女も相当気持ちは揺れたはずです。
そのうえ、中国の建築の現場では珍しいことではありませんが、コストはオーバーするし、納期は遅れるし、しかも、工事の途中は仕上がりの予想がつきませんので、どんどん不安になるわけです。何度も送られてくる仕上がりを心配するメールから、彼女の胸の内は手に取るようにわかりました。ようやくできあがったのはオープンの12月5日の前日でした。
明け方の3時、彼女からショートメールが届きました。そこにはこう書かれていました。
「世界中の書店の未来は明日終わりを告げます。わたしがつくりたかったこの空間が世の中に生まれたことによって、すべての書店を圧倒する世界にただひとつの空間が誕生します」
僕はオープン当日にそのリニュアルした書店で「中国のブランド空間」というテーマで講演をすることになっていました。アモイの空港に出迎えにきていた車に乗り込んで、オープン直前の「光合作用」に到着すると店の前には孫が待っていました。車から降りた僕の顔を見るとそれだけで感極まった孫と僕は何も言わずにハグしました。お互いが自然とハグするような気持ちになることはあまりないことです。
BB:デザイナーとしての迫さんにとって、このプロジェクトはどういう意味を持ったんでしょう。
自分たちが育ててきたブランドを高いレベルに持っていきたいというこの施主との出会いによってデザインの使命感を改めて認識しました。
「光合作用」の施主と僕との間にデザインを媒介として深く結びつき合う関係が成立したように、中国にはここでやっているからこその空間をデザインするということの大事さや喜びがあります。施主のデザインへの期待やリスペクト、祈りのような思いを引き受けて一緒に空間をつくっていくことの達成感が、中国の現場にはあるんです。
そういう施主とデザイナーの間に生まれる志を共にするような関係性が中国のクリエイティブの現場にあることが、日本では伝わっていないことは少し残念です。
バブル景気の勢いに乗って経済性を生み出すための建築が猛スピードで製造されているという中国市場のイメージとは異なる、中国ならではのものづくりの現場にいて、そこで中国人と互いに尊敬し、信頼し、より優れたデザインを生み出す行為に関わっていることは、僕の誇りです。(本文中敬称略)

Vol.2 美容サロン経営(北京和僑会理事)北京朝倉時尚形象設計有限会社C.O.O・ディレクター 朝倉禅(34)
1人め:ウホイウェン 吴恵文(ファッション誌『昕微』(ViVi) 中国版編集長)
「カワイイ」を追求する女性編集長。
志をともに、ファッション誌のパイオニアと階段を上がってきた

(写真)朝倉 禅
<プロフィール>
あさくら・ぜん。1977年香川県生まれ。高校から渡英し、有名デザイナーを多数輩出している伝統校・セントマーティンズ大学で2年間学び帰国。地元・高松市で父親が経営するアサクラ美容室に4年間勤めた後、2004 年、北京にアサクラ・インターナショナル・北京オフィスを設立し、進出。中国最優秀ヘアスタイリスト受賞。「ニューズウィーク」誌で「世界が尊敬する日本人100人」に選ばれる。ファッション、雑誌、ショープロデュース、スクールなど美容の枠を超えた幅広い分野で活躍する
イギリス留学から地元・香川県高松市に戻った1997年、朝倉は20歳。父親が経営するワン・デイ・スパ形式の総合美容サロンで働きながら、将来のめざすべき方向を模索していた。「今後、日本で勝負すべきか。それとも海外で勝負すべきか」。中国で美容ビジネスに踏み出すことを決心する。
2004年、朝倉は中国の首都・北京で約30人のスタッフとともに日本人美容師による美容サロンASAKURAをオープンした。
中国人の所得上昇や前年比20〜30%の経済成長率を背景に美容市場が猛スピードで発展していく中、ASAKURAは技術、提案力、そして巧みなメディア戦術によって存在感を増していく。
7年後の今、美容だけでなくファッション、ライフスタイルなどトータルでおしゃれを楽しみ始めた中国女性達に呼応するように、朝倉もビジネスの多角化に向けて舵を切ったところだ。
朝倉は、この7年、いったいどのように中国人顧客の心をつかんできたのか。
BillionBeats(以下BB):日本で事業拡大を図るのではなく、海外で美容ビジネスに挑戦しようと思ったのはどうしてだったんでしょう?
朝倉:父は2代目として、美容室にレストランやスパなどを併設したワン・ディ・スパ形態の総合サロンをある程度形づくっていました。次世代である僕が事業を引き継いで発展させていかなければならないと考えた時、香川という地域でのブランド力はあったとして、香川で店舗を増やすのか、他都市に進出するか、どちらにせよ、日本で結果が出せるのか、疑問でした。東京や大阪に出店したとしても恐らく2、3店どまり。もっとやりがいのある場所、美容ビジネスの広がりを出せる場所は一体どこだろうと考えた結果、海外で勝負しようという答えに行き着きました。そしてリサーチのためにアジアの都市を見て回り、北京を選んだんです。
BB:なぜ、アジア地域、そして中国だったのですか?
朝倉:海外に進出するならヨーロッパではないと思っていました。イギリスはじめヨーロッパは美容の概念がある程度完成している成熟市場ですので、よほどニッチな部分を攻めていかないと入り込むのは難しい。僕は、やりたいことが伸び伸びとできる場所で思いっきりチャレンジしたいと考えました。ヘアスタイリングによる表現の本流を追求できて、なおかつ日本のスタイルを最大限に生かせる場所、そしてそれがビジネスとして成立する場所はと考えると、やはりアジア地域です。香港やタイなども視察しましたが、中国に将来の可能性、美容業界の発展性を感じました。例えば、日本の女性ファッション雑誌の中国版では大々的に日本のスタイルが紹介されているのを見て中国女性のヘアスタイルやファッションが明らかに変わろうとしているのを実感し、自分がやりたいことを中国できちんと形づくっていけば、この国の美容業界で自分たちのポジションを築くことができると確信したんです。
BB:中国の都市の中でもなぜ上海ではなく北京を選んだのでしょう?
朝倉:中国で美容ビジネスを立ち上げるからには、中国に来た日本企業というスタンスではなく中国の企業として中国全土でASAKURAブランドを確立し、根づかせていきたいと思いました。
どの都市に進出するかを考えた時、まずはじめに名前が上がるのはやはり上海。経済都市・上海は、ある意味すでに完成されています。上海で出店ができたとしても、その後中国のほかの都市に進出する場合、上海で展開したビジネススタイルが通用するかは別だと思いました。
上海は人の流れが重要です。人の流れを読んで建物を造り、建物の力によって人が集まるというようにして人の流れをつくっていきます。また、外資企業が多いため、中国の都市の中では最も外国人客の獲得が容易なエリアでしょう。でも、上海で成功しても「それは上海だからでしょ」で終わってしまいます。上海という都市の特殊性の上に成り立つ成功でしかない可能性があります。その意味で、上海は僕らの選択肢ではないと判断しました。
また、ASAKURAブランドの価値を高め、全土に広げていくためのプロモーション活動を行う上でも、多くのメディアが集まる北京は魅力的でした。カラーやパーマをする人々はまだまだ少なかった北京の市場に成長性も感じました。ASAKURAの特長である日本のスタイルを打ち出していくならやはり北京、ここで成功すれば、中国の他都市でも認めてもらえるという読みがありました。

(写真)開店したばかりのASAKURA。三里屯から少し奥に入ったところの2階建てビル。
北京・三里屯エリアにオープンするにあたって、朝倉は自分のスタンスをプロデューサーと定めた。店舗の運営、技術管理、PRなど、必要な場所にそれぞれ適した人材を配置し、陣頭指揮をとる。中でもメディア戦略には力を入れた。
2004年7月、オープンセレモニーとして約20の中国メディアから約200人の関係者を招待して大々的なショーを開催した。そのショーで、ASAKURAの対中国の姿勢をアピールし、本気で中国市場に入っていこうとする日系美容室として認知される入り口をつくった。
BB:華やかなデビューを飾ったわけですが、プロデュースはどなたですか?
朝倉:僕自身です。
僕が留学したロンドンの美大からは、アレキサンダー・マックイーンをはじめ世界的なデザイナーやアーティストがたくさん生まれています。僕もアートへの興味から、漠然とアーティストを目指して入学したんですが、クリエイティブの次元が違いすぎるクラスメート達に圧倒されてしまったんです。到底普通じゃない、天才という言葉が当てはまる人が多すぎて、勝負してもムリだなと思わされました。ここでの2年でアーティストとしては自分が凡人だということをつくづく自覚しました。
では、自分をどのようにプロデュースしていくか、どうやって目立っていくか、ちゃんと認めてもらえるかを考えた時、自分ひとりでやっても勝てないなら、自分ができない部分はそれができる人たちと組んで「集合体」で勝負していけばいいということに気づいたんです。つまり、僕はプロデューサーとして勝負しようと思った。
スタッフ達にそれぞれの持ち場で能力を発揮してもらってプロデューサーとしてASAKURAという複数の人間の集合体による作品をつくろうと考えたんです。

(写真)北京に出店して間もない2004年7月、メディア20社を招いてショーを開催。 ここで吴惠文と出会った
ショーの招待客の中に、昕微ViVi 中国版編集長のウ・ホイウェンがいた。
当時は中国のファッション誌自体が少なく、ViVi中国版の内容も日本で流行っているファッションやヘア、メイクの紹介がメイン。中国で制作したページと日本で制作したページとではつくり込み方やスタイリングが異なるため、どこからが中国で制作されたページか一目ですぐ分かるといった感じだった。
日本のスタイルを中国で広めたい朝倉と、読者に喜んでもらえるオシャレでカワイイ雑誌をつくりたいウは、その場で意気投合した。
朝倉:彼女は30を過ぎたくらいの若い編集長でした。中国の読者に日本のスタイルを伝えたいという思いを持っていた彼女と僕とで、店がオープンした1週間後にはもう一緒に撮影をしていました(笑)。ViVI中国版の誌上で、ヘアスタイリングを提案するページを僕ら主導でつくらせてもらうことになったんです。僕をはじめ、ASAKURAのスタイリストが誌面に自分の顔と名前を出して、ヘアスタイリングについて説明しました。
中国ではヘアスタイリストは裏方でしたが、僕らは積極的に表へ出ていこうとしました。というのも、中国には美容学校も美容師の国家資格もなく、社会的な位置づけが低い。そのため、最初僕らは大卒の中国人を何人か採用したのですが、本人は日本の最先端のファッションに関わる仕事に意欲的なのに、親に「なんで大学まで出て美容室で働くのか」と猛反対されて辞めざるを得ないというケースがありました。
その時、美容師の社会的位置を上げていくような取り組みをしなくてはと感じたんです。僕らが表に出ていって発信し、美容師の仕事の魅力が伝わっていくようにすることも必要だと思いました。
ViVi中国版に参加し始めた7年前、僕達には力不足な面もあったかもしれませんが、彼女は僕達を信頼し、僕らからの提案や意見を積極的に取り入れてくれました。
4年前には中国の美容室として初めてヘアカタログを出版することができました。現在もViVi中国版には関わり、同誌モデルの審査員も務めています。
BB:なぜ、ASAKURAのスタイルが受け入れられたと思いますか?
朝倉:それまでは日本のスタイルを中国人に合う髪型におとし込める人がいなかったんだと思います。僕達がつくるスタイルは、日本人から見るとラインをちょっと出しすぎと感じるかもしれませんが、同じカットでも、ややラインがはっきり出るようにした方が中国人は日本のスタイルを感じます。ラインを出し過ぎても日本流のままでもダメ、ニュアンスの足し引きの加減が大事なんです。
そして僕らはヘアに限定せずディレクションやスタイルにも積極的に関わってきました。試行錯誤を繰り返しながら中国人が思う「カワイイ」をつくり続け、今はASAKURA流スタイルと評価していただいています。
BB:ASAKURA流スタイルをつくるのに、ViVi中国版を通したウ編集長との関わりはどう影響していますか?
編集長とは、単なる雑誌づくりというより中国での日本のスタイルを一緒に創造してきたと自負しています。編集者と美容師という関係を超えて、お互いがビジョンに基づいてどう展開していくか親身に相談し合う仲間です。ViVi中国版は発行部数が40万部だったのが、今では120万部。一緒に高め合ってきて、彼女の雑誌はここまで成長し、僕らはASAKURA流スタイルを確立することができたんです。
オープン当初に志をともにする仲間と出会えたこと、目標に向かって一緒に仕事ができたことは、本当にありがたい。彼女との出会いは、現在のASAKURAにとって何ものにも代え難い契機となったと言えます。(文中敬称略)
2人め:ヤン クン(楊坤) C-POP歌手
ショー出演依頼を快諾した実力派歌手。
C-POP界を生き抜いてきた彼からメディアでの“自分”の見せ方を学んだ
朝倉は中国進出当初から積極的にメディア展開に取り組んできた。ASAKURAの顔として表舞台に出続けることは、中国でより多くの人々にASAKURAを知ってもらう最も効果的な戦術だった。
オープン時にメディアを招待したショーが成功し、朝倉は、今度は中国美容業界での認知度向上に向け、新たな試みを実行に移す―。
朝倉:ViVi中国版をはじめファッション誌に露出していったことで、中国のファッション業界や芸能関係者が多く来店するようになりました。でも、彼らはASAKURAを日本人スタイリストがいる日系サロンとしか捉えておらず、中国企業としてASAKURAのブランド価値が上がったわけではありません。一方で、将来この国で美容ビジネスを広げていくうえで中国での美容師の地位向上と技術向上は欠かせないと考えていたので、僕達が高い技術を持っていることを中国の美容業界の人達に知ってもらい、ASAKURAの認知度を高める必要があると考えました。
自分達で積極的にショーなどのイベントを展開していく中、オープン1年後の2005年8月、美容業界の大きなイベントに参加することが決まりました。国際展示場で3日間にわたり行われるそのイベントには中国国内から美容関係者が集まり、連日さまざまなショーが行われるといいます。僕らはそこでASAKURA独自のショーを行うことにしました。
そのショーで、僕はサプライズゲストを迎える演出をしたいと思いました。そしてダメもとで提案したところ、快諾してくれたのが、中国で有名なC-POP歌手のヤンクンさんなんです。
当日、会場でショーがクライマックスを迎えた時、突然ヤンさんが舞台に現れると会場は興奮した観客でパニック状態になりました。彼は僕と握手したり肩を組んだりして、自分がどれだけASAKURAを信頼しているかを会場の人々にアピールしてくれました。まさか有名歌手のヤンクンが来るとは思っていなかった観客は、度胆を抜かれていました。
「ASAKURAの技術は中国の人にも絶対通用するし、中国でナンバー1の美容室になる」
そうヤンさんはその大観衆に向かって高らかに宣言してくれました。
美容業界でASAKURAを知ってもらうきっかけになり、また、そのショーの後にはますます多くの人がきてくれるようになったんです。

(写真)北京の国際展示場で開かれた美容業界イベント。緑色のシャツの男性が杨坤
BB:ヤンさんとはどのように出会ったんですか。
朝倉:芸能関係のお客様からの紹介で、来店してくださったのがきっかけです。でも僕は彼が有名な歌手だと知りませんでした。中国語が話せなかったので、通訳を介したりジェスチャーを使って会話をしながら意思疎通を図っていました。それでもこんなに親密になれたのはきっと波長があったんだと思います。
何度も来店されるうちに、お互いの仕事やプライベートなどいろいろな話をするようになりました。僕は、中国でこれから新しいヘアをプロデュースしていきたいこと、一般の方に発信するだけではなく多くの中国人美容師にも知ってほしいと願っていること、自分達の技術を広めて中国の美容業界自体をよりよくしていきたいと考えていることなどを伝えていました。
オープン以来、いろいろな場所でショーを開催していましたが、そのイベントは中国の美容業界にアピールする絶好のチャンスでした。せっかく参加するなら、何かサプライズ的なものができればとヤンさんにゲスト参加をお願いしたところ、二つ返事で、それもノーギャラで引き受けてくださったんです。きっと、僕の思いに共鳴していただいたのだと思います。
ヤンは中国大陸を代表する歌手である自分がショーに出演することの影響と効果をわかっていた。朝倉は、ショーでのヤンクンの“見せ方”を通し、少しでも多くの人に認知してもらうためのプレゼン方法、トコトン表に出て名前を覚えてもらうことの意味を学んだ。
BB: ヤンさんが出演したことはショーにどんな影響を与えたのでしょう?
朝倉:ヤンさんには本当に感謝しています。僕らは自分達の技術に自信を持っていますが、それだけではきっとショーは満足いく内容にはならなかったと思います。ヤンさんは、メディア上での自分の見せ方を知っていた。それをショーで目の当たりして、自分が中国でどのようにASAKURAを見せていくか、ヒントを得たような気がしました。また、その後の来店客の増え方からも、中国では人とのつながりや口コミでどんどん情報や関係が広がっていくことを実感したんです。芸能関係だけでなく、他の業界の方々、陸上選手の劉翔さんも世界大会で世界新記録を出した前日に来店されてから、その後も験担ぎにわざわざ来てくださるようになりました。
BB:ヤンさんを引きつけた朝倉さんの魅力は何だと思いますか。
朝倉:それは僕達が持っている提案方法、技術の高さにあったと思います。僕自身、最初ヤンさんが芸能人だと知らなかったし、中国の芸能人に対して先入観がなかったので、サロンにいらした時のヤンさんの雰囲気によって、似合うと思うスタイルを率直に提案してきました、当時、中国の美容師はお客様に何も提案をせず勝手に切って「はい、できあがり」という感じだったので、ファッションとも絡めてヘアスタイルを提案する僕らのやり方は新鮮に映ったのだと思います。中国の美容師にはない技術を用いたのも「そんな意外な提案をしてくれるんだ」「そんなことができるんだ」とヤンさんに感じていただけたのかなと思っています。

(写真)地方都市でのスクール開講。
高い技術を求めて集まる美容師達は驚くほど熱心
ASAKURAは現在、2012年春の上海出店に加え、内陸部の都市でも出店計画が進んでいる。
朝倉:北京や上海への出店はあくまでも通過点です。この2都市のサロンはフラッグショップ、つまりブランドの発信基地と位置づけていて、そこから第3、第4の都市へ展開していきたいと考えています。もうひとつ力を入れていこうとしているのがスクール事業です。
ブランド価値を高めるためには、店舗を拡大するだけでは意味がありません。ASAKURAのスクールで技術を学んだ美容師が、将来そのままASAKURAの美容室で働けるようにしていきたいです。中国には美容師の国家資格制度がないので、僕らがスクールによって教育の分野でアクションを起こし、ASAKURAの美容学校で学んで資格を取ることが技術の証明となるような段階までもっていければと思っています。
現状では、中国人美容師には時間をかけて技術を勉強するという概念が育っていません。これだけ美容全体の技術や感覚が向上してきている中、今後はそれでは通用しないでしょう。中国の美容師やタマゴたちにASAKURAの技術を学んでもらい、その技術を中国のスタンダードとして普及させるのが夢です。美容スクール事業は、担当講師が中国国内を行脚して、すでに各地で講座を実施しています。成都でも7月からスクール事業がスタートしました。北京では、月数回、約30人を対象に実施しています。受講費は3日間で約4,5000元(日本円:50000〜62500円)と決して安くありませんが、意欲と実力のある美容師が集まってきます。実践で使える技術を中心に、それぞれの仕事場で実際に使ってもらえるような技術を指導しています。
ASAKURAが業界で認められる存在になるのを後押ししてくれたヤンさんにはとても感謝しています。そして、中国でブランドを高めていくことと中国の美容技術の向上は、僕にとってどちらも同じ意味を持っています。(文中敬称略)
3人め:中国大企業の副総裁
「中国の父」と慕う某大企業の副総裁。
中国ビジネスを知り尽くす彼からビジネス成功術の指南を受けて
ASAKURAの中国国内での知名度は格段に伸びた。順風満帆に見えるが、中国ビジネスには予期せぬトラブルがつきものだ。契約不履行に営業妨害など、外国人にとって中国での事業展開は一筋縄ではいかない。理不尽な出来事は日常茶飯事だ。
「中国ビジネスで最も大事なのは、人と人のつながり」という朝倉。どのように中国人とつき合い、つながりをつくっていくか。「人とのつながり」が中国ビジネスには欠かせない要素だと、朝倉に教えた人物との出会いは―-。
朝倉:僕達の業界は、普段営業していくだけでもトラブルが耐えません。外国人というだけで、営業妨害を受けたりするのも珍しくありません。例えば、中国国内のある地方都市でショッピングモールに店舗を出店しようとして、契約面でこちらが正しくても理不尽な理由で急に契約できなくなったことがあります。別のケースでは、契約した時より費用を上乗せされたり、いろいろな理由を出してきて契約不履行にされたこともありました。そんな状況では、ASAKURAという日系の会社の日本人の私が表に立って話し合いをしても埒があかない。相手にとって、私は外国人で知り合いではない、つき合いがない人間だからです。
そんな時、相手の会社につながりを持つ中国人に間に入ってもらい、こちらが正しいということをきちんと説明してもらうと、あっという間に解決することを体験しました。それを教えてくれたのは、ある中国大企業の副総裁です。
BB:その副総裁とはどうやって出会ったんでしょう?
朝倉:以前、ある企業からASAKURAブランドのヘアケア用品を作りたいという提案をいただき、その企業の紹介で副総裁とお会いしました。結局、ヘアケア用品の案は実現しなかったのですが、日本から両親が来た時に副総裁のご家族と一緒にみんなで食事をしたり、逆に副総裁が日本に行かれた時は僕達がアテンドしたりと、家族ぐるみで仲よくさせていただくようになりました。
香川の父と同年輩の50代半ばの副総経理は、ビジネスで何かあるたびに相談してはアドバイスをもらう「中国の父」のような存在です。
自分では対処しきれない事案が発生した時など、トラブルの解決につながる人物を紹介してもらったり、僕の代わりに間に入って相手側と対応・交渉してもらったりと、要所要所で助けていただいています。みなさん不思議に思われるかもしれませんが、見返りを求められたことは一度もありません。
中国人的つき合いというのでしょうか、とても情が深く、一度築いた信頼関係によって一生つながっていられる関係のように感じています。

(写真)2009年に北京にオープンしたフラッグショップ。工人体育館に面した一面ガラス張りの窓から燦々と日が差し込む。
中国のブランドになるべく努力していても、外国人であるために越えられない壁が、朝倉の前に何度も立ちふさがる。そんな朝倉を支えているのが某大企業の副総裁だというのである。多くの日本人経営者が中国人との人間関係・信頼関係の構築が難しいと感じている中で、朝倉はなぜ、このように中国人の協力者を得ることができたのか。
朝倉:イギリス留学時代にいろんな国から集まってきたクラスメートとつき合った経験も影響しているんだと思いますが、私は国籍より個人と個人の関係が重要だと思っています。中国に来たばかりの時にだまされたのは日本人コンサルタントでしたし、日本人でもいい人もいれば悪い人もいます(笑)。今でも中国人とのトラブルは絶えませんが、それよりも助けてもらっていることの方がずっと多いですから。
人と人とのつき合いは、基本的にフィーリングが合うか合わないかではないでしょうか。有名だからとか、権力があるからか、どこの国の人だからとか、そういうのは全く関係ありません。
BB:中国では人と人のつながりが重要なのは、なぜだと思いますか?
朝倉:やはり、中国は家族をとても大事にしますし、人と人のつながりによって情報が往来し世界が広がっていくという文化的背景が関係していると思います。日本人には理解できない部分も多々あると思いますが、実際、僕もこれまで友人達のつながりによって何度も救われてきました。誰々の知り合いだから、友人だから、家族だからというのをきっかけに、ビジネスが展開していく場合もあるので、今後も一つ一つの出会いを大切にしていきたいと思っています。今後、北京以外の都市にビジネスで進出する時も、応援してくれる人がいる場所に出ていきたいですね。

(写真)クリスタルのシャンデリアが出迎える受付。
現在、飽和状態となった日本の美容業界からは、いくつかの日系美容サロンが海外に活路を見出すべく、アジア地区、特に中国へ進出しているが、朝倉は一部の企業の手法に疑問を投げかける。
朝倉:近頃は日本の有名店の上海などへの進出の動きがあります。内情を見てみると、ブランド名は持ってくるものの実動部隊は現地で調達しているというパターンが多いようですね。中国にベースを持って現場で戦う僕らとは違う彼らのやり方で、中国で成功するのかどうか、僕も非常に興味を持って見ています。
中国の人達は、ファッションに限らず、日本人が思うほどには東京や日本ブランドへの憧れはないようです。でももちろん日本製の素晴らしいものはたくさんあります。重要なことは、「なぜ」「どのように」いいのか、見せ方を考えて向き合っていくことです。でないと、せっかくいいものを持っているのによさが伝わらないのではないでしょうか。例えば情報を発信する際、中国というと、数の多さに踊らされてしまいがちですが、よりその部分を知っているコアな100人、興味を持っている人100人にターゲットを絞り、詳しい情報を発信していくといった方がより効果的な場合がある。見せ方をもっと工夫していくべきだと思います。
BB:ASAKURAが目指す未来像を、ぜひ聞かせてください。
朝倉:今、僕達の店は日本人スタイリストが中心ですが、10年後、20年後にまだ日本人美容師の需要があるかどうかわかりません。今後は、ASAKURAの技術者は素晴らしいと思ってもらえるよう、見せ方、伝え方を考えていかなくてはなりません。ASAKURAの中国での「本気」を示すために、旗艦店を北京で最も華やかなこの三里屯そばにオープンしました。中国の人達に「こんなの今までみたことない」と思ってもらえるような、1100平米規模でモダンかつラグジュアリーな雰囲気のサロンにしたんです。最終的には中国の方々に「美容・ファッションといえばASAKURAだよね」と思ってもらえるような、身近に感じるあこがれのブランド、中国全土どこに行っても店舗がある中国の美容ブランドになっていきたいです。
BB:香川のお父さまと同じ道に進み、北京というアウェイに飛び出し「中国の父」にも出会った朝倉さんの中国での仕事ぶりを、お父さまはどう見ていらっしゃるのでしょう?
朝倉:父親は技術にすぐれた職人肌の人で、僕とは経営に対する考え方がぜんぜん違います。彼はどういう作品でブランド力を高めていくかと考えるタイプです。逆に僕はプロデュースが得意なので、父は超えるべき対象というより、今も協力してもらっている大事な応援団です。とはいえ、いつか父を超えたと思える日が来るといいですね。(文中敬称略)
Vol.3 テニススクール経営(北京和僑会会員)レインボーテニスガーデン代表 藤本龍一郎氏(27)
1人め: イエンダミン 厳大●(左:石、右:名)(河北テニスアカデミー経営兼校長)
ナショナルチームのコーチと、北京で再会。
今度は経営の指導を受ける

(写真)藤本 龍一郎
<プロフィール>
ふじもと・りゅういちろう。1984年香川県出身。幼少時代を北京、小学2年から5年まで上海で過ごす。中学でテニスを始め、3年時にシングルスメンバーとして全国中学生大会ベスト8入賞。高1の夏、再び北京へ。2年生の時、よりよいテニス環境を求めてカリフォルニアのワイルテニスアカデミーに留学。2004年筑波大学体育専門学群入学、スポーツ科学、体育経営学を学ぶ。大学卒業と同時に、北京でレインボーテニスガーデンを開校。
中国のテニス人口は現在500万〜600万人。中国におけるバドミントンや卓球人口が約2億人とすれば、認知度はまだ低い。しかし、目覚ましい経済発展とともに富裕層が拡大、さらには中国人のプロテニスプレーヤー李那が全仏オープンで優勝したことも追い風となり、将来は1000万〜1500万人、さらにはもっと増えるといわれている。
藤本が北京にレインボーテニスガーデンを設立したのは、日本の大学を卒業した年の2009年4月、24歳の春だ。「北京で本格的なテニスアカデミーをつくりたい」という夢を道連れに単身北京に乗り込んだ。
藤本:銀行マンの父の転勤で、小さい時から北京、上海、日本の間を行ったり来たりしていました。1歳から4歳まで北京に住んでいて、天安門事件で戦車を見たのをうっすらと覚えています。
東京の中学の1年の時、部活でテニスを始めてのめり込みました。ちょうど『テニスの王子さま』が流行り始めていた頃です。3年の時、全国大会の団体戦で自分の試合でチームの勝敗が決まるという大事な局面で負けてしまい、チームはベスト8で終わりました。相当ショックで、部活を引退した後はテニスをやめました。
高1の夏、父が再び赴任していた北京に合流し、アメリカ系のインタースクールに通いながらテニスを再開したんです。中国人のコーチにプライベートレッスンを受けていましたが、だんだんもの足りなく感じだし、長期休みに河北省にある民間のテニスアカデミーの合宿に1ヶ月の間参加することにしました。そのテニスアカデミーの校長が厳大●(左:石、右:名)さんです。当時40代前半の厳さんは、河北省ナショナルチームのコーチ経験があり、中国の代表レベルの実力者であるだけでなく、指導者としても一流でした。そして10年前、自分でテニスアカデミーを設立し経営を始め、僕はその設立まもないアカデミーに通ったというわけです。
25人の同年代の中国人生徒達との共同生活は、朝6時から朝練、午前と午後の練習が終わると、夕方は10キロのマラソン、夜は世界で通用するプレーヤーに欠かせない英語の授業というふうに、テニス漬け。自分がどんどんうまくなっていくのが実感できました。
厳さんのアカデミーでは自分でも上達が実感できたのに、休みが終わって高校が始まると時間が制限されて思うようにテニスができなくなりました。合宿生活で得たものがあっという間に失われていくのがもどかしくて、それでテニスの本場であるアメリカに留学することを決めました。その時、北京に指導レベルのしっかりしたテニススクールがあればと強く思ったのが、テニススクールの起業につながっていると思います。

(写真)厳コーチのアカデミーで。真ん中の男性は、
10年前に藤本と一緒にここで合宿した厳コーチの教え子。
今はアカデミーのコーチとして働いている。
BillionBeats(以下BB):アメリカでのテニス生活ではどんなことを考えていたんでしょう。
藤本:アメリカには親元を離れて高い費用をかけて行ったので、本当に自分は正しいことをしているのかというプレッシャーがありました。北京にスクールがあったら、北京で家族と暮らしながらテニスが学べたらいいのにと漠然と思っていました。
2年後に帰国して進学した筑波大ではプロのコーチや学校の先生を目指す友人が多く、僕も「将来はテニスで仕事ができれば」と考え始めました。そして就活の時期になって、北京やアメリカで培った経験を生かしてスクールをやろうという気持ちがいよいよ現実味を帯びてきたという感じです。
大学時代の後半は、ひたすらコーチのアルバイトをして起業資金を貯めました。卒業前の2008年初冬に、いま北京和僑会の会長をされているゴルフレッスンプロの本多さんのブログを見つけて連絡をとったところ、すぐに返事をいただいたので、12月に本多会長を訪ねて北京に行き、本多会長に教えていただきながら、家探しと情報集めをしました。北京でスクールを開くのに、会社設立の方法にしても一体何から始めたらいいかもわからず、上海の日本人学校時代の幼なじみのお兄さんがすでに上海でサッカースクールを始めていたので、7年ぶりに電話をしてアドバイスをもらったりもしました。中国人のパートナーと一緒に会社を設立すれば少ない資本金で始められるというような基本的なことも、この時に教えてもらったんです。
2009年4月、藤本はバイトで貯めた200万円をもとに、北京でテニススクールをスタートした。最初集まったのは20人足らずだったが、ブログなどを使って北京にテニススクールをつくった強い気持ちや指導者としての特長をアピール。次第に口コミや知人の紹介などで評判が広まり、北京在住の日本人の小中学生や主婦を中心に生徒数は順調に増えていく。
2009年10月、藤本は北京で開かれていた世界的テニス大会のひとつ・チャイナオープンに生徒達を連れて行った。会場となった北京市北部の北京テニス場で、藤本を待ち受けていたのはーー。
藤本:「藤本!」と呼ばれて振り向くと、見覚えのある顔がそこにありました。なんと、テニスアカデミーの校長の巌さんでした。僕が高3でアメリカに行って以来ずっと会っていなかったので8年ぶりです。「今、北京でテニスを教えている」と言うと、コーチの方もびっくりしていました。
「今度、遊びに来い」と言ってもらい、生徒達を連れて河北にある厳コーチのアカデミーに行ったのがきっかけで、週末や長期休みを利用して、そのアカデミーに生徒達を連れて行って練習試合などをさせてもらうようになりました。技術向上はもちろんですが、日本人の生徒達にとっては中国人と交流できる貴重な機会にもなっています。
現在、中国には民間のテニスアカデミーは5、6校しかありません。選手育成は国が主体となって取り組んでいます。一方で、指導者の環境を見てみると、テニス指導を職業にしようと考えた場合、国の機関だと収入は安定していますが金額は低い。ある程度の収益を得ながらプロのテニス選手を自ら育成しようと思ったら、自分でアカデミーを経営するのがいちばんいい方法です。それを10年前から実践しているのが巌さんです。アカデミーの中にはお金持ちが出資して経営しているところもあるようですが、厳コーチのアカデミーは独資。現在、このアカデミーには14歳以下の中国代表選手ら何人かのトップレベルの子がいます。国の施設だったら、保護者の負担は0円ですが、アカデミーは年間60000元かかります。欧米では約300万円かかるので、僕らの感覚から言えばこれでも安いと思います。また省のチームに入ると、有名になったらお金を返さなければならないといった契約などもあり、今はアカデミーを選ぶ親が増えています。もちろんアカデミーに子供を入れる親は裕福ですが、投資感覚もあるのではないかと感じています。

(写真)開校して1年目。北京で学校に通う日本人の生徒達。
BB:藤本コーチはなぜ北京でアカデミーを開きたいと思ったんでしょう。
なぜ北京かというと、それは僕が高校時代に過ごした北京で、テニス環境が伴わないことがとても悔しかったから。日本のテニスはプレイの技術も指導技術もレベルが高い。これは僕が中国で展開する時に必ずアドバンテッジになるという自信がありました。それに、指導者になるなら、優れた選手を育てたいというのは当然の夢です。僕も、厳コーチのように将来はテニスアカデミーを運営し、プロを育成したいと本気で思っています。その一歩として、会社として専用コートを持とうと考えて、実は今年の春から動き始めようと、まず相談したのは巌コーチでした。僕は中国ではビジネスを展開するのに人脈が大事だと思ったので、テニス関連での人脈づくりについてアドバイスを求めたいと考えたんです。ところが、厳コーチから届いた返信メールには、僕が期待していたようなことではなく、コート取得のための初期費用、コート1面につき必要な売上げ見込み、その達成に必要な稼働率、といった経営上の必要条件がびっしりと書かれていました。そして極めつけは「今、これらが達成できるのか。達成できないようならコート取得は不可能」という冷静な1文。これを読んでハッと我に返りました。
独自のコートを持ちたいという気持ちだけが先走って焦っていた僕に、思いだけでは経営はなりたたないということを、冷静な現状分析を示すことによって、気づかせてくれたんです。
もし厳コーチからのあのメールを受け取っていなかっったら、僕はもっと強引にコート取得に動いて手痛い失敗を経験していたかもしれません。
厳コーチに、スクール運営を経営的側面から捉えていくことが大切だという当たり前のことを示してもらったおかげで、コート取得をはじめ、スクールやアカデミーといった展開を、もっと長期的な展望で捉えていこうというふうに考え方を切り替えることができました。
BB:高校時代にテニスを教わったコーチから、今は経営者としても指導を受けているというわけですね。
藤本:そうなんです。厳コーチは僕が教え子だからこそ、ここまで踏み込んで丁寧に教えてくれる。本当にありがたいです。指導者として、世界に通用するプレーヤーを育てたいという夢はありますが、教えるというのはそれだけではないと思っています。僕もコーチとして教えている子ども達に対して、テニスだけでなく、テニスを通して何を得るか、何ができるかを体と心でつかまえてほしいし、その手助けはできるようでありたいと思っています。サーブがうまくなっても社会的に通用しない、気持ちの部分で人間的に何かを得て学んでもらいたい。大人になって自分のやりたいこと見つけて、その仕事をしている教え子がいたら、自分もものすごく応援すると思います。厳コーチがいま僕にしてくれていることを、僕もいつか自分の教え子に返していけたらと思うんです。(文中敬称略)
2人め: ジャンジェン 張剣(レインボーテニススクール共同経営者)
日本をよく知る心やさしい共同経営者
中国で日本式テニスコートの普及を目指す
2009年春のスクール開校当初、藤本は北京市北東部のインドアテニスコートの1面を借りた。だが、中心部から遠く地の利がいいとは言えない。小中学生のレッスンには送迎バスを手配し、場所の不便さをカバーしつつ、都市部で探し続け、1年後、都市部にほど近い北京市東部でインドアコート1面の年間契約にこぎ着けた。
藤本:借り上げたインドアコートを一緒に運営しているのが張さんです。
そもそも、コートを借りたのはいいのですが、その時、コーチは僕しかいなかったんです。すぐにコーチを増やすわけにもいかず、困って彼に相談したところ、自分のスクールの会員さんがいるので一緒にやろうという話になりました。
張さんとは僕がスクールを始めて間もなく僕の生徒さんの紹介で知り合いました。彼は日本の大学を卒業していて日本の事情もよく知っていたので、たまに一緒に食事をしては何かと相談に乗ってもらっていたんです。
BB:張さんもテニス経験者なのですか?
藤本:ええ。張さんは今33歳。10歳で始めているのでもう20年の経験があります。ナショナルチームには属していなかったのですが、試合には出場して好成績を収めていたようです。
大好きなテニスでビジネス展開をしようとしていて、僕が借り上げたコートの共同経営を始めた時点で彼はすでに3面のコートを確保してテニススクールを運営していました。彼は中国で日本式のテニススクールを広めたいと考えています。
共同経営するコートでは、彼がコート管理、商品販売、会計を、僕はレッスンスクールを担当というふうに業務を分担しています。
BB:この3年で、たくさん大変なことがあったと思いますが。
藤本:中国人と関係を築いていくのは難しいですね。時々、何が本当のことなのかわからなくなることがあります。例えば、同業者とはよく知り合うので、きちんと挨拶して自己紹介をするようにしているのですが、先方はといえば、「ナショナルチームにいた」とか自分を誇大広告する人がほとんどですね(笑)。そのうちに他からどうも本人の言ったのとは違う話が聞こえてきたりします。日本人は謙虚に自分を控えめに言うので、はじめは驚きました。今では最初から相手の言うことを鵜呑みにしないようにしてます(笑)。

(写真)合宿で子ども達を指導する張さん。大きくて温かい人柄が子ども達に人気。
BB:ビジネスの場面でカルチャーショックだったことは?
藤本:今年の夏、あるテニスクラブと業務提携を結ぼうとしたんです。僕からもっと高額の契約金をとろうと思ったのか、先方が、その時契約しようとしていたインドアのコート以外に、そのコートの外にある国営のアウトドアコートも来年には自分達のものになるからと言うんです。その時僕はただ「それはすごいなあ」と思っていたのですが、中国人の友人達に話すと「国営なんだからそんなはずはない」と言われて。よく考えたら分かることなんですが……。すぐに人の話を信じてしまうので、よく張さんに注意されます。
BB:日本語ができて日本のこともテニスについても熟知している張さんがビジネスパートナーで、心強いですね。
藤本:本当に頼りにしています。
先日も、こういうことがありました。中国人コーチを増やしたいなあと思っていたところへ、張さんのスクールのコーチが辞めて田舎に帰ったと聞き「彼が来てくれれば」と思って早速誘おうとしたところ、なぜか張さんに「彼はやめておいた方がいい」と言われたんです。どうしてだろうと思っていたら、実際は、彼は田舎に帰ったのではなく北京にいたんです。トラブルがもとで辞めたのに、実家に帰ると嘘をついていたんです。僕は彼が嘘をつくわけがないと思っていたのですが、ある時テニスコートで彼と偶然出くわして、ああ、やっぱりウソをついてたんだなあと。
僕はつい人を信じてしまいがちだし、何かをやりたいと思うと、その気持ちだけで走りそうになってしまいます。そんな時に、一歩踏みとどまって、引いた目でみなくてはいけないということを教えてくれる張さんには感謝しています。体も190センチくらいあるのですが、日本人よりも優しい、僕にとって兄のような存在です。
信頼できる共同経営者を得た藤本だが、中国人との信頼関係構築は、最大の課題だという。
BB:中国でビジネスをしていくうえで、何が大事だと思いますか?
藤本:まず、日本人がいくら頑張っても中国人の人脈と深いつながりにはかなわない。やっぱり、いかに中国人の助けを借りていくかは大事だと思います。何か問題が起きた時、相談できる中国人がいないと、日本人だけでやっていると絶対つぶれてしまうと思います。
でも、いきなりビジネスの関係から入るのはムリだと思います。張さんと僕との関係も、はじめは友人でした。まず、先にしっかりとした関係を築くことが大事。逆に、
それがしっかりできれば、今後のビジネスも変わってくると最近感じています。
中国人のテニス界の人脈も北京に来た当初よりかなり増えましたが、今後もっとつながりをつくっていかないと、テニス業界でサバイバルしていくのは厳しいでしょう。経営上のプラスにつながるかどうかはさておいて、僕にとってはテニス界の人脈もひとつ、ビジネス界の人脈もひとつ。ビジネスにつながる場合もあるかもしれません、そういうことを考えないで人としてつき合っていくことを大事にしたいです。(文中敬称略)
3人め: リュウバイシン 劉佰鑫(北京ナショナルチームアシスタントコーチ兼マネージャー)
テニスの新しい方向性を示してくれた同い年
初心を思い出させてくれた大切な友人
インドアコートを一面借り上げたことで、生徒も増え、経営は順調に推移している。しかし現在の状況は藤本が当初思い描いていた理想とはまったく違うものとなった。
気がつけば、生徒はほとんどが日本人。「これが自分が本来やりたかったテニススクールの姿なのか」。忙しさに翻弄され、「テニスアカデミーをつくる」という初心をすっかり忘れかけようとしていた藤本に、再び熱い思いを思い出させたのは、現状に妥協せず、野心を持った同じ年の劉佰鑫だった。
藤本:劉佰鑫は北京ナショナルチームのアシスタントコーチ兼マネージャーです。
僕が北京に来たばかりの2009年のことです。北京で行われるテニスの試合に参加するために日本から来ていた知り合いの日本の選手を、きちんとした環境で練習させようと連れて行ったコートで知り合いました。劉は、ナショナルチームのマネージャ―として僕らを案内してくれましたのですが、同い年ということもあり、すぐに意気投合し、食事に行ったりするようになりました。

(写真)劉佰鑫と一緒に開催した
日本語学校向けのプロモーションイベントで
BB:ということは、劉さんはテニスのエリートということですか?
藤本:たしかに上手ではありますが、どちらかというと指導者のエリートです。彼は高校でテニスをスタートし、その時は遊びでやっていたようですが、その後、北京体育大学でテニスを専攻しました。選手としてというよりは、グリップの持ち方といった指導方法を基礎から学んでいるので、初心者らトップレベルではない選手を教えるのに優れているんです。ずっと選手としてトップでやっていた人は自分の経験から得た精神的なものは教えることはできますが、技術指導などは教えられません。つまり、テニスコーチとしては、選手としてものすごくても指導のノウハウがないと何も教えられないんです。テニスができなくてもできる、マネージメント能力が高いということです。
BB:彼はどういうきっかけを与えてくれたんでしょう。
藤本:実は1年ちょっと前ぐらいから、彼に誘われて一緒に中国人のレッスンをやっているんです。
というのも、ある時、彼に「中国にいるのになんで日本人ばっかり教えてるんだ。中国人にも教えるべきだ」と言われたんです。彼の言葉を聞いてはっとしたんです。自分はやりたかったのは、日本人、中国人、外国人みんなにレッスンをすること。テニスを通して、いろんな国の人々が交流を図れる場をつくること」そして「世界に通用するプロのテニス選手を育成すること」だと。開校以来ずっと血を吐くかと思うくらいに忙しかったので、初心をすっかり忘れてしまっていたんです。
「一緒に中国人に教えないか」と、彼は中国のテニスに関する情報や共同事業の詳細な提案書をつくり、僕にプレゼンをしました。内容はもちろんのこと、彼の熱心さにも刺激を受け、見習わなければと思いました。
劉の行動力と言葉は、藤本を刺激した。こうして藤本は劉と協力し、中国人を対象にしたレッスンを行うようになる。
BB:なぜ、彼を信用できたのですか?
藤本:彼はナショナルチームのコーチなので公務員です。生活は安定していても高収入は望めない。だからこそ、彼だけではなく、中国人は何かチャンスがないか、うかがっているんです。仕事はやめたくない、でも空いている時間で何かやりたいという彼の気持ちはよくわかります。それにずっと友人として築いてきた信頼関係がありましたし、もしここで騙されているんだったらそれはもう仕方がないという気持ちでした。
BB:劉さんと一緒にどういう事業を始めたんでしょう。
藤本: 日本語専門学校や英語の学校に働きかけて、中国人生徒向けにイベントを開催しました。2カ月おきに20人ぐらいを集めて、日本語を勉強しながらテニスを体験するイベントを開きました。参加者の中には、テニスに興味を持ってスクールに入会してくれたり、プライベートレッスンをしたりするようになった方もいます。彼はビジネスにもとても真剣です。忘れていた初心を思い出させてくれただけでなく、中国人を増やすきっかけをつくってくれました。今のところ、ほとんど収入はないですが、将来、何かの役に立つといいなあと思います。
現在、日本人の生徒数は120人。設立から2年、藤本は新たな態勢を整え、次の段階へと進み始めた。
藤本:来年中には中国人の生徒を50人ぐらいにしたいですね。と同時に日本人も増やして200人ぐらいにしたい。1年後の目標は日本人3割、中国人5割、外国人2割です。
今は試合に出る選手育成コースと初心者や趣味などのリクリエーションコースに分けてレッスンをしています。生徒さんが増えて、日本から日本人コーチを招きました。彼にリクリエーションコースの練習を任せ、初心者から試合に出たいと考える子までを専門に育ててもらい、僕は主に選手育成コースの生徒を指導しています。また、経営は僕が、指導は日本人コーチがというように、役割を分担して組織的にやっていくことがより現実に近くなりました。
中国人のコーチの取得は今は考えていません。僕が英語と中国語ができるので、日本人か日本語ができるコーチを増やしたい。将来的には外国籍のコーチも増やしたい。よりよいスクールにするにはコーチの育成も重要だと思っています。

(写真)テニスに興味のある中国人が増えていることを実感する
BB:テニスアカデミー設立のプランを教えてください。
藤本:スクールはあくまでもアカデミー設立への第一歩です。アカデミーには生徒たちが生活する小規模の寮も併設し、テニスに集中できる環境、プロを育成するため、できる限りのいい環境を整えてあげたいですし、そしてアカデミーだけでなく、レジャーとしてテニスをする人が増えているので、自宅から通うスクールと時間配分をしっかり行い、両方一緒にできる場所を作りたいですね。プロ選手も輩出するには、まずアカデミーを作らないと始まりません。民間アカデミーなので学校と交渉も必要です。ビジネス的に考えたら、最初にスクールを作って土台をつくってからと考えています。
BB:スポーツビジネスの世界からもチャンスを求めて中国にたくさんの人や企業が入ってきていますが、日本人の強みをどう発揮していきますか。
藤本:世界標準で見ても、日本人コーチは細かく真面目に教えてくれるだけでなく、指導レベルが高いのは確かです。今後はもっとコーチを増やして、自分がもっといろいろ動けるようになれれば。
指導する立場から感じる日本人と中国人の違いは、日本人は一見真面目で、言われたことをきちんとこなしますが、中国人はわがままで、言ってもやらないこともしばしばですが、ただ、追い込まれた時の集中力、底力は中国人の生徒はすごいです。
試合で勝っていくテニスを目指すなら、わがままなくらいの方がいいと思っています。日本人はひとつのものを2人いたら2人とも譲りますが、中国人はけんかしてでも取り合う。試合の勝ち負けを決めるのはそういうところだと思うんです。僕は日本人として礼儀正しさと謙虚さを持ってテニスを広めていきたいと思います。試合では別ですけどね。(文中敬称略)
Vol.4 日本料理店経営(北京和僑会理事)北京市有薫一心餐飲有限公司総経理 高山貴次氏(34)
1人め:ヤンジュン 閻郡(42)
「これぞ中国」を見せてくれた厳しく優しい老北京

(写真)高山 貴次
<プロフィール>
たかやま たかつぐ。1976年東京都出身。実家は東京・赤坂の九州郷土料理店の名店『有薫』。3人兄弟の二男。95年3月高校卒業後、北京語言大学に留学。97年帰国、サラリーマンを経て、2001年旧正月に再び北京へ。日本料理を提供する北京市有薫一心餐飲有限公司を設立と同時に1店舗目をオープン。現在は北京で日本料理店、バーなど8店舗を展開。2011年春、千葉・幕張にも出店。
高山が高校を卒業した1995年の日本は、阪神・淡路大震災、急激な円高などの外的なショックが重なり、経済が足踏み状態だった。そんな中、改革開放を進めていた中国市場が注目されるようになっていた。
高山の実家は祖父の代から九州、東京で有名九州郷土料理店を営む。90歳を過ぎるまで店に出た祖父も、2代目を継いだ父も、店にこの人ありきと言われるような、存在そのものが店の看板となるキャラクター。高山は、そんな祖父や父の姿を見ながら3人兄弟の二男坊として育った。
「何か人と違ったことをやりたい、人と違ったところで生きていきたい」。大学進学を考えていた高校生の高山は、メディアが盛んに取りあげる中国に惹かれた。
高山:将来を迷っていた時、テレビで「これからは中国だ!」としきりに言っていました。それを見て「中国語を身につけて何かしたい」と漠然と考えるようになりました。それで大学の中国語学科を3つ受験しましたが、全部落ちてしまいました。辛く厳しい浪人生活を覚悟していたのに、なんと親は「浪人は許さない」と。
BillionBeats:なぜ北京に留学することになったんですか?
高山:親父から留学を勧められたんです。正直言うと、その時最初に頭をよぎったのは「これで1年間勉強しなくていい、きっと北京に行ってしまえばいいことがある(笑)」。その頃、僕の中国のイメージというと香港の飲茶。「美味しい飲茶を毎日食べて、きれいな女の子がいっぱい」。まだ高校生ですから考えることと言ったらこの程度でした。

(写真)父と結託して北京留学の
甘い夢を見させた閻さん。
「この笑顔に安心してたのに..」(高山)
BB:すごく若者らしいですね(笑)。
高山:父には中国人の知り合いがいたんです。北京出身の閻さんというその人は、東大大学院に留学中の26歳でした。父に紹介されて初めて会った時「北京なら私の両親が住んでいるので安心してください」と言われました。さらに、彼のお父さんも北京ですごい力を持っているという話もしてくれて、不安がなくなりました。
閻さんは「留学前に日本で中国語は一切勉強しちゃダメ」と言うんです。発音がおかしくなるからとアドバイスされ、その言葉に従って本当に勉強しませんでした。
ついでに「なぜ、留学先に北京を勧めるの」と聞いたら「あなたは上海に行くときっと遊んじゃう。北京でがんばれ」と(笑)。
北京から入学書類が送られてきて、自分が知らない間にどんどん留学の手続きが進んでいました。大学のパンフレットがまたとんでもなくボロボロで、「中国は今、本当に発展途中なんだなあ」と、少し不安になりました。
事前に寮を申し込まなくてはならなかったのですが、寮といっても「2人部屋・風呂なし・トイレ共同」から、ホテルのようなフル装備の部屋まで幅広いんです。さすがにトイレも風呂もない部屋はいやだったので「ルームメイトはいてもかまわない、エアコンもなくてもいいから、テレビ、トイレ、シャワーがある、真ん中ぐらいの部屋にしてください」と閻さんに強くお願いして手配してもらいました。
「異国の地に行く」。同級生とは違う世界に一歩踏み出そうとしている自分が、カッコよくも思えた。高校を卒業してから留学が始まる9月までの半年間、高山はアルバイトをしながら自由な時間を過ごす。
「北京に行ったら、すごいことになるぞ」。北京生活への期待で胸を膨らませていた。
高山:8月下旬、僕と親父と閻さんほか4人で初めて北京へやって来ました。降り立ってから入学までの数日間、閻さんが北京観光や食事に連れて行ってくれました。豪華な料理を食べ、夜はきれいなお姉さんがいるお店にも連れてってもらい、自分が思い描いていた中国がそこにありました。
BB:入学してからは?
高山:一切中国語を話せない僕には入学手続きだって大変なんです。閻さんに電話をかけて来てもらい、助けられながらようやく入学手続きをしたその足で寮に案内されたのですがーー。木の机の引き出しを開けると、驚くような数のゴキブリが……。とりあえず見なかったことにして閉めました。でも部屋を見回せば、ベットの上には体育のマット運動で使ったような古いマット。机には古ぼけた魔法瓶とブリキの洗面器みたいな食器が。刑務所かと思いました。唖然としている僕を横目に閻さんは「次があるから」とそそくさと帰ってしまったんです。
「ちょっと待って、風呂は?」。……。これは騙されたなと思いました。
BB:散々なスタートだったんですね。
高山:天国から地獄です。
食堂のごはんは油が合わず、1カ月くらいお腹の調子がおかしいままでした。そんな時、1年間使えるオープンチケットを持っていたことに気がついたんです。留学前に親父と閻さんが束になって「海外といってもこんなに近いんだから、いつでも行ったり来たりすればいいじゃないか」と僕を諭した時、買い与えられたのは往復のオープンチケットだったんです。
本当に体調が悪かったので、1、2週間日本に帰って調子が整ったらまた戻ってこようと思い、親父に電話したんです。すると、北京に来る前はあんなにいつでも帰ってこいと言っていたはずが「一度志を持った人間がやすやすと帰ってくるんじゃねえ」とガチャン。なぜか、閻さんまで音信不通に……。
後で聞いたところによると、閻さんもだいぶ心配したらしいですが、敢えて連絡をしなかったみたいです。当時の話になると、閻さんは未だに「あれ、そんなことあったっけ?」ととぼけていますが(笑)。(文中敬称略)
2人め:ワンチュエンガン 王全剛(42)
その熱意が、北京に戻らせた
90年代、北京の留学生活は電話をかけるだけでもひと苦労。極寒の中、数少ない国際電話がかけられるボックスの前の長い列に並ぶしかなかった。寮の電話事情はというと、各階に1台の黒電話があるだけ。その電話さえ、荒くれ者の留学生により破壊されていていた。
思い描いていた留学生活とはかけ離れた、寮での過酷な生活。カルチャーショックの中で、高山はーー。
高山:中国にいても、日本の大学でキャンパスライフを楽しんでる友達とつい比べてしまうんです。例えば、大学のサークル活動ひとつとっても中国にいるとイメージが湧かなくて「コンパって、なに?」という感じでした。
「こんなところで羊肉を食べて、オレは何をやってんだろう」と思うこともありました。高校を卒業したばかりで何をするにも不器用で、留学生の輪に入って楽に生きるのすらままならなかったんです。
日本の友達に国際電話しようにも料金が高い上に、国際電話ができるボックスが少なくて。200元(2011年12月現在・約2200円)もするカードを買って、行列に並んで電話をかけてました。北京には日本語ができる閻さんの弟さんがいたのですが、連絡もとれなかった。北京でとりあえず生きてはいるものの、生活、食事、習慣など、いろんなことに耐えていたような気がします。
BB:いちばん辛かったのはどんなことでしょう?
高山:よくお腹を壊したのが辛かったです。
ある時、中国人が購買部で親子丼やかつ丼、チャーハンのような日本食の弁当を売りに来ていたんです。学生食堂がイヤでたまらなかった僕には神様に見えました。大して美味しくはないけれどちゃんとカツ丼。「美味しくない」と文句を言いながらもしょっちゅうお世話になっていました。その弁当を売っていた中国人が、ビジネスパートナーとなる王全剛さんです。僕の実家が日本料理店を経営していると知ってからは、これはどう作ればいいのか、何を売ればお客さんが増えるかといった相談を受けるようになり、僕も喜んでアドバイスしてました。
BB:仲よくなったきっかけは?
高山:留学2年めの冬、寒い日にある店で牛丼のようなものを食べたのですが、どうしても生卵を溶いて食べたくなって。「やばいかなあ」と思いながらも食べたら見事に当たってしまい、部屋でのたうち回っていたんです。ルームメイトが僕の惨状を王さんに話したみたいで、雪が降る中「大丈夫ですか?」と、お弁当と果物を持ってわざわざお見舞いに来てくれた。うれしかったです。彼の方が6歳年上でしたが、いい友達になれるかもと思いました。

(写真)01年、高山が北京に戻って一緒に開業した当時の王さん。事務所にて
2年間の語学留学後は北京大学への進学を考えていた高山だったが、北京に住んでみて感じたのは「中国への失望」だった。「周りが言うほど中国は成長しないのではないか」。これが高山の出した答えだった。中国語も上達し自信をつけた高山は、2年間の留学生活に終止符を打ち、日本で就職する。
その3年後の2000年、「将来は一緒に日本食料理店をやろう」と冗談で話していた王が来日。バリバリのサラリーマンとして働いていた高山を訪ねてきたことから、高山の新たな人生が動き始めた。
高山:王さんは、96年には北京語言学院の近くで日本料理屋を始めていました。ところが、2000年頃になると、北京で日本料理店を経営するのに見よう見まねでは通用しなくなってきていました。危機感を持った彼は、家族や親戚から借金をして、日本料理とはなんぞやということを知るために来日したんです。約2週間、僕の西葛西のアパートに居候し、僕の仕事が終わるとレストランや居酒屋から寿司屋まであらゆる業態と価格帯の日本料理店に連れ立って出かけました。そして、その日体験した店や味を反芻しながら王さんの店づくりについて連日朝まで話し合いました。そんな中で、ぜひ協力してほしいと彼から誘われたんです。
BB:その時に王さんのビジネスパートナーになろうと決めたんですか?
高山:僕自身、97年に帰国してからも中国に関するニュースが流れると知らず知らずに見入っていたりして、ずっと気になっていました。99年頃には街がキレイになってきたなどという報道を見るようになり、中国はこれから伸びていくんじゃないかと改めて思い始めていたんです。
でも、中国で日本料理屋を始めたものの中国人に乗っ取られた、などの日本人と中国人のだまし合いみたいな話は聞こえてきていました。それで、王さんに、僕が聞いた悪い例をくまなく話し、想定されるあらゆる状況を全て話し合いました。そして、それでも一緒にやっていけるんじゃないかと思えた。それで、北京に戻ろうと決心したんです。
BB:サラリーマンを辞めることに迷いはありませんでしたか?
高山:もちろん迷いましたよ。でも、会社員として経験も浅く失うものがなかったので「とりあえず行ってみようか」と、留学と同じようなノリで行動に移しました。
赤坂の店は兄貴が継いでいましたし、二男の僕がちょうど「こいつにとりあえず何かやらせてみよう」と言われるポジションにいたのは家族にとってもよかったようです。海外出店に憧れていた両親は、賛成してくれました。
2001年の旧正月、高山は再び北京へ。今度は北京で日本料理店を始めるために。2008年夏季オリンピックの北京開催やWTO正式加盟が決まるなど、中国が世界から注目され始めた時期でもあった。
「中国は今、俺を求めているんだ。俺が行くしかない」。根拠のない自信を胸に、父親から借りた200万円と自分で貯めた50万円の現金をポケットに入れて北京に乗り込んだ。

(写真)北京語言大学東門前にオープンしたての
記念すべき1号店(当時)
BB:最初から料理人ではなく、経営者としてやっていくつもりだったんですか?
高山:実家の日本料理店は創業者の祖父も二代目の親父も店の主として看板のような存在で、ふたりが僕のロールモデルでした。経営者、プロデューサーとしてやっていくのは僕にとって自然なことだったんです。だから北京でまず事務所機能をつくり、同時に1店舗めを北京語言大学の東門にオープンしたのですが、11月にはオリンピック開催の影響で立ち退きに遭ってしまいました。
ビジネスパートナーの王さんとも最初は意見が合わず、けんかばっかり。日本人と中国人ではこんなにも考えが違うのかと実感させられましたね。
BB:それにしても、王さんは運命の出会いとなりましたね。
高山:本当にそうです。現在、独自でビジネスをしている王さんは、一心グループの株主でもあります。
「どうしたら北京でやっていけるんですか?」とよく聞かれますが、事業の成功に法則はないと思うんです。
僕は人との出会いに恵まれているとつくづく思います。そう言うと「高山さんが人を大事にしているからですよ」と言っていただいたりしますが、仮にそうだとしても、人とのつながりのベースである出会いは運や巡り合わせですし、僕がなぜこんなにいい巡り合わせのもとにいられるのか、これを言葉で説明するのは難しいんです。
ふとした瞬間に心から「お天道様ありがとう」と思うくらい、運がよかったと思うことの連続です。でも今後どうなるか、一瞬先は闇。
僕は、2001年に「これからは中国だ」と思った延長線上にまだいます。もっともっと戦わなければいけないなあと思うと同時に、不安です。

(写真)オープン当時のスタッフと。高山、若干24歳。
BB:この10年で高山さんを取り巻く環境は変わりましたか?
高山:中国の一般の人がお金を持つようになり、プライドをもってある程度のレベルの仕事をするのが当たり前になった今、正直に言って、これから中国ビジネスをしたいという人にたやすく勧められない部分はありますね。
中国で出店して10年になりますが、そもそもこの10年の間に苦境をくぐり抜けて利益を出してきた日本人が果たして何人いるか、チャイニーズドリームをつかんだ人はどれくらいいるかーー。表面上はハッピーに見えても、誰もがひと言では語れない矛盾や葛藤を抱えているんじゃないでしょうか。
僕自身、10年経って今、中国はそんなに簡単ではないと思うようになりました。 (文中敬称略)
3人め:ガンヤンフォン 甘央凰(48)
偉大なるおばちゃんは‘大衆目線’
2001年の旧正月明けに事務所開設と同時に最初のお店をオープンした高山。
1年後、2店舗目を計画するも次第にパートナーと考えが合わなくなり、パートナーと別れ、自分で運営していくことを決意する。その時、パートナーや中国人スタッフのクッション役となった女性がいた。
高山:パートナーの王さんは別のビジネスを始めることになり、日本料理店の事業は僕がひとりでみることになったんです。当時、中国人スタッフが30人くらいいたんですけど、日本人の僕が彼らを束ねるのは大変です。それを一手に受けてくれた偉大なるおばちゃん、その人が今も私の下で働いている甘央凰さんです。
BB:どうやって知り合ったんですか?
高山:1号店の工事の真っ最中のある時、工事責任者がペンキを塗りながら「うちのかみさんを使ってくんないか」と。「昔、国営企業で会計をしてたんだよ」と言われ、ちょうど事務所にスタッフが必要だったので「ああいいよ。連れてきてみなよ」と安請け合いしたら、やって来たのは恰幅のいい、いかにも‘中国人のおばちゃん’。正直「やばいなあ」と思ったんですが、ひとまず事務所で採用しました。声がものすごくデカくて、ドアを閉めているのに甘さんの話し声が聞こえてくるんです。
BB:第一印象は最悪だったんですね。
高山:彼女にとって僕は初めての外国人でしたので、お互い微妙に壁があるかもと思っていたんですが、中国的おばちゃんのいいところで、遠慮なくズカズカと僕の内側に入ってきて、早口で聞き取りづらい北京語を弾丸のように繰り出すんです。
はじめは僕の意向をわかってくれなくて困ることがありましたが、彼女は頭がよく、すぐに理解してくれるようになっていきました。
2店舗目を計画していた当時、できれば3店舗目まで一気に出店したいとも考えていて、僕が経営に集中したい時期に彼女がスタッフとのやり取りを責任を持ってやってくれたのが非常に助かりました。例えばボーナス支給のタイミングで中国人スタッフのテンションを上げるにはどうしたらいいかという時、中国人の感覚を彼女は大衆の目線でわかっています。中国人一般の感覚に基づいて「こういうやり方がいい」と提案してくれました。

(写真)05年10月、北京の友人と全スタッフが参加した、北京市内の中華料理店での高山の結婚式は、甘さんがとり仕切った
BB:たしかに日本人ではわからない部分がたくさんありますよね。
高山:彼女はスタッフの不平不満などを僕の代わりに受けて、スタッフ間の微妙な調整をし続けてくれています。例えば、調理人から副調理長に昇進する場合、副調理長候補という時期があるんですが、その期間もきちんと副調理長待遇の賞与を与えたほうがいいとか、売上目標を3か月連続で達成した場合はスタッフの誕生日会の費用をもっと上乗せしようとか、スタッフのモチベーションが上がるようなアドバイスをしてくれます。
また、年に1回のスタッフとの個人面談には彼女が同席して僕の代わりにスタッフからいろいろな話を聞き出してくれます。例えば、皿洗いをしてくれているおばちゃんの家庭の悩みとか、僕では聞き出せないし相手も僕には打ち明けにくいいようなことも、甘さんがいるとわりと簡単に話してくれます。
そうやってひとりひとりから話を聞くと、それぞれがいろんな悩みを抱えていることがわかりますし、店で会った時に僕からも自然に声をかけられるようになります。若いスタッフはほとんど寮に住んでいるんですが、彼らはまだ精神的に弱い部分もあるので、彼らのお母さん的役割も担ってもらっています。
BB:彼女なしでは現在の一心グループはなかったということですか?
高山:彼女は体調を崩しながらも、自分のことより店を気にかけてくれるような人です。2号店を出した時には僕の代わりに現場を見てくれるなど、信頼関係という言葉では言い表せないくらいです。彼女がいなかったら、多店舗展開は実現していません。
中国で飲食業を経営していく現場には、日本とは違う難しさがあります。マニュアルなどなく、出会いの運やタイミングの問題もあります。そんな中で外国人の僕が抱える矛盾を全部受けとめてくれる。こんなやさしい中国人が本当にいるのかという中でやってこられたのは幸せです。
現在、高山は更なる事業拡大を目指し、事務所機能を強化するとともに、店舗では調理長とフロアリーダーを同じ権限を持つポジションにする、インセンティブ制を導入するなどの組織改革を行っている。
高山:漠然と、6店舗までは自分のテリトリーの中でなんとかなると思っていました。でも、7店舗以降になると、組織本部を強化しなければ広範囲に対応しきれなくなります。そこで事務所を会計部5人、仕入れ部3人、主任1人、秘書1人の構成に強化し、各店の幹部には権限を持たせて店の運営を任せてみることにしました。
そもそも、中国人の幹部たちは非常に独立心が強いですが、資金や営業許可許可などの問題で、自分で店を出すのは大変です。そこで、彼らに独立せずとも起業に近いチャンスがつかめる舞台を提供し、活躍に比例して年収が上がるようなインセンティブ制を導入しました。
BB:店舗ごとに競わせることにもなるわけですね?
高山:インセンティブ制を導入してからは、店舗によっては自分たちで工夫して原価率の低い材料で開発した商品が中国人のお客様に好評で、ひいてはリピートにつながったというケースもあります。まだ試行錯誤中ですが、確実にいい方向に動いていて、売上げも前年比で伸びています。
2001年、24歳の高山が、ホールスタッフ5人、裏方8人、事務所は24歳の高山と3人のスタッフで始めた90平方メートルの1号店を皮切りに、3店舗目でスタッフは50人を超えた。2007年には「和一心」と経済貿易大学店の2店舗をオープンし、現在、一心グループは6店舗を展開する。130人を越えたスタッフの団結力を強めるために、高山は年に3回、従業員が参加するイベントを開催している。
高山:毎年5月1日には朝7時から開店前の時間に、各店舗対抗の大運動会を行っています。入賞チームには賞品が出るので、店舗ごとに1カ月前から練習を始めて、面白いことにスタッフ全員でお揃いのTシャツをつくったりするんです。夏には全店休業にして従業員全員参加の遠足も開催しました。郊外でみんなで川下りをして、お昼を食べて、山に登って。そして、1年目から開いているのが大遊技会です。旧正月前に店舗ごとに2つの演目を披露してもらいます。このほか、3カ月に一度、誕生日会活動手当を支給しています。みんなでひとつの目標に向かって困難を克服するというのが狙いです。学生街にあるお店が多いので、暇な時期はスタッフがまとめて辞めたり、ケンカになったり、何かと問題が起きやすいのですが、それを回避するためにも役立っています。

(写真)圧巻、一心大運動会!
BB:これから中国という荒野に飛び込もうとしている起業家にアドバイスをお願いします。
高山:今、中国人スタッフを100人以上雇って事業を展開しているとは言っても、実力のある中国企業や中国人に同じことをされたら負けるのはわかっています。今後、僕の事業を真似されることもあるだろうし、真似した方が伸びる可能性も高いです。資金力、コネクション、どちらをとっても、外国人は中国人の足元にも及ばない。
それでも中国市場で闘っていくには、僕が甘さんという中国人を味方に得られたように、信頼できる中国人のパートナーを持つことは不可欠です。ビジネスパートナーでなくて妻や夫などプライベートのパートナーでもいいんです。
要は、自分が中国側に立てるかどうか。ここは中国ですから、中国人の視点に立って物事を考えられるかがポイントです。(文中敬称略)
Vol.5 リサーチ会社経営・安田玲美(北京和僑会理事) ー 北京世研伝媒広告有限公司・北京世研信息諮訽有限公司・等、CRCグループ10社およびエンジェルエンジェル服装服飾有限公司の総経理

(写真)安田 玲美
<プロフィール>
やすだ なるみ。1972年東京都足立区生まれ。小中高時代を岩手県久慈市で過ごす。94年大東文化大学外国語学部中国語学科卒。同9月北京の首都師範大学に語学留学。97年5月、舞台衣装製作の日中合弁企業を設立するが、倒産に近い状況を経験。さまざまな職を経て2001年、中国社会科学院メディア研究所調査センターに勤務、日中間コミュニケーションを学ぶ。02年調査会社(CRC)を設立、12年2月現在、CRCグループは10社に拡大。
1人め:胡堅(47) ー 撤退寸前を支えたパートナーは、熱い怪獣キャラ
日本と中国が国交正常化40周年を迎える今年、安田も40歳になった。田中角栄首相(当時)が北京で周恩来首相(当時)と国交正常化に関する共同声明に調印したのは1972年9月。安田は同年1月に生まれている。
こうした背景に育った安田は、小4の時、テレビで中国残留孤児の中国人養父母のドキュメンタリーを見て、中国に行きたいと思うようになった。国際関係に関心のあった母が、本を読んでは小さな安田に話して聞かせたことが、中国に引き寄せられた最初のきっかけという。小中高と、卒業文集では将来の夢を「中国語の通訳」と書き続けてきた安田は、大学で中国語を学ぶと94年に北京の首都師範大に留学。以来18年間、北京との縁は切れない。昨年末は女性向けビジネス誌・日経ウーマンの『2012 ウーマン・オブ・ザ・イヤー キャリアクリエイト部門』を受賞した。中国で調査会社を設立し、日本企業の中国展開を支援、日中の懸け橋として事業・交流促進に貢献してきたことが認められての受賞だ。
BB:ウーマン・オブ・ザ・イヤーの受賞おめでとうございます!
安田:ありがとうございます。去年は私の故郷・岩手県久慈市も被災して大変なさなかでしたので、お断りしようと思ったんです。でも、被災したふるさとの仲間の励みになり、私を支えてくれた中国のみんなに喜んでもらえるならと、お受けしました。中国のスタッフがとっても喜んでくれたのが嬉しかったです。
BB:被災後は毎月北京から岩手県久慈市に通って被災地支援を続けてこられていますが、そもそも、中国への目覚めがすごく早いですよね。
安田:ええ。小さい時から中国語の通訳になるのが夢でした。大学では中国語を専攻し、大学には中国人留学生も多く、当時から中国人の友人がたくさんいました。卒業後は中国への留学をと決めていて、母校と提携している北京師範大学に行くつもりだったんですが、中国からの留学生の友人の強い勧めで、彼の恩師で日本語の大家の先生がいる首都師範大学に留学先を変更しました。
BB:17年前の北京はどんな様子だったんでしょう。
安田:「真っ暗」。それが北京の第一印象でした。夜、現在の北京首都国際空港の第1ターミナルに到着し、迎えに来てくれていた車で、市内までただただ漆黒の闇が広がる中を疾走しました。街中に着いてもなお真っ暗でした。当時の北京の夜は本当に暗かったんです。先生の紹介で、すぐに中国共産党青年団の幹部に日本語を教えるアルバイトを始め、仕事を通して生きた中国語を吸収しました。2年間の留学を終えると就職活動のために一旦日本に戻りました。
BB:当時はどんな就職先を希望していたんですか?
安田:北京の大使館の派遣員の職を受験しようとしていました。この仕事なら必ず北京に戻れますから。どうしても中国で働きたかったんです。
留学を終えて日本に帰ったその日の夜、留学中に親しくなった友人が、自分が中国で出会った人たちを一堂に集めて開いた食事会に呼んでくれました。そこで、衣裳のデザイン事務所の社長さんと知り合いました。その女性社長ちょうど中国の天津で会社を設立したばかりでした。社長に同行通訳のアルバイトをしないかと誘われ、就職試験までの間ならと、ふたつ返事で引き受けたんです。
その会社は天津でスタートしていた。法律上の制約により、当時の北京では製造業として独資の会社をつくることはできなかったからだ。だが、天津では材料の供給や委託先など不便が多い。
社長に北京で一緒に会社をつくろうと誘われ、なんとか北京で独資の形態で会社をつくれないものかと周囲に相談していた安田に、留学時代からの中国人の友人が自分の以前のビジネスパートナーを引き合わせた。

(写真)福建の沙県という田舎町にある工場でのフージェン。工場から出てきた染色サンプルでは納得が行かず、2人して飛行機とバスを乗り継いで現地の工場まで直談判に出かけた時のスナップ
安田:「彼とパートナーを組みなさい。絶対に間違いないから。私が知っている人間の中で最も信頼できる人だよ」と、その友人が紹介してくれたのがフージエン(胡堅)です。フージエンは中国の大学で生産管理を学んだあと横浜国立大学大学院に留学し、北京に戻ってからすでにスリッパ工場を経営していました。
彼の方にも、日本人と組みたい理由がありました。当時、内資企業には輸出入権が与えられませんでしたが、外国資本と合弁することで、正規の輸出入権が獲得できます。また、外資企業には免税減税などの優遇政策が適用されていたため、こうした政策を活用したいと考えていたんです。
こうして私たちは共同で会社を設立することにし、彼のスリッパ部門と私たちの衣装部門をそれぞれ独立採算にしました。ひとつの会社で2つの事業をお互いに干渉し合わずに運営していくことにしたわけです。
大陸的な豪快さと日本人以上の繊細さを併せ持ったフージエンは、ビジネスのいろはも知らない25歳の安田をビジネスパートナーとして引き受けた。以来、フージエンのリクエストにより、安田は「ケンちゃん」と彼を呼ぶ。安田が「ドスドスして怪獣みたいな、でもあったかい人」と形容する「ケンちゃん」との打ち合わせは全て中国語。
97年の年明けに日中の合弁企業『エンジェルエンジェル』はスタートした。
安田:私たちの衣装部門はサンリオピューロランドやシーガイヤのオーシャンドームなど、アミューズメントパークのステージで使われるような舞台衣装の制作を主力事業としてスタートする予定でした。ところが、会社設立の手続きなどに当時は驚くほど時間がかかり、ようやく正式にスタートした98年には、すでに日本のバブル崩壊から実質経済にも影響が出始めていました。日本から来るはずだった仕事はなくなり、やむなく方向転換して中国国内で営業をかけていくことにしました。高校・大学時代にバンドをやっていたため、北京に留学してからも現地のミュージシャンの友人が多くできました。その彼らに衣装制作の仕事を始めたことを伝えたところ、友人たちが舞台衣裳の必要な芸能人を紹介してくれ、ステージ衣装の製作を受注するようになりました。ほかに、レストランや工場のユニフォームなども受注しました。日本から専門誌を買ってきて研究して、ナイトクラブのダンサーの衣装などもつくりました。
ある日、レストランを始める日本人の知人から「制服を作りたい」と依頼を受け、見積もりを持って行きました。彼は見積もりを受け取って数字を見ると「だめだなあ、玲美ちゃんは」と言いながら私が書いた金額の横に何か書いているんです。「あれ、高かったかなあ」と思いながら彼の手元をのぞくと、書いてあった数字をすべて倍の金額に書き直していました。経営が苦しいことを知っていたその人は、売上をたくさんつけてくれたんです。
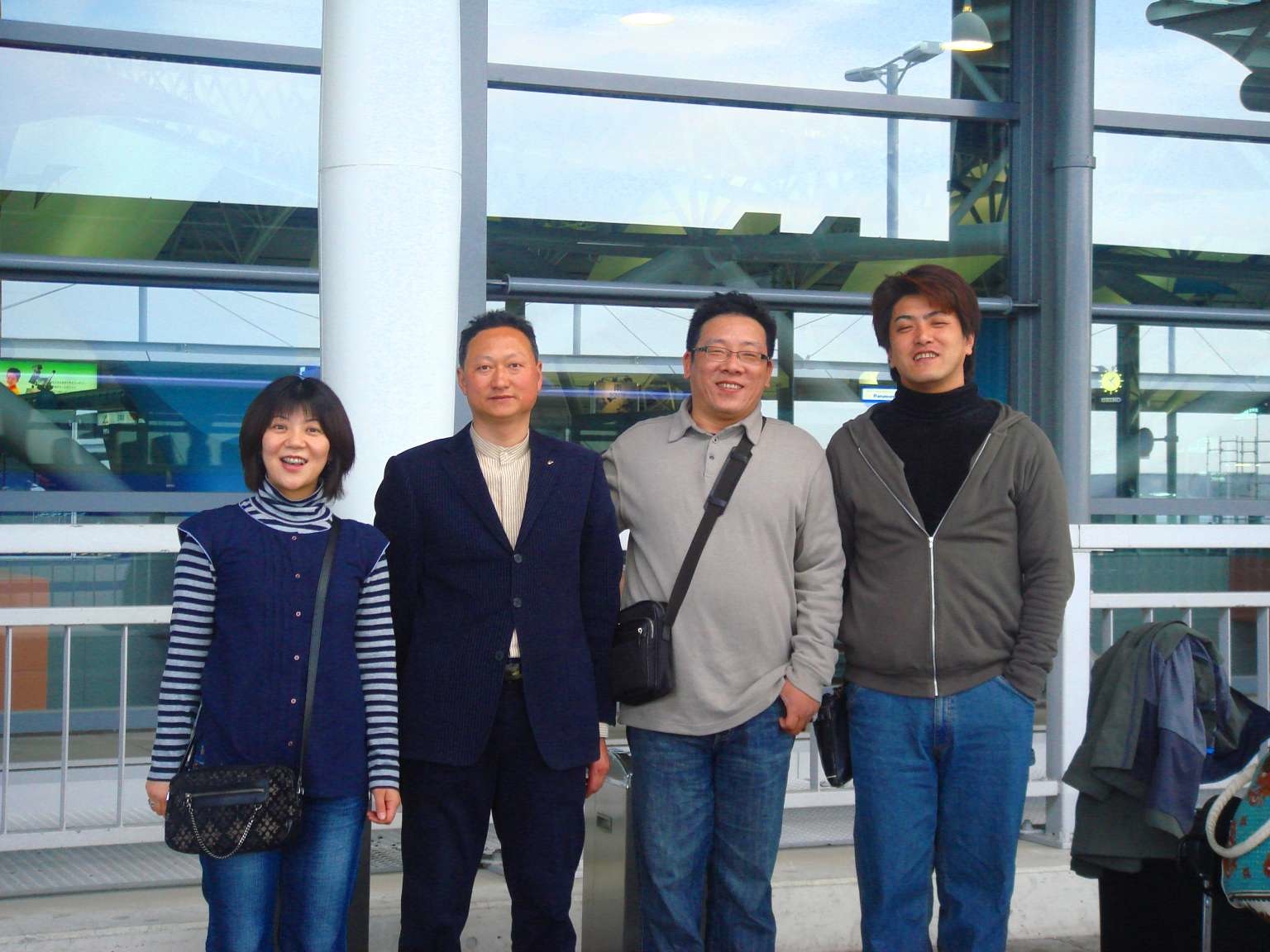
(写真)日本出張した時、関空で出迎えてくれたクライアントとの記念撮影
BB:ケンさんとの共同経営で、難しかったことは?
安田:怒鳴り合いのケンカはしょっちゅうでした。だいたい、ケンちゃんと私の2人の間だと考えはまとまりやすいんですが、第三者が絡むと意見が一致しなくなることが多かったんです。ケンちゃんは短気なところがあって、話が込み入ってきたり意見が合わなかったりすると「もういい!」などと言い出したりするんです。私も若かったので「そんなこと言ったってダメじゃん!」と大声で怒鳴ってました(笑)。お互いプンプンして「じゃあね、バイバイ!」と怒って帰って行き、翌日は何事もなかったかのようにケロリと「おはよう」。
ズケズケと言い合って、後にひかないのがケンちゃんと私のケンカです。
BB:会社の業績はどのように推移したんでしょうか?
安田:ケンちゃんのスリッパ部門は順調に伸びましたが、肝心の私たちの衣装製作部門は、日本の景気が回復して受注できるようになるまで会社を維持しようと北京での営業に走り回ったものの、好転の兆しは見えないままでした。日中かかわらずいろいろな方面から仕事をいただき細々と食いつないでいたのですが、3年後の2000年春、日本側のパートナーがついに撤退を決断したんです。
「玲美さん、このままいつになれば日本の景気が回復するか、まったく先が見えないので、残念ですがあきらめましょう。もう、あなたは自由になっていいのよ」と言われました。
BB:ケンさんのスリッパ部門はどう整理することになったんですか?
安田:事情をケンちゃんに話しました。すると彼は「心配するな。俺の方はうまくいっている。当面会社は俺が維持するから、いつかおまえたちの部門が再開する時がくるまで任せておけ。撤退しなくても、維持費を出さなくてもいいぞ」と言ってくれました。
政略結婚のいいところは、片方がうまくいっていれば倒れることはないということですが、本当にケンちゃんには申し訳なくて。本来は折半するはずだった会社の維持費や諸経費は、ケンちゃんに頼らざるを得ませんでした。
ケンちゃんの厚意に甘えて衣装制作部門を開店休業状態で残すことにしました。その後もケンちゃんの部門の業績は伸び続けました。
BB:ケンさんの事業にはその後もノータッチですか?
安田:ケンちゃんにはお世話になりっぱなしでしたが、2000年にケンちゃんのスリッパ部門が取引先の勝手な都合で在庫を抱えるハメになった時、その在庫の販売先を探したことがあります。
ケンちゃんのところにスリッパを注文していた日本のバイヤーが、中国の別の工場に同時にサンダルを注文していて、そのバイヤーは日本のクライアントと、スリッパとサンダルを同時に納めるという内容で契約していたのです。ところが、サンダルの工場の方で問題が起きて納品ができなくなり、バイヤーが逃げて連絡がつかなくなってしまったんです。でも、ケンちゃんのスリッパはすでに日本の港に到着して3カ月以上も経っていて、倉庫代や輸送費などの請求は全てケンちゃんにきました。莫大な損害です。
ケンちゃんから相談を受けてすぐにそのバイヤーを探して連絡をとったところ、相手は「訴えたかったら訴えてみろ」と開き直りました。頭に来て、日本に戻って探そうとしたのですが、ケンちゃんは「そんな人たちを相手にしても時間と金がもったいない」と。とりあえず、送り返されてきた商品を少しでも現金化するために、中国国内で日本式のスリッパを買ってくれるところを探すことにしたんです。結局、日系のスーパーに20足入りのカートンを数十カートン買い上げてもらうことができました。
そんな大変なことがありつつも、中国が世界の工場として力をつけていった当時、ケンちゃんの部門は日本専門に輸出するスリッパを生産していたので、年間80万足を生産する大工場に成長しました。 (文中敬称略)
2人め:リュウジミン/劉志明(48) ー 日中をつなぐ指標をくれた師匠は宇宙人?
立ちゆかない状況になった衣装製作部門。会社の運営は、好調だったスリッパ製造部門のフージエンに任せ、安田は中国での身の振り方を考えることに−—。
安田:さすがに一旦会社を落ち着けようと決心しました。そして今後のことを考えようとしていた時に、聴覚障害者による中国舞踊“千手観音”で有名な、中国障害者芸術団の日本公演にボランティアとして関わることになったんです。日中間に関わる各方面に支援のお願いをして回ったのですが、2000年の年明けに私の運命を変えた出会いがありました。中国社会科学院メディア研究所調査センター長の劉志明先生との出会いです。
劉先生は、社会科学院のポストにつく以前は、人民大学大学院での研究を経て、日本の一橋大学や神戸大学で研究や指導をされています。98年に中国に戻ってからは、社会科学院で日中間の世論調査やメディアの役割などメディアコミュニケーションを研究されていて、もちろん日本語もものすごく上手でした。

(写真)尖閣諸島問題が起きた直後の2010年9月、予定されていた日中間行事が次々とキャンセルになっていく中、「こんな時こそ対話が大事」と東アジアフォーラム2010を開催した劉。パネラーとしても登壇
BB:劉先生の第一印象はどうでしたか?
安田:初めてご挨拶にうかがった時、紹介者の方が私を紹介する際に先生に向かって「この子、カワイイでしょ」と言ったんです。先生がそれに対して「まあ、カワイイとはいえないですけどね」とあっさり切り返してくれたその対応がすごくかっこよくて、スカッとしました。
そもそも、私は机に向かう勉強は得意ではなく、北京で大学院に進むのを諦めていました。でも、もし将来また勉強する機会があるなら中国社会科学院でというのは私の夢だったんです。だから、劉先生に会った時は「社会科学院の先生!しかも日中のコミュニケーションをやっている!」と、私の中ではアイドルに出会ったに等しい感動でした。それに加えて、紹介者のつまらないマクラコトバに対する鮮やかな切り返しに、すっかりファンになってしまい、すぐにアタックを開始しました。といっても男性としてではなく人間として魅力を感じたということですが。何かあればすぐ先生に電話していろいろ話をしていたよう気がします。
BB:劉先生との出会いはどのように運命を動かすことになったんでしょう?
安田:すぐは何も変わりませんでした。とりあえずは中国障害者芸術団の日本公演を無事に終わらせる方に集中しました。同時に、実は2000年夏から工人体育館という北京の中心部にある競技場の一角でオーダーメイドサロンを経営しました。もともと洋服のオーダーメイドサロンをしていた知人がその場所を引き払うにあたって「この場所を使わない?」と声をかけてくれたんです。当時、おしゃれな洋服なんて北京にはなく、偶然にも私も衣装を作る仕事をしていて素材の仕入れや加工するところの知識やノウハウがあったので、民族大学に留学していた日本人のデザイナーを口説いてお店を開きました。そのデザイナーが1年後に家庭の事情で帰国するまで、エンジェルエンジェルの仕事も引き合いがあれば対応したり、ケンちゃんの工場を手伝ったり劉先生をお手伝いしたりと、いろんな仕事を掛け持ちしていました。
BB:劉先生のお手伝いはどんなことを?
安田:劉先生のところには日本の政府機関やメディア関係からいろんな調査の依頼がきて共同研究をしていました。日本語の部分で劉先生の手伝いをしながら日中間コミュニケーションを学んでいきました。1年後の01年夏にオーダーメイドサロンを閉じると、劉先生に呼ばれ、劉先生のもとで本格的に働くことになりました。
01年、中国はWTOに加盟。APEC国際会議が上海で開催されるなど、国際社会での転機を迎えていた。
APEC開催直後の10月、APECの会場としてつくられたばかりのコンベンションセンター・上海国際会議中心で、中国社会科学院メディア研究所調査センター主催の日中コミュニケーションシンポジウムが開催されることになった。安田はそのシンポジウムの運営を担当し、無事に取り仕切った。それが安田の新たな事業展開へのスタートとなった。

(写真)北京市の日航新世紀飯店で安田は挙式。劉は安田への結婚祝いに、劉のもとでの研究内容をまとめた書籍を中国で出版させた
安田:劉先生のもとで働き始めてすぐ、中国がWTOに加盟したことを受けて日本企業が大挙して中国に押し寄せてきました。中国に本格的に進出するにあたり、中国の市場調査の需要が爆発的に発生しましたが、それを受託できるようなところが中国になかったんです。そもそも市場がなかった中国では市場調査という概念がなかったので、市場調査会社も存在しなかったんです。必然的に、外務省やジェトロなどからの紹介を受けた日系企業からの問い合わせが、劉先生の調査センターにたくさん集まってきました。しかし、国家機関である中国社会科学院メディア研究所では企業の市場調査には対応が難しいため、02年4月、劉先生と一緒に調査会社を始めることになりました。
BB:こうして運命が動いたんですね。
安田:本当にそうだと思います。でも最初、劉先生って本当は宇宙人かもしれないと思っていました。発想がぶっ飛んでいて、いつも時代を先取りした先見性があるというか、誰も想像できないような中国の未来を話したりするので、はじめは先生の言っていることの意味がまったく理解できなくて、ついていくのに苦労しました。先生のところで働き始めて1、2年が過ぎた頃「そういえば、劉先生以前こう言っていたな」ということが実際にたびたび起こり、徐々に劉先生が言われることの背景を理解できるようになっていきました。
私にとって日中間コミュニケーションにおける師匠は劉先生です。日本と中国の理解を促進していくために必要なこととして最初に示された指標は、相手に対する「尊敬」「理解」「寛容」の3つです。当たり前と言われればそれまでですが、国と国のコミュニケーションギャップって、この中の何かが欠けている場合がほとんどなんですよね。
BB:これまでたくさんの会社を立ち上げていますが。
安田:02年に調査会社を立ち上げてから、03年4月にコンサルティング会社、05年4月にはPR会社を立ち上げました。その後、ウェブ調査会社、産業調査会社、上海支社、広州、唐山、成都などの出張所など、現在CRCグループは日本法人を含めて全部で10社です。これは中国の会社法の問題で業種ごとに免許をとらなければならないという特殊な事情のためです。09年末には日本法人を、昨年は中国のメーカーと手を組んで、ネット販売をメイン業務にした合弁会社をつくりました。ここまで経営内容を多角的にできたのは、中国でいろんな人に出会い助けられてきたからだと思います。(文中敬称略)
3人め:ワンヨンチャン/王永強 (41) ー 手仕事継承、日中プラットフォーム構築のパートナー
2009年、安田の会社は中国住宅産業に参入した。それまで、マーケティングやコンサル、PRなど、クライアントからの依頼・委託業務が中心だったが、住宅産業分野でのフォーラムと住宅産業化連盟という組織を運営していくこの新事業は、安田がしかけた。
現在中国で建てられている建築物は使用権でいえば70年後の人達の生活まで影響する。何十年も先まで責任が問われる住宅産業分野でいかに自分達が貢献できるかを考えていきたいのだという。
安田:08年にリーマンショックが起きた時、それまで100パーセント近くが日系企業からの依頼だったのが、一気に受注が減りました。同時に中国企業からの業務依頼が驚くほど増え、日中のクライアントのシェアが逆転したんです。中国の経済構造が内需の方に転換していったこの時期、これまで海外向け商品を作っていた中国のメーカーが自社ブランドを立ち上げて国内向けに動き出すにあたっての業務依頼がたくさんありました。その流れで、中国に足りないモノがあること、中国側にはそれらを日本から購入したいという需要があること、さらに、その需要は確実に増えていることもわかりました。

(写真)中国文化伝媒集団・家文化伝媒中心の常務副主任でもある王は、物質的な豊かさが追求されている現代の中国で忘れられがちな心の豊かさを大切にしている
BB:なぜ住宅産業事業だったんですか?
安田:中国企業からの業務依頼や日本企業との橋渡しをしていく中で、需要が多かったのが住宅産業分野でした。中国の経済成長を支える主幹産業でもあるし、実際問題これから先、中国市場に供給される不動産物件の数を考えても巨大な産業です。また、ちょうど日本企業がまだ入り込めていない分野でした。人の暮らしに直接関わるところでもあり、ぜひともこの分野をやってみたいと思いました。
09年末に中国住宅産業化フォーラムを立ち上げ、2年間で中国全国数十カ所で20回に及ぶフォーラムを開催しました。中国の住宅の未来について一緒に考えていく企業や専門家らによるチームを中国住宅産業化連盟として各地に組織して活動していこうという主旨です。
11年3月、東日本大震災で安田のふるさと・岩手県久慈市は甚大な損害を受けた。以来、安田は毎月北京と久慈市を往復し、地元の仲間と一緒にふるさと復興のための活動に取り組んできた。もともと平均賃金が全国ワースト1位の地域は、安田にいわせると震災がなくても再生困難な地域だった。安田は、地域を根本から復興するには経済復興しかないと考えた。地域の資源をいかに活用し、経済を呼び込んでいくか。安田は鉱物や農産物など、地域の特産品や資源を、既存の流通企業やメーカーとのビジネスマッチングにより商品化、ブランディングしていくプロジェクトをスタートした。同時に、中国市場と地元産品をつなげていくことを考えた時、中国のキーマンとなる人物は安田のすぐそばにいた。建築専門誌『中国建築装飾装修』とインテリア誌『家飾』を主宰する企業家・王永強だ。
安田:10年春頃、私たちが開催した住宅産業化フォーラムに王さんが参加してくれたことがきっかけで知り合いました。王さんは雑誌社を経営しているほか、住宅関係の事業を複数手がけています。甘粛省出身の彼は、甘粛省も含めた中国の各地方の手仕事による伝統工芸品を伝承していく社会活動にも取り組んでいました。
私も岩手県出身で地方のものづくりに思い入れがあったため、すぐに意気投合したんです。彼から、中国の民間の手仕事が産業化できずに廃れていってしまう一方なので日本の伝統工芸の産業化について教えてほしいと言われるようになっていました。お互いの事業やいろいろな話しをしていくうちに、私の中でも彼の社会活動への共感がふくらんでいき「仕事は別にして何か日中伝統文化交流的なことができればいいね」と相談していたんです。

(写真)中国でも多くの伝統文化が残されている南宋の古都・杭州のインテリアショップ『我的手芸』。中国の伝統的な手芸品や中国人アーティストの作品が並ぶ
BB:それを東日本大震災が後押しすることになったんですね?
安田:そうです。昨年、震災が起きたことでその思いはもっと強いものに変わりました。中国にいながら私ができることを考えた時「被災地をはじめ、日本の伝統工芸品と中国市場を結びつけられないか」と思い立ちました。王さんに相談すると「できることからすぐやろう」と。そこで、日本の伝統工芸品を中国で販売するための合弁会社を立ち上げることにしたんです。
BB:具体的にはどのようなビジネスモデルなのでしょうか。
安田:彼の会社はインターナショナルデザイナークラブというネット上の会員制クラブを運営しています。国内20万人のデザイナーはじめ、海外からも多くのデザイナーが参加しているこのクラブのウェブサイトで日本の商品を紹介・販売します。この会員制ウェブサイトが日本のインテリア用品に関するBtoBのプラットフォームの機能を持つわけです。
日本と違って空間をデザイナーがトータルでデザインする中国では、デザイナーが閲覧するネットで商品を販売すれば、大量販売も可能になります。デザイナーにとっても自分の仕事の幅を広げるためにも、業界関係者だけが集まるサイトは優れた販売ツールになり得ます。
彼は上海と杭州にショップを持っていて、そこでも商品を展示・販売する予定です。雑誌『家飾』では「現代に活きる日本伝統文化」というテーマで連載します。1月号で紹介する岩手県の南部鉄器に始まり、漆器や陶器なども取り上げました。
こんなふうに、自分が持っているメディアを使わせてくれるなど、資源を惜しみなく提供してくれます。

(写真)王の経営する出版社が発行するインテリア誌『家飾』1月号では、新連載『現代に活きる日本伝統文化』の初回、南部鉄器の歴史や暮らしに息づく様子を4ページにわたり紹介した
BB:王さんは日本の伝統工芸品をどのように見ていますか?
安田:王さんはNYの大学でMBAを取得した後、中国でインテリアや建築の雑誌を出版する雑誌社を立ち上げた人で、生活の中のアート、デザインで生活を豊かにするということに敏感、なおかつ、それらアートやデザインをビジネスとして中国で取り扱う企業家でもあります。昨年10月には、会津若松で開かれた東日本の伝統工芸品を集めた展示会に、11月には東京で開かれたインテリアライフスタイルリビング展に王さんに行ってもらい、日本各地の伝統工芸品を実際に手に取って見てもらいました。王さんの反応はよく、全部で約50社ほどの会社のパンフレットや名刺を持ち帰りました。
実際、彼はこの時すでに数十社と話をしました。王さんは東日本支援として1年間は全面協力すると言ってくれていて、日本の企業には「サンプル提供が難しければ買い取ります」「私たちが責任を持ってやります」などと日本側にとって好条件を提案しているのですが、半数ぐらいの企業は「まだ商標登録ができていない」とか「コピーされる危険がある」などを理由に及び腰なのが現状です。今後、私たちのビジネスモデルを日本の企業にきちんと伝えていきたいと考えています。
変化のスピードが速い中国で、安田は敢えて目標を設定せずに仕事をしてきたという。師匠・劉志明には「何をどう決めてもそれにこだわるな」「いつどの時点でも、その時にいちばん正しいと思ったこと、いちばん必要と思ったことを選びとっていくこと」「続ける勇気以上に捨てる勇気が大切」と教えられてきた。
毎年、自動車の販売台数や経済成長率など、さまざまな人がさまざまに予想し、なかなか当たらないという事実を目の当たりにし「中国は簡単に予想できる国ではない」と考えてきた安田が、21世紀の2回目の10年を迎えるにあたって、初めて長期目標を設定した。
安田:私は30年後の目標を立てました。被災をした私のふるさとの平均賃金を全国最高レベルまで引き上げることです。今、平均賃金が全国ワースト1位の岩手県は、国で規定されている最低賃金を大きく下回るぐらいに労働に対して価値がつかない地域と言わざるを得ません。でも、根本的に社会の仕組みや構造、価値観を大きく変えていく時期に来ていますし、それができれば、私の立てた目標は実現不可能ではないと。
震災はひとつのきっかけであって、本気で変えていこうとしなければこの町はなくなってしまうかもしれないという危機感を覚えたのも事実です。そして、ふるさとになくなってしまってほしくないと強く思ったんです。
BB:北京からどうやって実現していくんでしょうか。
安田:「ふるさと復興」はどうしてもやらなくてはならないことです。ふるさと・久慈市の復興に自分が関わらない人生は考えられません。自分が中国にベースを持っていることがふるさとに対しての価値になると私は確信しています。
久慈市には世界に自信をもって誇れる資源がたくさんあるので、伝統工芸品をはじめそれらをいかに中国市場とつないでいけるか、挑戦していきます。30年で実現できるかわかりませんが、それくらい時間をかけてやっていく覚悟がないとだめだと思います。日本一給料が高い街、日本中でいちばん有名な街になればというのが目標です。
BB:パートナーたちはどのように支持してくれていますか?
安田:ケンちゃんも劉先生も王永強さんも、私が毎月被災地に行っている間の業務について一切言いません。むしろその逆で、全力で応援してくれています。そういう時、中国人の懐の大きさ、器の大きさを感じます。
仕事をしていると大変なことや崖っぷちに立たされることはたくさんありますが、3人とも必ず「有我在、你放心(私がいるんだから、何も心配はいらないよ)」と言ってくれる。この言葉に勝る励ましはありません。
この3人がいるから何があっても大丈夫だと思えるし、本当にその通り、何があってもちゃんと守ってくれるんです。私もこの人たちのためだったらなりふり構わず全力で返していきたいと思っています。そしていつか、私もこの言葉を誰かに言える人間になりたいと思っています。(文中敬称略)
