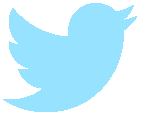北京和僑会リレートーク ー「ビジネスの転機に出会った3人の中国人」

大陸を舞台に日々奮闘する和僑たち。飛躍であれ失敗であれ、そのビジネスの転機には必ず中国人との出会いがあります。北京和僑会は、2010年夏、日中ビジネスに関わる起業家達のネットワークとしてスタートしました。40年近い中国ビジネスのキャリアを持つベテランから、20代の若い起業家まで、様々な業種の100人近い経営者が集まり、華僑のようなタフなネットワークを世界に張り巡らそうと切磋琢磨しています。個性豊かな会員が、忘れられない中国人との出会いを語り尽くすリレートークです。(聞き手:佐藤律)
Vol.1 建築家(北京和僑会副会長) SAKO建築設計工社代表取締役 迫慶一郎 (41)
1人め:ジャンシン(张欣) ディベロッパー・SOHO CHINA,CEO
「洗練と革新の35歳の女性社長。
堂々と確信を持って中国の現代建築を創造する彼女が中国への扉を開いてくれた」

(写真)迫慶一郎
<プロフィール>
さこ・けいいちろう:1970年福岡県生まれ。東工大大学院修士課程修了後、96年山本理顕設計工場に入所。2000年、山本理顕がコンペで勝ち取ったプロジェクト「建外SOHO」の担当者として赴任。04年、山本事務所を退職し、文化庁派遣芸術家在外研修員として米国コロンビア大学客員研究員に。同年、北京に事務所を開設。2008年、四川大地震被災地への学校寄贈プロジェクトを開始。2011年、東日本大地震被災地復興プロジェクト「東北スカイビレッジ」を開始。
迫が初めて中国に来たのは2000年。中国がWTOに加盟する前年である。めっぽうケンカに強い建築家として知られる社会派建築家・山本理顕のもとで2つの公共建築を担当し、ちょうど30歳になる年だった。
建築系大学のトップ・東工大で学んだ迫が建築家を目指した時、意識したのは欧米が主流の現代建築だった。香港を訪れたことはあったけれど、大陸は初めてという中国へは全く関心が向いていなかった迫が、その後、山本のもと、北京経済地区の開発プロジェクト「建外SOHO」のプロジェクトリーダーとして北京に駐在する。
2004年、「建外SOHO」第3期工事の終了を機に山本事務所を退職し、コロンビア大学客員研究員のポストを得てNYに渡ろうとしていた迫が、北京に事務所を開くことになったのは、ほんの偶然の出来事による。
それから7年。プロジェクト数は70を超え、現在は中国国内で300万平米スケールのスマートシティのプロジェクトも進行中。2人でスタートした事務所は、「建てたい」という意欲だけで海を渡ってきた20代の日本人を中心に38人の大所帯になった。
欧米の現代建築に憧れていた迫だが、中国での活躍が今では日本国内でも注目される。その迫に転機をもたらした中国人との出会いとは。

(写真)現場に常駐していた頃。北京の冬はとてつもなく寒かった
BillionBeats:11年前、2000年の北京は迫さんの眼にどのように映ったんでしょうか。
迫:カルチャーショックでした。それまで、北京がこんなに発達した都市だと思ってなかったんです。返還直前の97年に行った香港は、あれだけの高密度な都市に人とエネルギーが溢れているという印象でした。香港に現代建築デザインの先端があるわけではなかったけど、オルタナティブな都市のエネルギーに惹きつけられました。でも大陸にはステレオタイプなイメージしかなくて、人民服、自転車の波、万里の長城、カンフー。それぐらいのイメージしかなかったんです。
僕らがいるこの経済区・国貿は、今と比べると全然違いました。こんなにビル群はありませんでしたし、CCTVのビルだってもちろん影も形もありませんでした。ただ、東三環道路と天安門広場へと続く片道8車線の長安街はできていて、国貿の交差点には高層オフィスビルが建っていて、既に都市の姿は現れていました。車もけっこう渋滞していて我先に行こうとする車のクラクションが鳴り響き、エネルギーが溢れ返っていました。僕が想像していた京劇のような優雅な時の流れとは違うものがそこにはありました。
BB:迫さんの会社が入っている、この建外SOHOのコンペのために東京から来たんですよね?
迫:そうです。
磯崎新さんと香港の建築家・ロッコーイム、僕のボスの山本さんが指名コンペに誘われていて、その内容を聞き取るというのが僕の役割でした。
後輩を連れてケリーセンター(注:シャングリラ系列の高級ホテル併設のオフィス棟)のオフィスのデザインされた受付に行くと、お約束通りに美人の受付嬢がいるんです。間もなく出てきたブラジル人の秘書が流暢な英語で僕に話しかけてきました。中に通されてから会ったベネズエラ人のアントニオというインハウスの建築家は、英語もスペイン語も中国語も話す。スタッフ全員が英語でコミュニケーションをとり、イングリッシュネームで「クリスティーナ」などと呼び合うわけです。
なんとなく「素朴な中国」というイメージをもっていた僕らは、まずそのインターナショナルな雰囲気に圧倒されました。日本のアトリエ事務所勤めの建築家のたまごが、そんな洗練された場で1人前の扱いを受けることなんて、それまで日本では経験がなかったんです。ケリーセンターの高層階に紛れ込んでいくのと同時にインターナショナルな雰囲気に迷い込んでいった、そんな感じでした。
そもそも、迫がボス・山本理顕から「北京に飛んで来い」と言われたのも唐突だった。山本は2000年9月、北京大学の招待で北京を訪れていた。東雲のSOHOプロジェクトについての山本の講演を聴衆として聴きに来ていたジャンシンは、その場で山本さんを食事に誘い「コンペに参加しませんか」と持ちかける。
当時ジャンシンは35歳。見た目より若く見えるチャンシンは、山本からすれば「よくわからない小娘」。翌日、もっと詳しい話をと自宅に招かれた山本は、すでにジャンシンが建てていた高層マンション最上階のペントハウスの自宅に招かれ、度肝を抜かれる。そして、ジャンシンから「70万平米のプロジェクトだ」と言われ、ようやくジャンシンの本気度を理解し、担当として迫を、急遽北京に呼んだのだった。
ビザの申請をしてようやく迫がやってきたのは、2000年の国慶節だったのだ。
BB:ジャンシンがはじめに言ったことを覚えていますか?
迫: 彼女が言ったのは、このSOHOプロジェクトでは本当にいいものをつくりたいということでした。中国はこれから生まれ変わろうとしていて、これまでは企業といえば国営ばかりだったけれど、これからはどんどんベンチャー企業が出てくるからSOHO(small office home office:職住接近)スタイルにはニーズがあるんだという彼女の言葉には説得力がありました。
BB:ジャンシンとのミーティングはどういうものだったんでしょう?
迫:ある時、風水についてのジャンシンの意見を聞こうとしたんです。僕たちは普段設計をする時に風水を取り入れることはありませんが、施主は中国人なので、一応考え方を聞いておこうとしたんです。するとジャンシンは「風水なんて言ってる!」と、笑い出したんです。その後真顔でこう言ったんです。「わたしたちは古い慣習にとらわれて建築をつくっているんじゃない。SOHOというライフスタイルをつくろうとしているんです」
山本さんが日本の公団と共同で東雲のプロジェクトを2003年に建てた時、当初山本さんが提案していたSOHOの本来の考え方に基づく提案は、今後働く場と生活の場を同じスペースでというライフスタイルはもっとニーズが出てくるはずだから、ゲストが空間に入るとすぐにワークスペースがあるような空間のとり方が必要だというものでした。でもその提案は当時の日本では斬新過ぎたのか、結局公団に受け入れられず、旧来型のマンションとそれほど違わないものになってしまっていました。
ジャンシンの言葉は、そのお蔵入りしたプランを北京で実現するチャンスが巡ってきたということでもあり、山本さんも僕も興奮しました。
実際、「建外SOHO」は、入居者のニーズ次第で居住空間としてもオフィスとしても商業空間としても使える「マルチスペース」という考え方を軸に完成しました。

(写真)建外SOHOは北京の経済地区・国貿エリアの新しい顔となった
BB:ジャンシンのどういう点に施主として魅力を感じるんですか。
迫:SOHO CHINAとジャンシンはまだ全国区の知名度はありませんでしたが、デザインが大好きだということはよくわかりました。完璧主義で短気。打ち合わせで素材や質感、コスト、耐久性にまで全部専門レベルで話ができる人なんて、ふつうディベロッパーの社長にはいません。建築の素人なのに、図面の意図を汲み取って打ち合わせができてしまう、それくらい建築とデザインが好きな人です。施主がそれくらいデザインにこだわりがあるということは、僕ら設計をする人間はうれしいに決まってます。
彼女は新しいものや未知のものに対して、それが不可能だとか、手に入らないとは全く思わない人なんです。その、何事にも限界をつくらない姿勢は、僕らつくる側を大いに刺激するわけです。
彼女の実行力のすごさといったら、「長城の別荘群」というプロジェクトでは、あらゆるコネクションをつかってアジアから選りすぐりの建築家を集めて別荘群を建てるという極めてアグレッシブな試みで、ベネチアビエンナーレの特別賞を受賞しているんです。
現代建築の世界において全くプレゼンスのなかった中国を一気に世界レベルにひきあげようとするパワーを僕は見習いたいと思いました。その後ジャンシンは「TIME」誌の「世界に影響力を与える女性100人」にも選ばれました。
彼女が北京に戻ってきた当時の中国には建築やデザインの動きはまだなかったといってもいいと思いますが、ジャンシンは中国にチャンスを感じ、自分が中国でデザインを切り拓いていこうとしていました。そのモチベーションを僕は中国で生きていく「手本」だと思いました。
中国有数のディベロッパーを率いる女性富豪となったジャンシンは、その魅力的な笑顔とカリスマ性もあいまって最も有名な女性経営者のひとりとして知られる。生まれは北京。文化大革命の影響を受けた幼少期のことは詳しく語られていないが、14歳の時には香港で女工をしていた。そこで同級生が成功しているのを聞き、自分も女工で終わりたくないと一念発起し、渡英。ケンブリッジ大学を卒業後、アメリカに渡りゴールドマンサックス等で働いたあと、95年に北京に戻り、SOHO Chinaのチェアマンでもある夫と同社を起業している。
BB:迫さんは4年でプロジェクトの3期が終了すると山本事務所を離れましたが、その後はジャンシンとどんなふうにつき合っているんでしょう。
迫:建外SOHO4期、三里屯SOHOオフィスタワーの内装やクラブハウスの内装などで声をかけてもらっています。
ぜひいつかは大きなプロジェクトをやりたいです。
SOHO CHINAほどに時代を引っ張っていく建築をプロデュースするという意欲にあふれたディベロッパーはほかにないんじゃないかと思います。それを端的に表しているのが2008年秋のリーマンショック後の売値への影響です。中国の最大手ディベロッパーでさえ価格を下げて対応していた時、SOHO CHINAのプロジェクト・三里屯SOHOはさらに価格を上げて発売し、もちろん完売しました。その理由は、プロジェクト数が他社に比べて多くなく、ひとつひとつのプロジェクトを展開していくことで、土地を抱える不安が少ないというのが第一。それに加えて、SOHO独自のデザインと品質へのこだわりに価値が認められていることを示しています。
デザインとつくることに手を抜かずにやり続けることは、建築を巡る環境が日本や先進国とは異なる面のある中国では非常に根気が要ることですが、それは経済価値上も正しいということを証明しているディベロッパーだといえます。
10年前、北京が都市として萌芽したあの時期にジャンシンが北京にいたということ、そしてジャンシンに巡り会ったということは、僕にとって大きな転換期となったのは確かです。(本文中敬称略)
2人め:ファン・ジェンニン(方振宁) アーティスト・美術評論家
「無名の若者を地方政府のプロジェクトに推薦。中国を拠点にするきっかけをくれた」
2000年、30歳で初めて中国に来た迫は、ボス・山本理顕が「建外SOHO」のコンペに勝つと、2002年からプロジェクトリーダーとして北京に赴任。建築に対する考え方も技術レベルも異なる現場で、施工会社のおやじ達とケンカ腰でやり合う毎日が始まる。日本ではあって当たり前な建材が中国にはないために話が通じない。そのため仕方なく建材の製造から自前で手配する。そんなことの繰り返しを延々続け、2004年、3期工事が終了。迫は、これを機に山本事務所を退職し、米国コロンビア大学の客員研究員として1年間の予定でNYに飛ぶばかりになっていた。現代建築の先進国であるアメリカへ行くことは、迫にとって念願だった。
そんな時、思いも寄らない話が降ってくる。浙江省金華市の政府庁舎の設計をしないかという話だった。日本の建築界では、公共施設のプロジェクトを手がけると一流建築家としてのステージに一歩近づくことができる、そして話が受けられるようになるのは早くても40代半ばというのが定説だ。
若干34歳の、まだ事務所も持たない迫に願ってもないチャンスを与えようという奇抜な発想をした中国人はーー。
BillionBeats(以下BB):34歳でNYに行くことは前から決めていたんですか?
迫:いいえ。現代建築に関わっていくために、山本事務所の次はアメリカの設計事務所を体験したいと思っていたんです。僕らのようなアトリエ設計事務所勤務の若いスタッフは、1カ所に留まらずいくつかの事務所を体験することも珍しくありませんし、30歳を過ぎればそろそろ独立も視野に入れるのも当たり前です。僕はアメリカの建築への憧れもあったので、スティーブン=ホールという世界的建築家のNYのアトリエに行きたいと思っていたんです。ところが、ボスの山本さんが、それより研究の立場になってみたらどうだとアドバイスをくれて、それで文化庁の制度にも応募して、2004年秋から1年間、コロンビア大学の客員研究員のポストを得ることができました。
BB:それなのに、同じタイミングで中国に事務所を設立したんですね?
2002年、僕は建外SOHOの現場の事務所に詰めていて、毎日ディベロッパーや施工会社、メーカーの人たちといった中国人の人たちを相手に毎日ケンカ腰で打ち合わせをしていました。「なんでできないのか」「なんでないのか」といったレベルのケンカです。今思えば、自分の価値観がひとつしかなかったのかとも思いますが、山本事務所としても海外のプロジェクトは初めてだったし、70万平米規模のプロジェクトなんて山本事務所だけでなく日本中のアトリエ事務所が受けたことのないスケールなので、初めて尽くしの現場でした。これを成功しないといけないという気持ちが強かったんですが、たとえば当時の中国には「バリアフリー」の概念がなかったので、それを実施するための材料も技術もないし、そもそも理解しようとしない。それに対して「絶対にやるんだ」という気持ちで毎日戦っていました。そこへ「現場を案内してほしい」と取材に来てくれたのが、ファンさんとの初めての出会いです。
ファン・ジェンニン氏は紫禁城で学芸員を務めた後、90年代にアーティストとして日本で10年間活動し、2002年に北京に戻る。北京を拠点に表現活動以外に現代美術や建築の分野の批評家としても優れた見識を持つ。キュレーターとしても活躍している。
迫:モデルルームと敷地を案内し、ファンさんに敷地全体の計画を説明したのを覚えています。後で本人から聞いたんですが「こんな若くて小柄な日本人が大変な中国人相手に現場を仕切ってるのか」と驚いたそうです。ファンさん自身は当時40代の前半だったと思います。それ以来、時々建築家の集まりなどで顔を合わせることはありましたが、特に深く話をする機会などはありませんでした。
ところが、2003年の年末に突然ファンさんから電話がかかってきたんです。
「辞めるって聞いたけど、いつ辞めるの?そのあとどうするの?」
といつもの早口で矢継ぎ早に聞かれました。その頃には、建外SOHOの三期工事が終わる2004年1月で山本事務所を辞めることについて山本さんの了承を得て、少しずつ周囲の人にも話し始めていたので、ファンさんの耳にも入ったようでした。僕のひと通りの説明を聞き終えると、ファンさんが「ひとつ紹介できる仕事があるよ」と言うんです。それが金華の交通局の1万3千平方のプロジェクトでした。
金華市が開発区をつくり市政府が移転してくるにあたり、交通局が一等地を押さえ、
ランドマークにふさわしい設計をしてくれる人を探すよう、ファンさんに依頼していました。ファンさんは「中国の実状を理解していて若くて実力のある条件で考えると迫が真っ先に浮かんだ」と言ってくれました。
BB:ファンさんはどうして迫さんを推薦したんでしょう?
迫:まず、スケールの大きい建外SOHOプロジェクトを、建築をつくるレベルもやり方も考え方も中国で、中国人と中国語で交渉しながら進めてきた推進力を評価してくれたんだと思います。金華市政府側は、その地方として初めて海外の建築家を起用することについて非常に期待感がありました。でも一方で、あまりにエラくなった建築家では地方の役人とぶつかってしまう心配もある。ということで、中国の事情を理解する若い実力のある建築家が必要だったんです。といっても、僕はまだアトリエ事務所のスタッフでしかなかったんですが。
先方からの条件は、外貨を送金するのは手続きが面倒だから中国に事務所を持っている建築家でなければならないということでした。こうして、ファンさんに導かれるように北京に事務所をつくったんです。

(写真)中国で事務所をつくることになるとは夢にも思わなかった迫。金華市のこのプロジェクトは「金華キューブキューブ」
BB:でもNY行きも決まっていたんですよね?
迫:そうです。ただ、NYに行くからってこれを諦める理由もないわけで(笑)。両方やれると僕は思いました。金華のプロジェクトは1万3千平米で、それだって決して小さくはありませんが、それまでやってきた建外SOHOは70万平米でしたから、NYからでもコントロールできないスケール感ではなかったんです。
また、僕としては、せっかくアメリカに行くために準備もしてきたのにという気持ちもありました。当時の僕は「現代建築の主流は欧米」という考えだったので、中国でキャリアをスタートすることには不安がありました。こんなに中国べったりになってしまって建築設計のメインストリームから離れていくんじゃないかという怖さがあったんです。
だけど、無名の僕が公共建築を建てるチャンスがいきなり巡ってきたという幸運をみすみす手放すのはあまりにもったいないという気持ちもあって、結局そちらが勝ったということです。
結局、NYに行っている間も2週間ごとに北京に通っていました。
BB:NYと往復、ですか?
迫:ええ。秋からNYに行くことになっていたので、その前に北京で事務所を設立し、スタッフを3人確保してから出発しました。ひとりは、日本の大学の建築学科を卒業したばかりの女子でした。彼女は現在も事務所の主力として働いています。
NYと北京を2週間ごとに往復する生活を1年続けました。時差がちょうど12時間なので、NYの夜中に北京に電話やビデオチャットで指示をしていました。インターネットが普及したおかげで、やることができたんです。
ファン氏は、2000年に入って中国で世界的な建築家たちによる建築ラッシュが起きる前から、数多くの海外の著名な現代建築家を中国に紹介してきている。CCTVの設計をしたオランダのレム=コールハースも、中国で作品紹介と批評をさきがけて手がけたのはファン氏だ。批評家としてのファン氏は極めて率直。いいと思ったら「すごくいい!」と言い、ピンとこないと反応しない人だという。
迫:ファンさんは全くウソがつけない人です。でもその建築や芸術への敬愛はとても純粋なんです。だから好き嫌いやいいもの悪いものへの見方がとてもはっきりして、とにかく本音で批評してくれます。
作品についてはもちろんですが、中国での仕事の仕方も「迫はわかってない」と辛辣に指摘されたこともあります。たとえば、施主へのプレゼンでは最初にインパクトを打ち出すことが重要だというのを教えてくれたのはファンさんです。「日本の奥ゆかしさの美学を持ち込んでも中国では理解されない」と教えられました。
中国でのメディア露出を力強くサポートしてくれたのもファンさんです。僕らはコネも予算もなく、受注のための営業スタッフなどいません。だいたい、アトリエ系の建築事務所は営業という概念があまりないのです。でも中国で、仕事をとっていかなくてはならないという時、メディアは僕がどういう建築家で何を目指しているのかを伝える貴重なツールです。建築やインテリア、アートの雑誌での取材が増えたのもファンさんの協力が大きいんです。
四川のボランティア(BB注:四川省幼稚園寄贈プロジェクト)を始めようと思った時も、最初に僕はファンさんに相談しました。ファンさんは、四川の有名な建築家に連絡して、すぐに一緒に会いに行ってくれました。
そう、2005年にはファンさんと二人で約10日間かけてアメリカを旅しました。NYからLAまでアメリカ大陸を西へ横断しながら世界的な建築を見て回る旅です。
BB:中国で出会った中国人と一緒にアメリカの建築を見る旅をするという時間の共有もおもしろいですね。

(写真)ファンさんを助手席に乗せて、レンタカーで砂漠の一本道を突っ走った
迫:テキサス州マーファというところにミニマルアートの聖地と呼ばれている建築やデザインに携わる人にとって巡礼の地のような場所があるんです。最寄りの空港から300キロ離れているそこまで、テキサスの荒野の1本道をレンタカーで時速100マイルでぶっ飛ばしました。壮大な大地と空に抱かれ、静かに、しかし力強く存在するドナルド・ジャッドの作品を目の前に、ファンさんと僕はただ言葉を失って立ち尽くすばかりでした。クリエイターとして一生心に刻まれる瞬間を、ファンさんと二人で共有したんです。
建築の世界のスケール感や目指すべき高い地点はどこにあるのかといった認識を共有できるファンさんのような人が中国にいるということも、僕が中国で建築をやり続けることを後押ししてくれているのかもしれません。(本文中敬称略)
3人め:ソンチー(孫池) 書店「光合作用」店主
「子どものような存在の店の再生に、デザインの力を信じる」
2004年に北京に事務所を開いてから、迫の事務所では300平米規模のスマートシティからブティックのインテリアデザインまで、70以上のプロジェクトをつくってきた。そのうち、インテリアデザインは37。2004年から7年連続でJCDデザインアワードに入賞するなど、実はインテリアデザインの評価も高い。
建築とインテリアデザインという対照的なスケールのふたつのクリエイティブ。迫のインテリアデザインは、多彩な色や素材とともに雄弁に語りかけてくる。子どものための虹色の書店、白色の網の目を張り巡らした有機的なブティックなど、時にユーモラスな、時にミステリアスな空間。見る人に、きっと迫は楽しんでアイデアを練っているのだろうと思わせる。
今回は、インテリアデザインを迫に発注した中国人の施主との出会いを語る。
BB:最終回はインテリアデザインを手がけた時の施主のお話ですね。
迫:ソンチーは「光合作用」という書店のオーナーです。この書店は彼女が30歳くらいの時にスタートし、現在は北京にも10店舗近く展開していますが、アート関連や小説など、「光合作用」独自の視点で選ばれた本がデザインされた空間に並ぶ、いわば本のセレクトショップのような、一般の書店とは違うスタンスの展開をしてきた書店です。
その「光合作用」の本店のリニューアル(のほうが一般的では?)をすると決めた時、彼女は北京の僕の事務所に訪ねてきたんです。2010年の夏です。
本好きのための空間として既に特長のある店づくりを展開してきた「光合作用」が本店をさらにリニュアルすると決め、僕を指名したいというので、彼女の僕のデザインへの期待値の高さは話しぶりからもすぐに伝わってきました。
ソンチーはおそらく40代半ばだと思いますが、いかにも文学少女がそのまま大人になったような雰囲気の女性です。彼女は、これまで一軒一軒の店を自分の分身のような気持ちで大事に育ててきたと切々と話し始めました。中国の都市部にはデパートのような大書店がいくつもありますが、彼女がオーナーとして10数年経営してきた「光合作用」では、本のセレクト、インテリアデザインなどを自分たちで工夫を重ねながらやってきた、その目的は、素晴らしい書籍と心地よい空間を読者という本好きの人たちに提供することだったと彼女は言いました。中国語では本を読むことを「閲読」と言いますが、彼女は「悦読」という言葉を使う、それほど本を読むことの喜びと素晴らしさを書店を通して伝えたいという思いに溢れた人です。
僕は映画「You’ve got mail」を思い出しました。ニューヨークの大手書店の経営者と街の小さな本屋さんの経営者がお互い反目し合っているにも関わらず、メール上のやり取りで書店づくりにかける思いにおいて意気投合するという話ですが、彼女の書店は街の本屋さんなんです。
「光合作用」は、北京市内でも清華大学の近くや高級百貨店、ショッピングモールなど、15店近くを展開する。ゆったりとした空間には本が空間の余白を生かして配置され、本そのものの美しさも楽しむことができるような店づくりが印象的な書店である。中国では、大型書店が経営難で閉店したという話を聞く一方、「光合作用」のような個性的な書店が支持されるという現象が起きている。
BB:中国で本のセレクトショップを10数年前から展開してきたこと自体、驚きです。
迫:これまでは店のインテリアなども自分たちがやってきたけれど、ここでもっと高いレベルに持っていきたいという説明のあと、彼女はこう言ったんです。「自分の育ててきた子どもを託す気持ちでデザイナーを探した。そしてあなたに頼みたい」
BB:設計者冥利に尽きる言葉ですね。
迫:そういう施主のために仕事をする時、僕らのモチベーションはすごく高くなります。ディベロッパーの建築とのスタンスは、つくったものが売れたら終わりですが、書店オーナーの場合、空間ができあがった時が長いつき合いの始まりなんですね。僕に託して新しく生まれ変わった空間が、そこにすてきな本が常に入れ替わりながら本好きに愛される豊かな空間に育っていき、結果として書店のブランドも売上げも上がる、そのゴールまでの過程まで含めて、僕はデザイナーとして責任を持つことになるわけです。
設計して終わりではなく、設計した空間を一緒に育てていく感覚を持つことができることに喜びを感じました。
BB:デザインへの具体的な注文はあったんでしょうか。
迫:あったといえばひとつだけ、「一切を新しく。これまでの雰囲気はひきずらなくていい」。それと「社名は変えない」。というのも、空間デザインだけでなく、書店のロゴサイン、書棚のサイン、コーヒーコーナーのカップ、紙袋まで一切のコミュニケーションツールのデザインを依頼されたんです。
僕は、彼女がこれだけは変えないと言った「光合作用」をそのままデザインに翻訳すればいいと考えました。空間デザインもそうですが、光合成に必要な水と光を、「地球」(アポロン)と「太陽」(ポセイドン)の化身というふうに捉え、「APODON」という新たなキャラクターもつくりました。

(写真)「光合作用」という名前をデザインで表現することを考えた
その後、プレゼンと打ち合わせが何度も繰り返された。そして2ヶ月半の施工期間、担当スタッフがアモイの現場に常駐して作業を続けた。
BB:完成した「アポドン」への施主の反応はどうだったんでしょう。

(写真)初日を祝うゲストが詰めかけたオープン当日、笑顔のふたり
迫:いくら僕に任せたといっても彼女も相当気持ちは揺れたはずです。
そのうえ、中国の建築の現場では珍しいことではありませんが、コストはオーバーするし、納期は遅れるし、しかも、工事の途中は仕上がりの予想がつきませんので、どんどん不安になるわけです。何度も送られてくる仕上がりを心配するメールから、彼女の胸の内は手に取るようにわかりました。ようやくできあがったのはオープンの12月5日の前日でした。
明け方の3時、彼女からショートメールが届きました。そこにはこう書かれていました。
「世界中の書店の未来は明日終わりを告げます。わたしがつくりたかったこの空間が世の中に生まれたことによって、すべての書店を圧倒する世界にただひとつの空間が誕生します」
僕はオープン当日にそのリニュアルした書店で「中国のブランド空間」というテーマで講演をすることになっていました。アモイの空港に出迎えにきていた車に乗り込んで、オープン直前の「光合作用」に到着すると店の前には孫が待っていました。車から降りた僕の顔を見るとそれだけで感極まった孫と僕は何も言わずにハグしました。お互いが自然とハグするような気持ちになることはあまりないことです。
BB:デザイナーとしての迫さんにとって、このプロジェクトはどういう意味を持ったんでしょう。
自分たちが育ててきたブランドを高いレベルに持っていきたいというこの施主との出会いによってデザインの使命感を改めて認識しました。
「光合作用」の施主と僕との間にデザインを媒介として深く結びつき合う関係が成立したように、中国にはここでやっているからこその空間をデザインするということの大事さや喜びがあります。施主のデザインへの期待やリスペクト、祈りのような思いを引き受けて一緒に空間をつくっていくことの達成感が、中国の現場にはあるんです。
そういう施主とデザイナーの間に生まれる志を共にするような関係性が中国のクリエイティブの現場にあることが、日本では伝わっていないことは少し残念です。
バブル景気の勢いに乗って経済性を生み出すための建築が猛スピードで製造されているという中国市場のイメージとは異なる、中国ならではのものづくりの現場にいて、そこで中国人と互いに尊敬し、信頼し、より優れたデザインを生み出す行為に関わっていることは、僕の誇りです。(本文中敬称略)

連載一覧
-
Vol.1 建築家(北京和僑会副会長) SAKO建築設計工社代表取締役 迫慶一郎 (41)
1人め:ジャンシン(张欣) ディベロッパー・SOH…
-
Vol.2 美容サロン経営(北京和僑会理事)北京朝倉時尚形象設計有限会社C.O.O・ディレクター 朝倉禅(34)
1人め:ウホイウェン 吴恵文(ファッション誌『昕微…
-
Vol.3 テニススクール経営(北京和僑会会員)レインボーテニスガーデン代表 藤本龍一郎氏(27)
1人め: イエンダミン 厳大●(左:石、右:名)(…
-
Vol.4 日本料理店経営(北京和僑会理事)北京市有薫一心餐飲有限公司総経理 高山貴次氏(34)
1人め:ヤンジュン 閻郡(42) 「これぞ中国」…
-
Vol.5 リサーチ会社経営・安田玲美(北京和僑会理事) ー 北京世研伝媒広告有限公司・北京世研信息諮訽有限公司・等、CRCグループ10社およびエンジェルエンジェル服装服飾有限公司の総経理
(写真)安田 玲美 <プロフィール> やすだ なる…

投稿者
三宅 玲子
ノンフィクションライター。
週刊誌で人物ルポやひとと世の中を取材・執筆。
2009年~2014年まで北京。
現在は東京、ときどき北京。
建築家・迫慶一郎氏と所員たちの10年の軌跡を追いかけたノンフィクションを書き下ろし中。
BillionBeats2011年開始の発起人。
BBウェブサイトの編集および、
立体プロジェクトでは日本側のコーディネートを主に担当。
- Categories: ビジネス