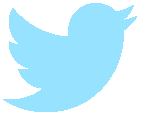冬天

第3回/冬天
僕は授業料を支払い北京電影学院の中国語クラスに入った。受講者のレベルに合わせて初級、中級、上級のコースがあり、さらにそれぞれ上下2つに分かれる。つまり全部で6クラス。僕は初級の上に入った。先生からは一番初歩の初級の下から始めるようにと言われたが、初日に授業に出てみると漢字の「一、二…」からやるようなので、付き合い切れないと思い替えてもらった。北京では多くの大学が留学生用の語学クラスを開設している。だから電影学院は主に映画を学ぶ大学ではあるが、中国語クラスは当たり前だがあくまでも中国語を学ぶ場であり、映画と関係があるわけではない。もっとも留学生の多くは語学習得後の本科への進学を目指していて、彼らは必然的に電影学院で中国語を学ぶことになる。在籍する学生は様々な国から来ていたが、南米、中央アジア、アフリカからの学生が多いのに驚いた。おそらく中国政府の取る政策とリンクしているのだろう。ちょうど中国政府が第三世界の国々との関係を強化発展させようとしている頃だった。中国政府は留学生の招聘のために奨学金に多額の予算を割いている。出国前、テレビで北京オリンピックの開会式を観て、僕はある感銘を受けた。それは中国の文化と歴史のショーケースのような開会式だった。中国は本気で中国文化を世界のスタンダードにしようとしてるのではないか、と僕は思ったのだ。「本気で」というのが重要な点だ。オリンピックといえば、僕が北京に来たばかりの9月はパラリンピックが開催中で、僕はU君らといくつかの競技を観に行った。盲人サッカーはボールの中に鈴が入っていて、選手はその音を頼りにボールの位置を知る。だからボールが動いている間はいいのだが、止まってしまうと選手達はフィールド内をうろうろとさ迷うことになる。選手にしてみればなにしろ4年に1度のオリンピックだ。必死にうろうろする。その様子に多くの観客がゲラゲラ笑う。モダンな競技場の客席で、僕は改めて中国に来たんだなと実感した。
中国語を学び始めて疑問に感じたのは、同じ文字を使う言葉なのにどうしてこうも日本語と違うのだろうということだ。文字以前に人も多く渡って来たはずなのに、日本語の文法の中に中国語の影響がまるで感じられない。ところがいくつかの単語を覚え、簡単な句を喋るようになると、感覚的には日本語と同じようにダラダラとだらしなく使える言葉なのではないかと思うようになった。ひとつひとつの漢字が持つ寛容さのせいだろうか、などと考えてみても学のない僕にはわからない。面白いことに、留学生同士の共通語はカタコトの中国語だ。皆、僕より一回り以上も若い学生ばかりで、覚えが早い。もちろん局面によっては英語も使われる。授業は昼までで、僕はイスラエル人とウズベキスタン人の学生とランチをとることが多かった。二人とも女性で、僕らは授業の休み時間に喫煙所に集う喫煙仲間だった。今、彼女たちがどうしてるのか僕は知らない。ある日「新進気鋭の女性監督登場!」みたいな記事を雑誌かなにかで見ないかな、なんて空想してみたりする。
北京の秋は短い。夏が終わるといきなり冬が来る感じ。学生気分が嫌になり、僕は寮を出て旧市街地の胡同に面したアパートに部屋を借りた。赤いレンガ造りの6階建てのアパートは社会主義時代の名残だ。もっとも今だって建前上は社会主義なのだけれど。大家さんは出版社に勤めるおばさんで、以前は仕事も住宅も国家から与えられた。自分の部屋を他人に貸して家賃を取り、大家さん一家は郊外のマンションに住んでいる。中国の法律では6階建てより低層の建物にはエレベーターを付けることができない。幸い僕の部屋は1階で、小さな庭があり、ザクロの木が1本植えられていた。貧相な木だったが、夏の終わりに痛々しいほどたわわに実を付ける。北京の冬は厳しく、僕は部屋にこもって脚本を書き始めた。
「くよくよクラブ」は北京を舞台にした4人の女の子の物語だ。新しい環境に身を置くと、初めのうちは違和感ばかりが気になるものだが、慣れて行くに連れ、今度はやって来た場所との共通点に目がいくようになるのかもしれない。北京の若者はナイーブで傷つきやすく抑圧されているようだった。東京の若者によく似てると僕は思った。急激に変化する社会状況と中国古来の伝統的な価値観との狭間で北京の若者は喘いでいた。僕はそれを書いてみようと思ったのだ。ひょんなことから知り合った4人の女の子たちにはそれぞれ北京で叶えたい夢があり、挫折を味わいながら友情を育み人間的に成長していく、そんなような物語だ。もともと僕は中国で小さなインディペンデント映画が撮れればと考えていたのだが、これは商業映画用の脚本だった。僕は気が変わっていた。以前はただ漠然とした数字であった13億という人口が、実感として迫ってくるようになったからだ。これはとんでもないことだ、と気づいた僕は、13億人に向けて映画を作ってみたくなっていた。
ある朝、近所に爆音が轟いた。間もなく春節がやってくる。僕は春節を知らなかった。戦争が始まったかのような爆竹と花火の轟音を聞きながら、北京の冬、僕は孤独だった。
投稿者について
Hiroshi Okuhara: 映画監督 1968年生まれ。『ピクニック』がPFFアワード1993で観客賞とキャスティング賞を、『砂漠の民カザック』がPFFアワード1994で録音賞を受賞。99年に製作された『タイムレス・メロディ』では釜山国際映画祭グランプリを受賞した。その後『波』(01)でロッテルダム国際映画祭NetPac Awarを受賞するなど、高い評価を受ける。その他の作品に『青い車』(04)、『16[jyu-roku]』(07)がある。本作品は、5本目の長編劇場作品に当たる。
- 初到北京 / 0 Comments
- 宋庄 / 0 Comments
- 冬天 / 0 Comments
- 地下電影 / 0 Comments
- 回国 / 0 Comments