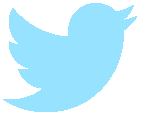回国

第5回/回国
林家威の撮影が終わり、僕は瀋陽に旅立った。7月、先に旅に出ていたU君と合流し、二人で遼寧半島を廻った。U君は犬好きで、中国の犬食文化に強い拒絶感を持っていた。けれどもそこは朝鮮族が多く暮らす土地。いたるところで犬料理屋の看板が自然と目に入ってくる。愛くるしいコリー犬の顔を描いた馬鹿でかい看板を掲げる犬料理屋があった。さすがに理解に苦しむ。でも考えてみれば、日本にだってかわいらしい豚のイラストをキャラクターに使用するトンカツ屋がある。敬虔なイスラム教徒が見たら卒倒するかもしれない。要は習慣の問題だ。
8月。僕は日本に帰国した。文化庁の研修期間は1年間。厳密に言うと350日間で、終了後には必ず一旦帰国する決まりになっていた。当時、自分が何を考えて生きていたのか今ではよく覚えていない。けれどもすぐにまた北京に戻るつもりではいたようだ。というのも借りていたアパートの部屋をそのままにしてたから。1年ぶりの東京で、電車に乗り、僕はたじろいだ。北京の地下鉄の車内とはまったく様相が違う。しんと静まり返っていて、乗客の多くが携帯電話の画面を見つめてる。車内に妙な緊張感がある。日本ではあらゆる公共の場所で小さな社会が瞬時に形成される。従うべき暗黙のルールが空間を支配する。「空気を読めよ」みたいなことをすぐ言う人が僕は苦手だ。「空気」は僕の知らないうちにどんどん複雑になっていくので、なかなか適応が難しい。この傾向はこの数年、さらに強まっているように思う。これも震災の影響だろうか。とはいえ僕もやはり日本人。「空気を読む」習慣も文化もない中国にいると、ストレスを感じてしまうこともある。
東京にいた僕に北京の友達からメールが届いた。張次禹だ。張次禹は当時北京電影学院の大学院生で、U君のクラスメートだった。U君を通じて僕は彼と友達になった。彼は地元の湖南省の大学で美術講師をしていたのだが、どうしても映画が撮りたくて、退職し、手を尽くして電影学院に入学した。電影学院は志望して簡単に入れる学校ではないらしい。それでも電影学院には彼のように一度社会に出てから入学し直す学生が少なくない。彼と出会ってすぐの頃、映画を撮る時には手伝って欲しいと彼に言われ、僕は気軽に「いいよ」と答えた。僕は彼の言葉をまったく真に受けていなかった。彼のように言ってくる人は時々いるが、本当に撮る人はほとんどいない。それに彼が在籍していたのはニューメディア・アート科だった。専攻は何でも構わないからとにかく電影学院に入りさえすればよかったのだと彼は言った。映画を撮る仲間が欲しかったのだ。そして彼が目を付けたのがなぜか僕だった。
張次禹のメールには8月の末から映画を撮るから手伝ってくれと書いてあった。悪いけど行けそうにもないと僕は返信した。秋から妻も一緒に北京で暮らすことになり、東京に借りていた部屋を引き払わなければならなかった。長年溜め込んだ荷物を処分するのは容易でない。それに彼女は小さな飲食店を経営していたので、それも畳まなければならなかった。そうした事情を彼に説明すると、すぐにメールが返ってきた。「ならばいつなら来れるのか。お前の都合に合わせて撮り始める」と書いてあった。さすがに手伝うと言ってしまった手前、そこまで言われれば行くしかない。9月に入り、僕は撮影場所の湖南省に向かった。結局、引っ越しも閉店後の片付けもすべてすっぽかしてしまった。そのことで僕はいまだに妻から恨まれているのだが、それはまた別の話。
80年代の終わりの頃、「芙蓉鎮」という中国映画があった。若き日の姜文と劉暁慶が主役の夫婦を演じ、日本でも公開されているのでご覧になった方も多いかと思う。「芙蓉鎮」のロケ地となった同じ村で、張次禹の映画も多くのシーンが撮影された。元は別の名前の村だったが、映画がヒットし、村は芙蓉鎮と名を変えた。湖南省張家界の空港で張次禹と再会し、彼の運転する車で芙蓉鎮に向かった。道中の数時間、彼はずっと喋りっぱなしだった。彼の話は難しく、僕はまったく理解できない。何度も彼にそう言うのだが、彼はまるで意に介さない。これは多くの中国人にしばしば見られる不思議な現象だ。相手が理解していようといまいと、彼らは構わず延々と喋り続ける。それでいいのだと張次禹は言った。僕が理解するしないはどうでもよくて、話す行為そのものが重要なのだ。確かに話すことで考えは整理されていく。これは中国人のプラグマティズムだ。
車はクラクションを鳴らしながらいくつもの山を越えて行く。険しいカーブを躊躇うことなくインコースに突っ込んで走る。僕がこれまでの人生で聞いたクラクションの総量をこの数時間だけで超えたのではなかろうか。道路の傍らに転がって錆び付いた車を何台も見た。けれどもなぜか僕の心はどんどん軽くなっていく。どこか投げやりな夏の終わりの陽射しのせいかもしれない。開け放った窓から乾いた風が吹き込んでくる。何かとても楽しいことがありそうだ。撮影がいつまで続くのか僕は知らない。張次禹に聞いても終わるまでだと言うだけだ。彼自身にもわかってない。無計画の成り行き任せ。それは僕の好むところだ。張次禹が僕に目を付けたのも、案外そんな性分が合っていたからなのかもしれない。
投稿者について
Hiroshi Okuhara: 映画監督 1968年生まれ。『ピクニック』がPFFアワード1993で観客賞とキャスティング賞を、『砂漠の民カザック』がPFFアワード1994で録音賞を受賞。99年に製作された『タイムレス・メロディ』では釜山国際映画祭グランプリを受賞した。その後『波』(01)でロッテルダム国際映画祭NetPac Awarを受賞するなど、高い評価を受ける。その他の作品に『青い車』(04)、『16[jyu-roku]』(07)がある。本作品は、5本目の長編劇場作品に当たる。
- 初到北京 / 0 Comments
- 宋庄 / 0 Comments
- 冬天 / 0 Comments
- 地下電影 / 0 Comments
- 回国 / 0 Comments