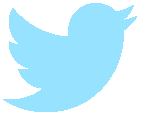梨

第6回/梨
芙蓉鎮は湖南省の北西に位置し、この一帯には苗族と土家族が多く暮らしている。張次禹は苗族で彼の身分証にもそう記されているが、本人曰く苗族は偽りで本当は漢族なのだという。中国政府は少数民族出身者に対して様々な優遇措置を採っている。二人目の子供を持つことも出来るし、大学入試試験の点数がかさ上げされたりもするようだ。張次禹の戸籍が苗族として登録されているのも、それらの恩恵を考慮に入れてのことかと思う。聞いた話では、文革が終わり中国が改革開放路線を歩み始めた頃、少数民族に関する法律が定められ、国民が出自の民族を自由に選択してよい時期があったのだという。確かめてないので真偽のほどは知らないが、本当であれば実に乱暴な話だ。しかし一方、民族というものの斬新な捉え方だとも思う。いずれにせよ中国ならではのやり方だ。
本文に付載されている写真を見ていただきたい。張次禹の映画「梨」の撮影開始を記念して撮ったものだ。いつ誰がなぜこんな幕を用意したのだろうと思っていたら、幕の右下に寄贈者の名前が入っていた。写真右端にピンク色の立て看板があるが、これを制作した地元の広告会社がわざわざ作ってくれたようだ。看板は美術道具としてこの会社に注文した。写っているのは全部で11名。中央の帽子をかぶっているのが監督の張次禹。その後ろの女性は張次禹と同期の電影学院大学院生で、その横に僕が写っている。メインスタッフはこの3人。あとは役者が4人と手伝いのスタッフが3人。背後の建物はロケ場所となった旅館で、左端に旅館の主人が写っている。旅館は我々一同の宿にもなった。これだけの陣営で映画を撮るのは決して不可能ではないが、それなりに大変だ。なにしろ映画撮影の経験があるのが僕だけなのだ。今、この写真を改めて見るとなんだか感慨深いものがある。あれからもう5年近くが経った。
ピンク色の看板は売春宿の看板で、空いていた旅館の1階の店舗スペースを飾りつけ、売春宿を作り上げた。主人公の若い男の妻が売春宿で働いている設定で、ここが物語の主要な舞台となる。主人公は客を取る妻を横目にここでやるせない時間を過ごすのだ。この一帯に限らず、僕が撮影で訪れた湖南省の街にはこの手の店は多かった。最近この旅館の1階は本当に売春宿として営業を始め、なかなか賑わっているという。去年の夏に僕がこの地方で一番大きな吉首の街を再訪したら、かつて通りにひしめいていた売春宿が一掃されていた。街の風紀規制が厳しくなり、吉首の売春業者の多くが近郊の田舎の小さな街に移動したのだそうだ。ロケ場所の旅館の1階が売春宿になったのもその辺の事情と関係があるのだろう。撮影前の準備期間、僕は張次禹に連れられて、辺りの売春宿をいくつか覗いて回った。不埒な奴だと思わないで欲しい。見学のためだ。僕は照明機材を作る必要があった。
撮影はデジタル・カメラで行うので、あれはRECボタンを押せばまあ写る。カメラは張次禹がかつて美術教師をやっていた吉首大学で借りた。昼間の外ロケばかりの撮影であればいいのだが、室内や夜撮ではどうしてもライトが必要で、こればかりは知った人間がやらないとうまくいかない。僕だって専門的に映画の照明を担当したことはないけれど、どんな場面でどんな光を作ればいいのかは経験的に知っている。それに僕は小さな自主映画の撮影現場で照明を作るのが好きだった。映画撮影用の照明機材屋など限られた大都市でしか見つけられないし、そもそも機材を借りる金もなかったので、それで僕は吉首の街で必要な部品を大量に買い込んで自作した。さすがに機材作りからやるのは初めてだったが、その分楽しみもあった。シーンによってはやり足りなさは残ったものの、ライティングは概ね狙い通りにうまくいった。こんな撮影でなければ経験できない満足感だ。
初めて映画を撮る張次禹は、あらゆる場面で僕に意見を求めてきた。僕は「自分の好きにすればいい」としか答えない。これは彼の作品で僕のものではないのだし、僕が意見を言って彼が考えを変えてしまえば撮る意味がない。撮影は遅々として進まず、あまりの効率の悪さに僕は我慢ができなくなり、苛つきを態度に出してしまうこともしばしばあった。でもそんな気持ちもご飯を食べればすぐに忘れることができる。食事は近所の食堂から届けられた。大きな洗面器のような器に様々なおかずが放り込まれていて、それを白米の盛られた丼を手に皆で囲んで食べるのだ。本場の湖南家庭料理は北京で食べていたのもよりワイルドで、何を食べても本当においしい。撮影の日々を暮らしながら、僕はかつての自分を思い出していた。大げさに聞こえるかもしれないが、張次禹は人生を賭けて撮っている。極めて非合理的な撮影も、僕だって初めて映画を撮った時はそうだった。何も知らずにただがむしゃらに撮っていた。効率よくやろうなんてハナから考えてなかったし、そういう考え方そのものを若い僕は馬鹿にしていた。すべての撮影が終了し、その夜、皆で酒を飲んだ。張次禹は心底解放されたようで、普段はあまり酒量の多くない彼が、この夜ばかりは飲みに飲んだ。張次禹陽気に酔いつぶれ、僕は彼を背負って宿に帰った。この撮影に参加して本当によかったと、しみじみ僕は思った。
中国には恩を恩で返す習慣が根強くある。「黒四角」は張次禹の助けなしには成り立たなかったことだろう。おまけに出演までしてくれた。起業家を目指して投資を募る男の役だ。張次禹のユニークなキャラクターがそのまま役になっていて、実に味のあるいい演技をしてくれた。ぜひとも劇場で確かめていただきたい。「梨」は素敵な作品に仕上がった。国外の様々な映画祭に招待され、大阪の映画祭でも上映された。張次禹はその後、電影学院を卒業し、今は北京の中央民族大学で教鞭をとっている。そして現在、やはり地元の湖南省で、第2作目の映画を撮っているところだ。残念ながらスケジュールの都合で僕は参加していない。もうすぐ北京に戻って来るはずなので、撮影の話を聞くのが楽しみだ。
投稿者について
Hiroshi Okuhara: 映画監督 1968年生まれ。『ピクニック』がPFFアワード1993で観客賞とキャスティング賞を、『砂漠の民カザック』がPFFアワード1994で録音賞を受賞。99年に製作された『タイムレス・メロディ』では釜山国際映画祭グランプリを受賞した。その後『波』(01)でロッテルダム国際映画祭NetPac Awarを受賞するなど、高い評価を受ける。その他の作品に『青い車』(04)、『16[jyu-roku]』(07)がある。本作品は、5本目の長編劇場作品に当たる。
- 初到北京 / 0 Comments
- 宋庄 / 0 Comments
- 冬天 / 0 Comments
- 地下電影 / 0 Comments
- 回国 / 0 Comments