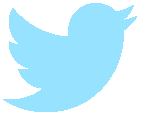地下電影

第4回/地下電影
旧暦、中国では農暦というが、太陰暦なので春節(日本の旧正月)の始まる時期は現行の暦に照らせば毎年違う。日本では正月に年賀状に「初春」と書いたりするが、これがなかなかピンとこない。正月が明けても寒さの緩む気配は一向に感じられず、「春」のイメージとは程遠い。ところが北京では春節が明けるとそれから日に日に暖かくなっていく。「初春」の由縁はこれだったのか、と北京で暮らすようになって僕は腑に落ちた。農暦と呼ぶのも然り。
北京電影学院は立派な映画館を備えていて、ここでは週に2日、2本立てで映画を観ることができる。国産映画の日と外国映画の日に分かれていて、2ヶ月遅れくらいで封切り映画が上映される。チケットの値段が他の映画館と比べて格安なのが嬉しいのだが、その分入手が難しい。学期の始まる前に通し券を購入することを覚えてから、僕は毎週映画を観に通うようになった。ただし観れる映画はハリウッド映画か国内の商業映画に限られ、インディペンデント映画、中国で言うところの地下映画が上映されることはない。電影学院だけでなく、それは国内のどの映画館でも同じ。ここには中国特有の映画にまつわる事情がある。地下映画は海賊版DVDやインターネットで観ることはできるのだが、やはり映画はスクリーンで観たい。というわけで、春になり、僕は映画を観に香港に行った。3月末から香港国際映画祭が開かれる。
数年前、僕の監督した「青い車」が香港国際映画祭に出品されたとき、劇場で質疑応答の通訳をしてくれたのが林家威だ。香港から戻ると、僕は北京で林家威と再会した。彼は処女長編映画の製作準備に入っていた。東京で交通調査員のバイトに励み、貯めた金をつぎ込んで撮影するという。彼はマレーシア出身で、日本語を自在に操る。僕は彼に頼んで撮影現場にスタッフとして参加させてもらうことにした。北京の自主制作映画の撮影現場が見たかった。
基本的にはやることは世界共通。役者、スタッフに指示を出し、カメラを据えて撮影する。日本だから中国だからという差異はない。ないはずなのだが何かが違う。予算規模に見合わぬスタッフの多さ。これは日本と違う。荷物持ちのようなポジションのスタッフが2人いて、彼らはどう見てもまだ子供だ。せいぜい15、6歳くらいといったところ。撮影は当然、無許可のゲリラ撮影だ。これは日本の自主制作映画でも同じ。電車の中の撮影があった。中国の電車のあり方は日本のそれとは大きく違う。中国の電車はすべて寝台車両を備えた長距離列車だ。カメラを担いで車両に乗り込む。僕も日本で経験がある。寝台車両の通路に三脚を立て、撮影開始。僕は「ん?」と思う。乗務員が通りかかった。広げた三脚を閉じ、通してやる。乗務員はそのまま通り過ぎて行く。周りの乗客たちも我々に注意を払う者は誰もいない。大きなワゴンを押した弁当売りの少女が通りかかる。監督が彼女を呼び止める。彼女の佇まいが気に入ったようだ。「ちょっとその椅子に座っててもらえる?」。頼むと、彼女は黙って言われた通りにただ座る。撮影再開。撮影終了。「はい、ありがとう」。彼女は立ち上がり、何事もなかったようにワゴンを押して去って行く。これは日本ではあり得ない。こんな自由な撮影が中国では許されるのか。僕は感動し、嬉しくなった。それから約3年後、僕は「黒四角」を撮影するのだが、3年で事情は大きく変わってしまっていた。北京は猛スピードで成熟した都市へと変貌を遂げつつある。80年代の思春期、90〜00年代の青年期を経て、北京は大人になってしまった。もはや無軌道な振る舞いは許されない。仕方がないのは分かっているが、なんだかすごく淋しい。
クランク・アップは2009年6月4日。日付を覚えているのは、ちょうど20年前のその日に天安門事件が起こったから。ロウ・イエという中国の監督に「頤和園」(邦題「天安門、恋人たち」)という作品がある。東京で僕は公開時に観に行った。中国では発禁の大問題作というような触れ込みだったが、僕は拍子抜けした。事件の描写があるにはあるが、作品としては普通の青春恋愛映画のようにみえたからだ。しかし、その後、中国に来てからこの作品を撮った監督の勇気に敬意を持つようになった。未だ事件は中国国内ではタブー中のタブーで、相当の覚悟がなければとても扱える題材ではない。そういう社会に身を置いてみなければ分からない事はたくさんある。中国の若者の間で、ロウ・イエの作品は非常に人気があるようだ。地下映画なので海賊版DVDかインターネットでしか観れないが、それが故にという部分もあるのだろう。
林家威の処女長編作品「after all these years」も、もちろん地下映画だ。素晴らしい作品に仕上がった。主役を演じた狗子の存在感に僕は魅せられ、「黒四角」にも出演してもらった。狗子は北京アングラ界の有名人で、「黒四角」では一風変わった詩人の役を演じている。林家威はその後、「after all these years」含め、立て続けに4本の作品を発表している。彼の屋号は『シネマ・ドリフターズ』。映画漂流者…それはまさに彼のことだ。世界中に散らばる友人のアパートのソファを拠点に、彼は今日も映画の企画を練っていることだろう。機会があれば、是非彼の作品世界を堪能していただきたい。
投稿者について
Hiroshi Okuhara: 映画監督 1968年生まれ。『ピクニック』がPFFアワード1993で観客賞とキャスティング賞を、『砂漠の民カザック』がPFFアワード1994で録音賞を受賞。99年に製作された『タイムレス・メロディ』では釜山国際映画祭グランプリを受賞した。その後『波』(01)でロッテルダム国際映画祭NetPac Awarを受賞するなど、高い評価を受ける。その他の作品に『青い車』(04)、『16[jyu-roku]』(07)がある。本作品は、5本目の長編劇場作品に当たる。
- 初到北京 / 0 Comments
- 宋庄 / 0 Comments
- 冬天 / 0 Comments
- 地下電影 / 0 Comments
- 回国 / 0 Comments