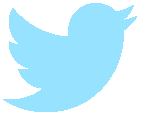沟通

第9回/沟通
前回Billion Beatsに文章をアップしたのが「黒四角」の公開前だったので、それから2ヶ月以上が経ってしまった。前回はプロデューサーの李鋭の話で、連載は撮影前の時間で止まったままだ。当初の予定では公開中も引き続き撮影中の様子等をお伝えするつもりだったのが、どうにも書けない。なぜ書けないのか。正直に言ってしまうと、面倒くさくて書く気が起きなかった。公開前に受けた取材や公開中に開催したイベントや映画を見終わったお客さんから北京での撮影の様子について聞かれることが多く、話し慣れてしまうと改めて文章に書こうにも新鮮味がなく何だかとてもつまらなく思ってしまう。上映期間中、僕は毎日劇場に行き、映画が終わって劇場のドアから出て来るお客さんの顔を観察した。中には直接感想等を言って下さる方もいたが、それはそれほど多くない。お客さんはどう感じたのだろうかと不安な気持ちで毎回ドアの外で終映の時間を待っていた。最初の2週間は1日4回の上映で、後の2週は1日3回。計90あまりの不安な気持ちを劇場ロビーに残したことになる。これも書けなかった理由であろう。その1ヶ月間、客観的に振り返るには「黒四角」は生々し過ぎた。
早稲田大学でアジア映画についての授業を受け持つ石坂建治氏が「黒四角」鑑賞を学生への課題にしてくれた。石坂氏は東京国際映画祭のディレクターでアジア映画部門を担当している。「黒四角」を東京国際映画祭に出品した際にも大変お世話になった。「黒四角」の観客は多くが60歳以上のシニア層であったが、石坂氏のおかげで観客の平均年齢がやや下がった。これは「黒四角」がシニア層に支持されたという意味ではなく、現在の日本のミニシアターを支えているのがこの世代の観客なのだ。今やどの劇場に行っても、まばらな客席を占めるのは元気で好奇心の強いおじさんおばさんたちだ。そんな中、早稲田大学に通う若者達は「黒四角」をどう観たのか。新宿での公開が終了後、僕は彼らの書いた感想文の束を受け取った。これが実に面白い。口頭で意見や感想を伝えられるのとはまったく違い、文章だと書き手の個性が強く反映される。物語にまつわる彼らひとりひとりの見立てが実にいい。「鏡を見た黒四角が笑ったのは空洞という自らのアイデンティティを確認したせいではなかろうか」「チャオピンが画家として存在する世界は虚構で、すべては日本兵であった黒四角が望んだ世界なのではないかと私は思った」「黒四角は心を失い身体を取り戻したが、次第に人々との交流や愛によって黒四角の精神が満たされていくことによって今度は身体が失われて行く。その過程が描かれている」等等…。改めて映画は観客が完成させるものだと僕は思った。劇場のドアから出て来たひとりひとりの心の中に、ひとりひとりの「黒四角」があるのだ。うっかりするとそうしたことは見過ごしてしまう。感想文を読み、僕はとても嬉しくなった。そしてまた勉強もさせてもらった。映画を乗り物として作り手と受け手は1対1のコミュニケーションをする。そして人と人とのコミュニケーションというものは、媒介物が映画に限らず(例えば言葉でも)、多くの場合そこに齟齬が生じる。完全なやり取りなどありえない。それが素晴らしいと僕は思う。我々はデジタルデータではないのだ。
コミュニケーションといえば、撮影期間中の最大の課題がそれだった。「黒四角」の撮影現場には、日中双方からほぼ半々の割合でスタッフがいた。日中の撮影現場で一番大きな違いは現場におけるスタッフの在り方だ。日本の現場だとスタッフが自分の人間性を大っぴらに出してくることはまずない。撮影が終わり、打ち上げの2次会くらいになって、ああこの人は実はこういうキャラクターの持ち主だったのか、と分かるくらいなものなのだが、中国では初日からほぼ全スタッフが自分を前面に押し出してくる。これは僕が撮影中に感じたことではなく、撮影の槙が言っていたことで、僕も言われてなるほどと思った。槙は僕よりはるかに日本での映画撮影の経験が多くある。撮影当時、僕はすでに中国人のこの性質に対する免疫があった。彼らは場に応じて自分の人間性を隠したり出したりなどしない。そうする意味も必要も分からないのだろう。僕にもそれはよく分からない。分からないけれどそうするものだと身に染み付いてしまっている。僕は自然に自分らしくいられる彼らを羨ましく思う。本当はどこにいたって誰といたって自分は自分でしかないのだから。ただし、ものには限度がある。ある程度の節度は保って欲しいと思わずにはいられない場面もあった。日本人としてではなく監督として。例えばリーホワと黒四角のキスシーン。日本のスタッフであれば現場の緊張感を緩めるような言動は絶対に許されない。ところが彼らはどうだったか。鼻歌を歌い冗談を言い合い、いつもの調子だ。リーホワ役の丹紅を囃し立て、ヤジを飛ばす者もいた。さすがにこれには僕も閉口した。監督である僕が怒ってどなりつけたりすればいいのだろうけれど僕にはそれをうまくできた試しがない。
映画の撮影は、日々生じる大小様々な問題をその場にいる全員で解決しながら進んで行く。時間とお金のない現場ではその多くが一刻を争う事態となる。そうした場合、日中間のコミュニケーションどうこう言ってる余裕はない。でも実はそうした事態の積み重ねが我々の関係性を鍛え上げていた。例えば夜中の撮影中、室内に焚いた照明機材の灯りが突然消えた。どうしたことかと外に出てみると、電源のジェネレーターから煙が上がっている。暗闇にスタッフの怒鳴り声と笑い声が飛び交う。笑い声が混ざるのが中国での撮影のいいところ。小1時間ほどの騒ぎがあって、再びジェネレーターが唸り声をあげると、同時にパッと辺りが明るくなる。わき起こる拍手と歓声。そして撮影がまた始まる。「黒四角」の撮影に参加した日中双方のスタッフが、僕を含め、互いに成熟した関係性を築き上げたとはとても言えないし、対立することも度々あった。けれども直面した様々な小さな事態を皆でどうやって解決していったか、それを具体的にひとつひとつ思い返してみると案外うまくやっていたのではないかとも思う。我々は一緒に映画を作り、その証が「黒四角」という作品になった。それを思うと僕は誇らしい気持ちになる。
これからもまだまだ地方での公開が続きます。詳細は「黒四角」公式ホームページhttp://www.u-picc.com/black_square/でご確認ください。引き続きどうぞよろしくお願いします。
投稿者について
Hiroshi Okuhara: 映画監督 1968年生まれ。『ピクニック』がPFFアワード1993で観客賞とキャスティング賞を、『砂漠の民カザック』がPFFアワード1994で録音賞を受賞。99年に製作された『タイムレス・メロディ』では釜山国際映画祭グランプリを受賞した。その後『波』(01)でロッテルダム国際映画祭NetPac Awarを受賞するなど、高い評価を受ける。その他の作品に『青い車』(04)、『16[jyu-roku]』(07)がある。本作品は、5本目の長編劇場作品に当たる。
- 初到北京 / 0 Comments
- 宋庄 / 0 Comments
- 冬天 / 0 Comments
- 地下電影 / 0 Comments
- 回国 / 0 Comments