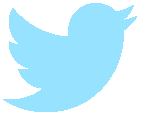第1回 写真がふたりの言語だった

(写真)最近のインリ ー 三影堂撮影芸術中心の中庭で
インリがロンロンと出会ったのは1999年12月、東京の立川。インリが27歳の冬のことだ。
彼が編集していた『NEWPHOTO』という手製のコピー誌が注目され、立川で開催していた国際芸術祭にロンロンが中国の現代写真家を代表して招かれて来日していました。
たまたまその展覧会に行って、彼の作品に強い印象を受けました。会場にいた彼に会った時に自分の塞いだ心が開かれて、彼が自分の心に入ってくるのがわかったんです。
インリは、東京の写真専門学校を卒業後に契約カメラマンとして3年間働いた新聞社を辞めたところだった。新聞社では雑誌のグラビアや取材を担当。現場で撮る写真と自分の目指す写真とのギャップに耐えられなくなると、ある日突然スキンヘッドにして出社したこともあった。表現としての写真を模索し、自我との格闘のさなか。写真仲間と議論すれば互いの写真観を徹底的に攻撃し合う。精神的に疲弊する中、ロンロンと写真を通して言語を超えて理解し合う体験をする。
彼の作品は素晴らしくて、何かとても強いものがありました。そこに撮られているものに共感できる思いがあったのと、自分が写真を撮ってることの理由のようなものが、彼の写真の中にも見えたんです。
「なぜ写真を撮るのか」というところで深く理解し合えたんだと思います。
それは、自己認識のためなどとは違います。写真を通してしか表現ができない、逃れられない重たいものがある。でもそれは、いくら表現しても自分が開かれていかない苦悩でもありました。出口は写真を通してしか見つからないとわかっているけれど、なかなか見つからない。ふたりともそういう状況にあって、写真を通して交差することで似たような現状をわかり合えたのと、ふたりは交差することによってもしかしたら開かれていくかもしれないという予感めいた思いがあったかもしれません。
中国に帰ったロンロンからは「中国に来てほしい」という国際電話やファックスが届き続ける。
写真を撮ることでしか自分の存在が成立しなくて、第三者を受け入れられない状態でした。閉じていた心が彼に会った時に突然開かれて、彼も自分の心の中に入ってきているんですが、すぐには自分の変化を受け入れられませんでした。
その頃私が撮っていたのは「Gray Zone」というシリーズです。自分の身体からわき起こる生命の叫びを撮ったものです。撮影を終えた後、それ以上に強い生命観が生まれてこなくなっていて、しかも自分の現実を考えると魂だけはあるんだけど、実際に身体がついてきてない、魂ばかりみたいな存在になってしまっていました。
世紀末的な空気に支配されていた99年に続いて、2000年は「ないはずの世界がまだあった」的な取り残された1年という感覚が私にはありました。その意味で、2000年は私にとっては空虚な時間だったんです。
さらに、ロンロンのところに行かない自分も空虚でした。彼は自分の心に入ってきているのに、自分の殻が強すぎるためにそれを認めて一歩進もうという展開はできないんです。
表現者同士だから、彼のところに行ったら自分の写真が消えてしまうかもしれないという恐ろしさもありました。
一方のロンロンは福建省の山間の農村地帯で育った。勉強は苦手だったが絵を描くのは好きだった。成績が悪くていつも教室では小さくなっていたけれど、ある日教室の後ろの黒板に描いた絵を先生がすごく褒めてくれた。初めて自分に自信を持ったという少年時代——。
目指す美術大学に合格できなくて浪人していたある日、村の写真館で初めてカメラを触らせてもらったそうです。見よう見まねで撮った妹の写真を現像した時現れた絵を見て驚愕し、これこそが自分の表現したかったものだったと思ったって言うんです。絵では表現できなかった世界がまさにそこに映っていた、そう感じたと彼は言います。
父が責任者を勤める農協で3年働いて貯めた1万元を手に、92年、22歳で彼は北京に出てきました。カメラを買って数年は働かずに写真だけ撮るつもりだったそうですが、北京の物価は農村とは桁違い。流れ着いた東村は北京市朝陽区の朝陽公園のそば。今では高級住宅が立ち並んだ開発地区となっていますが、当時は町外れで一番安い場所。たまたま若い前衛芸術家達が集まっていました。パフォーマンスや絵画を通して 新しい価値の表現に挑む同志との出会いから、夢中で彼等を撮り始めたのが、彼の写真の原点です。
ロンロンは、カメラだけは信じられた。カメラを手にしたことで表現者として自由にどこまでも羽ばたいていけると感じた。
当時の北京で前衛芸術は誰にも理解されませんでした。ロンロンは生活のために、映画のスチールや映画館の宣伝の写真を撮っていました。発表できる媒体もない中で、仲間と2人で作品をコピーして手綴じでつくった雑誌を美術館関係者や海外の大使館に配ったんです。この『NEWPHOTO』だけが発表の場でした。
『NEWPHOTO』は国内の芸術関係者から海外へと広められていき、海外の写真芸術関係者や現代芸術関係者にも注目されていく。それが、ふたりの出会いとなった99年・立川での展覧会にもつながったのである。
海の向こうから電話をかけてくるロンロンと、カタコトの英語でポツポツとしゃべりながら受話器の向こうの息づかいを感じるという時間が半年ほど続きました。彼は北京に来てほしいと言う。でも、行けば自分が自分でなくなってしまうと思っていました。自分を変えたら写真が撮れなくなるという怖さ。9ヶ月間悩んだ末に、自分の写真が撮れなくなったら、その時は仕方がない。葛藤があるんだったら行ってみるしかない。そう思って行くことを決意しました。
2000年9月、インリは1ヶ月の観光ビザを取得し、北京へ。
やっと会えても、言葉はやっぱり通じない。私は中国語はわからないし、彼は日本語はわからない。英語だってカタコト。ふたりで英語と中国語と日本語が混じったような言葉をつくってしゃべっていました。
まわりの人はわたしたちが何をしゃべってるのかわからないから、好き勝手にふたりだけでふたりにしか通じない言葉で会話をしていたんです。いまそのビデオを見ると自分でも何をしゃべっているのかわかりません。
生まれたばかりの双子が、放っておくとふたりだけの言葉をつくっている——。そんな感じでした。
写真が私たちの共通語でした。写真を通して理解し合える。だから言葉はあまり必要としなかったんです。
そもそも出会った瞬間は、中国人とか日本人とかいうことより、自分たちの中でもっとも大切だった写真を通して互いに開かれ合えた。
そういうふたりが、互いの写真を通じて欠けていた部分が補われて満たされた気分になったり、自分が求めている部分について何か潤いが得られたような感じがあったんだと思います。そうでないと、写真を見ただけで理解し合えたというふうにはならないでしょう。
ほかの人に説明しても「よくはわかりません」と言われるんですが。
北京オリンピックに向けて街中が工事中の状態になるにはまだ早いこの頃。北京市の主要交通網である環状道路は現在7環まであるが、当時は3環が整備された時期だった。
彼はまだ無名でしたが、注目され始めていました。
中国国内で現代アートは開かれた存在ではありませんでした。それが少しずつ変化し始めたのが2000年です。国立の美術館でも展示が行われたり、それにあわせていろんなところで小さな展覧会が開催されたりして国内でも少しずつ公な動きが出てきた時なんです。
この年の11月に、上海ビエンナーレが開幕しました。方力釣(ファン・リージュン)、黄永砅(ファン・ヨンビン)といった中国現代アートを代表する大御所の作家たちの作品が一挙に展示された展覧会。それも、初めて国内の美術館で展示した記念すべき展覧会です。ロンロンは言いました。
「彼らのような現代アーティストが国の美術館で展示できるなんて、これまではまずなかったこと」
上海じゅうのアトリエやギャラリーで上海ビエンナーレに関連する展覧会が開かれていました。その中に艾未未(アイ・ウェイウェイ)がキュレーターとして主催した『FUCK OFF』という展覧会があって、そこでロンロンも作品を発表したんです。
観光ビザを延長し、2ヶ月の滞在を終えてインリが帰国すると、その後資生堂ギャラリーが『亜細亜散歩』 展を企画。再来日したロンロンとインリは日本で入籍した。そして本格的な創作活動が始まる。(第2回「北京は世界につながっていた」に続く)
関連記事:
投稿者について
Inri: アーティスト 北京在住 1973 神奈川県生まれ 1994 日本写真芸術専門学校卒業 1994-97 朝日新聞社出版社写真部委託勤務 1997 フリーランスとなり自主作品制作に専念 2000 榮榮と共作開始 2001 オーストリア連邦政府のレジデンスプログラムに参加 2006 北京に三影堂撮影芸術中心を創設