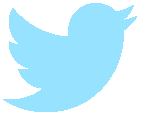林先生-地震と停電のなかで

「毎日大きな船に乗っているような感覚です。その船は時には大きく、時には小さく、ずっと揺れ続けています」
大地震の発生から1カ月経った4月11日、林先生は電話でそう言った。ちょうどその日の午後にもマグニチュード7の地震があり、それは余震とは言われているものの、彼にとっては地震と言った方が納得できそうな規模のものだった。中国人の林先生は約20年前から東京に住み、大学で中国語を教えている。
建物が激しく揺れ、家具がガタガタと音を出し始め、自分自身も強い耳鳴りのようなグラつく感覚に襲われた時、林先生はそれが地震なのだと分かった。
我眼中的日本人4 – 林老师在日本的地震与停电中
いつものようにすぐテレビをつけると、すでに地震の規模がアナウンスされていた。マグニチュード7。他の国では数百人、いや数千人の命までもが一瞬にして奪われてしまうかもしれない数字である。しかし彼が耳にしたのは、自分が実際聞いたか、感じただけか、いずれにせよ地震の“ドーン”という音だけだった。地震に驚いて叫ぶ人の声はまったく聞こえてこなかった。
建物からはすぐに人が出てきた。互いに話すでもなく、それぞれが携帯の画面を見ているかメールを打っているだけだった。先生は外に出ていくのが億劫で、窓からその光景を眺めていたのだ。彼の5階の部屋から見渡す限り、日本の一般的な住宅である2階建ての一軒家は特に損傷を受けた様子はない。程なくして、表に出て携帯をいじっていた人々も建物の中に戻って行った。彼らもきっと先生と同様、テレビをつけ、マグニチュード7という数字といくつかの地名を確認すれば、また淡々と、何事もなかったように過ごすのだ。たった今起きた地震について家族と話すことすらしないかもしれない。
“冷静に、あるいは仕方なく、とも言おうか、自然の脅威をただ黙って受け入れるしかない”その日本的な感覚を、先生もまた自身の経験から身に着けていた。人々は自然や政府に対して恨みごとを言うでもなく、ただひたすら耐え忍ぶ。しかしその声なき忍耐の陰には再起への叫びが潜んでいる。先生はその無言の叫びを、耳でなく肌で感じとっていた。
より現実的な問題として先生が向き合わなければならなかったのは、地震そのものよりもその後の停電だった。皆こぞって電池を買いに走り、お店では品切れ・品薄となる。家に電池のストックがあったとしても、売られているのを目にしたら買わずにいられないというような状況だった。
停電すればテレビは見られない。先生はラジオを聞き始めた。夜は枕元に置いた。何度か聞きながら眠りにおちてしまったこともあった。停電が終わって、スイッチを消し忘れていた部屋の照明が突然灯ると、先生は目を覚まし、自分がもう何時間か眠っていたことに気付く。先生のラジオは1時間聞くと自動的にオフになる、タイマー付きのタイプだ。日本では様々なものが周到にデザイン・設計されている。地震や津波、台風や集中豪雨にしばしば襲われる日本だが、普段の生活が便利で快適なのはもちろん、人々は災害時のような非日常であっても尚更、その便利さ快適さを保つために最大限の努力をしている。
中国から日本にやってきた林先生は、今回の大地震という状況下で、初めて2つの国がこんなにも違うものかと、悠久(中国)と刹那(日本)の絶対的な違いに気がついたのだった。そして自分もまた、地震が起きていない時に仕事や暮らしをより充実させるにはどうするべきなのかを考えた。
「停電が終わったので、灯りをつけて学生の提出物に目を通し始めました。その作業をするにはその一つの灯りだけで充分だったので、テレビは消したままにしておきました。とてもはかどりましたよ」
先生はそう言った。
停電に見舞われる以前の日本は、街全体がきらびやかなネオンに彩られ、その光が人の心をも過度に照らし、浮足立たせていた。停電は生活には大きな不便をもたらしたけれども、社会があるべき姿に戻ったのではないか、と先生は考えたのだった。
地震に対する日本人の冷静な対応と、停電という状況下で現れた生活の変化、これらはもう20年あまり日本で暮らす林先生にとって、初めて目にする日本の姿であった。
関連記事:
 その28 清水美和さん : 文革の影響を受けた記者
その28 清水美和さん : 文革の影響を受けた記者
 その27 大野信行さん:リーマンショックをきっかけに
その27 大野信行さん:リーマンショックをきっかけに
 その26 安藤裕康さん : 外交官から転身して
その26 安藤裕康さん : 外交官から転身して
 その25 山名健司さん : 日中が共有できる経験から
その25 山名健司さん : 日中が共有できる経験から
 その24 坂東玉三郎さん : 女形の極みから
その24 坂東玉三郎さん : 女形の極みから
 その23 本田雅一さん : フリーランスジャーナリストとしてのスピリット
その23 本田雅一さん : フリーランスジャーナリストとしてのスピリット
 その22 石島幹也さん:メイクの可能性
その22 石島幹也さん:メイクの可能性
 その21 森下洋子さん : 40数年前の衣装とともに
その21 森下洋子さん : 40数年前の衣装とともに
 その20 後藤雄三さん:環境保護と新エネルギーの可能性、そして困惑
その20 後藤雄三さん:環境保護と新エネルギーの可能性、そして困惑
 その19 野本正明さん : 日立の考えるスマートな次世代都市とは
その19 野本正明さん : 日立の考えるスマートな次世代都市とは
 その18 武田勝年さん:社会貢献の新しいかたち
その18 武田勝年さん:社会貢献の新しいかたち
 その17 渡辺日出夫さん:展覧会場を避難所に
その17 渡辺日出夫さん:展覧会場を避難所に
 その16 早坂裕さん:宮城発・スプレー塗装の革新
その16 早坂裕さん:宮城発・スプレー塗装の革新
 その15 本田勝之助さん : 福島の復興のために
その15 本田勝之助さん : 福島の復興のために
 その14 及川久仁子さん : “千年鉄器”を作り続けて
その14 及川久仁子さん : “千年鉄器”を作り続けて
 その13 栗原小巻さん
その13 栗原小巻さん
 その12 山田洋次さん:あたたかい眼差しとともに
その12 山田洋次さん:あたたかい眼差しとともに
 その11 鈴木さん:神社の宮司
その11 鈴木さん:神社の宮司
 その10 野松先生と車
その10 野松先生と車
 その9 辻元清美さん:国内外の民間パワーを被災地に
その9 辻元清美さん:国内外の民間パワーを被災地に
 その8 斉藤裕さん:「家、企業、都市」の概念
その8 斉藤裕さん:「家、企業、都市」の概念
 その7 普段着の東京:去りゆくネットカフェ
その7 普段着の東京:去りゆくネットカフェ
 その6 光:大地震後に生まれた新しい命 ― 世代を繋いで ―
その6 光:大地震後に生まれた新しい命 ― 世代を繋いで ―
 その5 ワタナベさん :ハンカチ落とし―バブルのあとに残ったものは―
その5 ワタナベさん :ハンカチ落とし―バブルのあとに残ったものは―
 その4 『言論NPO』代表・工藤泰志さん:救援・甘いもの・ウーロン茶
その4 『言論NPO』代表・工藤泰志さん:救援・甘いもの・ウーロン茶
 その3 富岡隆夫さん・雑誌編集長
その3 富岡隆夫さん・雑誌編集長
 その2 仙台在住の主婦・小林(古城)三千代さん
その2 仙台在住の主婦・小林(古城)三千代さん
 その1 匿名
その1 匿名
投稿者について
ChenYan: 会社経営者 1960年北京生まれ。 1978年に大学に進学して日本文学を専攻した。卒業後に日本語通訳などをして、1989年に日本へ留学し、ジャーナリズム、経済学などを専攻し、また大学で経済学などを教えた。 2003年に帰国し、2010年まで雑誌記者をした。 2010年から会社を経営している。 主な著書は、「中国鉄鋼業における技術導入」、「小泉内閣以来の日本政治経済改革」など多数。