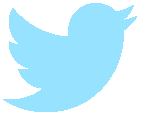その10 野松先生と車
野松先生の車はハイブリッドカーだ。
ハイブリッドカーは、日本でかつて使われていたMD(ミニディスク)やMO(光磁気)と同様に、本来は中国国内にマーケットがあって然るべきであるのに、それがないまま今に至っている。もともと中国国内に関連技術がなかったこと、政府が経済レベルでその開発を推し進めていなかったことが、上記のいずれもが中国に普及していない原因だろう。そしてハイブリッドカーがMDやMO以上に世界じゅうで大流行していたころ、中国だけはまだ蚊帳の外だった。
だから野松先生が一般消費者としてハイブリッドカーを選んだのは、私にとって軽い驚きたった。
現在、私の知人のうち何人かがハイブリッドカーを所有している。そのうちひとりは国立公園に勤める公務員だ。家はとても裕福で、彼女のお母さんはもともとヨーロッパの有名メーカーの車を買うように薦め、お金も一部出してくれると言っていたそうだが、彼女が最終的に選んだのは日本製のハイブリッドカーだった。
「国立公園の職員として環境保護に気を配らなくてはなりません。車を使わないのがいちばんですが、勤め先の公園がとても広いのと仕事で外出することも多いので、運転するならハイブリッドカーがいいと思いました」
と彼女は言った。公園の管理事務所の車も当然ハイブリッドカーであり、ためらうことなく同じタイプの車を自分用に選んだのだった。
もうひとりは大学の学長をしている。ある日大学のOB会のあいさつの席上、買ったばかりのハイブリッドカーも話題に取り上げ、そこにいた人たちに今後自家用車を購入するのなら、自分の車のようなハイブリッドカーがいいと薦めた。
「購入して1カ月あまりが過ぎました。毎日乗っていて気づきましたが、以前の車よりもだいぶガソリンの節約になっています」
彼はそう語った。
学長がどこかのメーカーの宣伝をしているようにはまったく思わなかった。この話を聞いた元学生たちはむしろ、母校に対して、そしてオピニオンリーダーの役割も果たしている学長に対して、その環境保護意識の高さに好感を持ったのではないだろうか。
野松先生は大学教授だ。
「工業区の近くに住んで20年あまり、私はひどい喘息持ちです。以前は車を運転していましたが、喘息になったのを機にやめました。車は空気汚染になり、他の人まで喘息になってしまいますから」
彼女はそれだけの理由でもう何年も車を運転していなかった。
先生は最近再び運転するようになった。大学は交通が不便な郊外にあり、仕事で外出するにも車が必要なことが多い。先生ももう若くはなく、毎日歩くのも自転車やバスを利用して通勤するのもあまり現実的ではない。しかし、車を買う決心がついた最大の理由はハイブリッドカーの登場だ。
「普通の車に比べて価格は少し高いですが、省エネと環境保護という観点からすれば十分受け入れられるものでした」
先生は言った。
数年前、ハイブリッドカーの販売台数は世界で100万台を記録した。2011年3月には300万台を超えている。
「中国での販売台数は約1万台です」
とある海外メーカーのセールスマンが言った。中国メーカーが開発したハイブリッドカーは、2010年前後に続々と登場している。
中国のニューリッチ層、官僚やオピニオンリーダーは、お金はあっても野松先生のような責任感に欠けている。運転を長い間やめていた野松先生がハイブリッドカーを選んだのは、彼女自身の喘息が理由だ。理念+自らの体験に基づく感覚――中国以外の国でハイブリッドカーがよく売れている理由のひとつかもしれない。
関連記事:
 その28 清水美和さん : 文革の影響を受けた記者
その28 清水美和さん : 文革の影響を受けた記者
 その27 大野信行さん:リーマンショックをきっかけに
その27 大野信行さん:リーマンショックをきっかけに
 その26 安藤裕康さん : 外交官から転身して
その26 安藤裕康さん : 外交官から転身して
 その25 山名健司さん : 日中が共有できる経験から
その25 山名健司さん : 日中が共有できる経験から
 その24 坂東玉三郎さん : 女形の極みから
その24 坂東玉三郎さん : 女形の極みから
 その23 本田雅一さん : フリーランスジャーナリストとしてのスピリット
その23 本田雅一さん : フリーランスジャーナリストとしてのスピリット
 その22 石島幹也さん:メイクの可能性
その22 石島幹也さん:メイクの可能性
 その21 森下洋子さん : 40数年前の衣装とともに
その21 森下洋子さん : 40数年前の衣装とともに
 その20 後藤雄三さん:環境保護と新エネルギーの可能性、そして困惑
その20 後藤雄三さん:環境保護と新エネルギーの可能性、そして困惑
 その19 野本正明さん : 日立の考えるスマートな次世代都市とは
その19 野本正明さん : 日立の考えるスマートな次世代都市とは
 その18 武田勝年さん:社会貢献の新しいかたち
その18 武田勝年さん:社会貢献の新しいかたち
 その17 渡辺日出夫さん:展覧会場を避難所に
その17 渡辺日出夫さん:展覧会場を避難所に
 その16 早坂裕さん:宮城発・スプレー塗装の革新
その16 早坂裕さん:宮城発・スプレー塗装の革新
 その15 本田勝之助さん : 福島の復興のために
その15 本田勝之助さん : 福島の復興のために
 その14 及川久仁子さん : “千年鉄器”を作り続けて
その14 及川久仁子さん : “千年鉄器”を作り続けて
 その13 栗原小巻さん
その13 栗原小巻さん
 その12 山田洋次さん:あたたかい眼差しとともに
その12 山田洋次さん:あたたかい眼差しとともに
 その11 鈴木さん:神社の宮司
その11 鈴木さん:神社の宮司
 その9 辻元清美さん:国内外の民間パワーを被災地に
その9 辻元清美さん:国内外の民間パワーを被災地に
 その8 斉藤裕さん:「家、企業、都市」の概念
その8 斉藤裕さん:「家、企業、都市」の概念
 その7 普段着の東京:去りゆくネットカフェ
その7 普段着の東京:去りゆくネットカフェ
 その6 光:大地震後に生まれた新しい命 ― 世代を繋いで ―
その6 光:大地震後に生まれた新しい命 ― 世代を繋いで ―
 その5 ワタナベさん :ハンカチ落とし―バブルのあとに残ったものは―
その5 ワタナベさん :ハンカチ落とし―バブルのあとに残ったものは―
 その4 『言論NPO』代表・工藤泰志さん:救援・甘いもの・ウーロン茶
その4 『言論NPO』代表・工藤泰志さん:救援・甘いもの・ウーロン茶
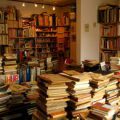 その3 富岡隆夫さん・雑誌編集長
その3 富岡隆夫さん・雑誌編集長
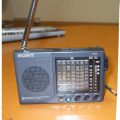 林先生-地震と停電のなかで
林先生-地震と停電のなかで
 その2 仙台在住の主婦・小林(古城)三千代さん
その2 仙台在住の主婦・小林(古城)三千代さん
 その1 匿名
その1 匿名
投稿者について
ChenYan: 会社経営者 1960年北京生まれ。 1978年に大学に進学して日本文学を専攻した。卒業後に日本語通訳などをして、1989年に日本へ留学し、ジャーナリズム、経済学などを専攻し、また大学で経済学などを教えた。 2003年に帰国し、2010年まで雑誌記者をした。 2010年から会社を経営している。 主な著書は、「中国鉄鋼業における技術導入」、「小泉内閣以来の日本政治経済改革」など多数。