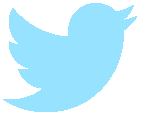その14 及川久仁子さん : “千年鉄器”を作り続けて

震災被災地のひとつ・岩手を訪ね、及源鋳造の及川久仁子社長に会った。
社長が3月11日当時の様子を語ればその心臓はなお鼓動を速めるようだった。
「私たちの会社では鉄瓶や鉄鍋を作っています。出来上がった商品は棚に並べてありました。地震では最初は左右に、続いて上下に揺れ、棚の商品は音を立てて床に落ちていきました」
恐怖は大きな音とともに襲いかかった。工房の外壁は崩れ、敷地の地盤が沈み始めた。及川社長はその時を思い出すのも辛いといった様子だった。
鋳造工房の電気炉では鉄を溶かしている最中だった。地震後の停電で炉が動かなくなれば溶鉄は鉄の塊に、そして炉も使い物にならなくなってしまう。
「幸い発電機がありましたので、すぐにそこから送電し炉内の鉄が塊になることはありませんでした」
及源鋳造は1852年に設立されている。明治政府の成立よりも十数年前のことである。そんな伝統ある会社だから危機対応にも長けている。準備が周到だったからこそ今回の地震で商品などの損害は少なくなかったにせよ、工場の要である電気炉を守ることができたのだ。
続いての困難は原料の不足だった。物流システムが発達している日本では、例えば商品の発注を受けたその日に原料会社に電話をすれば翌日か翌々日には原料が届く。そしてすぐに商品を製造し納品する。原料であれ製品であれ在庫を少なく持つということは、日本の大多数の企業にとって財務上の負担が減るということだ。日本の中小企業が厳しい競争に対応すべく迅速に立ち回るひとつの要素だろう。しかし、物流システムが発達しているからこそ、それが機能しない場合経営にどんな影響を及ぼすのかを考慮する機会は全体的に少ないと言える。
「原料が来なければ何も作れません。大型クレーンがなければ工房も修繕できません。地震による交通への影響、ガソリン不足が原因です。自分たちでできる範囲はなんとかやってみましたが、大型設備がないことには努力しても限りがありました」
社長は言った。
製品を納期通りに納品できれば何よりだが、状況は厳しい。
「地震を納品延期の理由にすることはできません」
震災後、及川社長は在庫を確認するとすぐに運送会社に連絡し、同時に自分たちで工房を修繕し始めた。
「3月28日(地震発生から17日後)、電気炉が動き始め生産を再開することができました」
社長は親しい人の忘れもしない誕生日であるかのようにその日を語った。
約千年前に京都から岩手県の丘陵にやってきた職人は、そこに質の良い砂鉄があることを知り、日常に用いる各種鉄器の名産地となった。日本には他にもいくつか良質の砂鉄が採れる場所があるが、そこでは主に日本刀が作られている。一方でここ岩手は千年もの間、鉄瓶や鉄鍋など鉄器製造の伝統を守り続けている。
「私たちは震災からさほど期間をおかずに鉄瓶を作り始めることができました」
及川社長のその言葉には“千年鉄器”を作り続けるという強い決心と、プライドがにじんでいた。
関連記事:
 その28 清水美和さん : 文革の影響を受けた記者
その28 清水美和さん : 文革の影響を受けた記者
 その27 大野信行さん:リーマンショックをきっかけに
その27 大野信行さん:リーマンショックをきっかけに
 その26 安藤裕康さん : 外交官から転身して
その26 安藤裕康さん : 外交官から転身して
 その25 山名健司さん : 日中が共有できる経験から
その25 山名健司さん : 日中が共有できる経験から
 その24 坂東玉三郎さん : 女形の極みから
その24 坂東玉三郎さん : 女形の極みから
 その23 本田雅一さん : フリーランスジャーナリストとしてのスピリット
その23 本田雅一さん : フリーランスジャーナリストとしてのスピリット
 その22 石島幹也さん:メイクの可能性
その22 石島幹也さん:メイクの可能性
 その21 森下洋子さん : 40数年前の衣装とともに
その21 森下洋子さん : 40数年前の衣装とともに
 その20 後藤雄三さん:環境保護と新エネルギーの可能性、そして困惑
その20 後藤雄三さん:環境保護と新エネルギーの可能性、そして困惑
 その19 野本正明さん : 日立の考えるスマートな次世代都市とは
その19 野本正明さん : 日立の考えるスマートな次世代都市とは
 その18 武田勝年さん:社会貢献の新しいかたち
その18 武田勝年さん:社会貢献の新しいかたち
 その17 渡辺日出夫さん:展覧会場を避難所に
その17 渡辺日出夫さん:展覧会場を避難所に
 その16 早坂裕さん:宮城発・スプレー塗装の革新
その16 早坂裕さん:宮城発・スプレー塗装の革新
 その15 本田勝之助さん : 福島の復興のために
その15 本田勝之助さん : 福島の復興のために
 その13 栗原小巻さん
その13 栗原小巻さん
 その12 山田洋次さん:あたたかい眼差しとともに
その12 山田洋次さん:あたたかい眼差しとともに
 その11 鈴木さん:神社の宮司
その11 鈴木さん:神社の宮司
 その10 野松先生と車
その10 野松先生と車
 その9 辻元清美さん:国内外の民間パワーを被災地に
その9 辻元清美さん:国内外の民間パワーを被災地に
 その8 斉藤裕さん:「家、企業、都市」の概念
その8 斉藤裕さん:「家、企業、都市」の概念
 その7 普段着の東京:去りゆくネットカフェ
その7 普段着の東京:去りゆくネットカフェ
 その6 光:大地震後に生まれた新しい命 ― 世代を繋いで ―
その6 光:大地震後に生まれた新しい命 ― 世代を繋いで ―
 その5 ワタナベさん :ハンカチ落とし―バブルのあとに残ったものは―
その5 ワタナベさん :ハンカチ落とし―バブルのあとに残ったものは―
 その4 『言論NPO』代表・工藤泰志さん:救援・甘いもの・ウーロン茶
その4 『言論NPO』代表・工藤泰志さん:救援・甘いもの・ウーロン茶
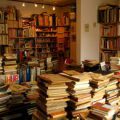 その3 富岡隆夫さん・雑誌編集長
その3 富岡隆夫さん・雑誌編集長
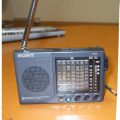 林先生-地震と停電のなかで
林先生-地震と停電のなかで
 その2 仙台在住の主婦・小林(古城)三千代さん
その2 仙台在住の主婦・小林(古城)三千代さん
 その1 匿名
その1 匿名
投稿者について
ChenYan: 会社経営者 1960年北京生まれ。 1978年に大学に進学して日本文学を専攻した。卒業後に日本語通訳などをして、1989年に日本へ留学し、ジャーナリズム、経済学などを専攻し、また大学で経済学などを教えた。 2003年に帰国し、2010年まで雑誌記者をした。 2010年から会社を経営している。 主な著書は、「中国鉄鋼業における技術導入」、「小泉内閣以来の日本政治経済改革」など多数。