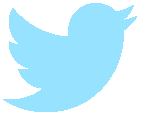その22 石島幹也さん:メイクの可能性
石島幹也さんと知り合ってから大分経った。彼の髪にも白いものが混じり始めたものの、つややかで血色のいい顔は以前と変わらない。日本人男性にとってスキンケアは珍しいものではなくなったのだ、ましてや石島さんは化粧品会社に勤めているから尚更だ、などと考える。
震災後、新橋にある石島さんのオフィスの喫茶スペースで会うことになった。エレベーターがまだ動いていなかった頃だ。そばには大きなスーツケースがおいてあり、私の視線を感じた石島さんは、
「お昼が済んだらこのまま出張なんですよ」
と言った。
話題はやはり震災のことが多くなる。特に私は被災地の取材から戻ったばかりで、その惨状を目の当たりにしていたということもあるだろう。日本は対口支援(中国の政策:中央政府が地方政府(省や市)に対して支援対象地区を割り当て、インフラ整備などの事業を行わせること)という方式がなく、被災地の復興は自らの力によるのみという現状や、衣食は足りているものの将来への不安を拭えない人々の沈んだ表情が私の心から離れなかった。
「被災地支援活動として会社から専門スタッフを派遣し、スキンケアやメイクの方法を伝えたり、実際に被災地の方にメイクをしました」
石島さんは言った。
企業の特性を生かし得意分野で被災地を支援するのはとてもいいことだ。しかし、スキンケアやメイク技術先進国である日本、初めて日本を訪れた中国人は日本人女性が皆しっかりお化粧していることに驚くほどだ。被災地の人々にとって化粧品会社からの“気持ち”は果たしてどれくらい伝わるものだろうか、と私は心の中で思った。
「お化粧してきれいにしている女性を見れば嬉しいですよね。そしてお化粧した方も相手が明るい表情で自分を見れば気分がいいでしょうし、自信にもなります。メイクにはそういう力があるんです。そして私たちは被災地の方々にメイクを施す際のプロセスを重視しています。誰かにお化粧をしてもらうということは、一人で鏡に向かうのとは違って会話が生まれます。これも一つのコミュニケーションだと考えています」
石島さんの言葉から、被災地でお化粧してもらった人々の表情やその場の和やかな雰囲気が私にも想像できるような気がした。
お化粧の後まるで別人のように明るくなった、という年配の女性が何人もいたという。石島さんはメイクによる支援活動に更に自信を持った。メイクは自分の沈んだ気持ちを隠してくれるだけでなく周りの人を明るくし、それが日常を取り戻す自信にもつながるだろう。救援物資では埋められない心の隙間がある。一度のメイクが果たした効果は小さくないだろう。
石島さんの引き締まった表情が心持ちから来ているのは当然だが、毎日のスキンケアの賜物という部分も多くあるのかもしれない。日本から戻って時折考えるのは、日常生活を少しだけ明るくする、こうした日本のスタイルが中国でも広まらないだろうか、ということだ。
関連記事:
 その28 清水美和さん : 文革の影響を受けた記者
その28 清水美和さん : 文革の影響を受けた記者
 その27 大野信行さん:リーマンショックをきっかけに
その27 大野信行さん:リーマンショックをきっかけに
 その26 安藤裕康さん : 外交官から転身して
その26 安藤裕康さん : 外交官から転身して
 その25 山名健司さん : 日中が共有できる経験から
その25 山名健司さん : 日中が共有できる経験から
 その24 坂東玉三郎さん : 女形の極みから
その24 坂東玉三郎さん : 女形の極みから
 その23 本田雅一さん : フリーランスジャーナリストとしてのスピリット
その23 本田雅一さん : フリーランスジャーナリストとしてのスピリット
 その21 森下洋子さん : 40数年前の衣装とともに
その21 森下洋子さん : 40数年前の衣装とともに
 その20 後藤雄三さん:環境保護と新エネルギーの可能性、そして困惑
その20 後藤雄三さん:環境保護と新エネルギーの可能性、そして困惑
 その19 野本正明さん : 日立の考えるスマートな次世代都市とは
その19 野本正明さん : 日立の考えるスマートな次世代都市とは
 その18 武田勝年さん:社会貢献の新しいかたち
その18 武田勝年さん:社会貢献の新しいかたち
 その17 渡辺日出夫さん:展覧会場を避難所に
その17 渡辺日出夫さん:展覧会場を避難所に
 その16 早坂裕さん:宮城発・スプレー塗装の革新
その16 早坂裕さん:宮城発・スプレー塗装の革新
 その15 本田勝之助さん : 福島の復興のために
その15 本田勝之助さん : 福島の復興のために
 その14 及川久仁子さん : “千年鉄器”を作り続けて
その14 及川久仁子さん : “千年鉄器”を作り続けて
 その13 栗原小巻さん
その13 栗原小巻さん
 その12 山田洋次さん:あたたかい眼差しとともに
その12 山田洋次さん:あたたかい眼差しとともに
 その11 鈴木さん:神社の宮司
その11 鈴木さん:神社の宮司
 その10 野松先生と車
その10 野松先生と車
 その9 辻元清美さん:国内外の民間パワーを被災地に
その9 辻元清美さん:国内外の民間パワーを被災地に
 その8 斉藤裕さん:「家、企業、都市」の概念
その8 斉藤裕さん:「家、企業、都市」の概念
 その7 普段着の東京:去りゆくネットカフェ
その7 普段着の東京:去りゆくネットカフェ
 その6 光:大地震後に生まれた新しい命 ― 世代を繋いで ―
その6 光:大地震後に生まれた新しい命 ― 世代を繋いで ―
 その5 ワタナベさん :ハンカチ落とし―バブルのあとに残ったものは―
その5 ワタナベさん :ハンカチ落とし―バブルのあとに残ったものは―
 その4 『言論NPO』代表・工藤泰志さん:救援・甘いもの・ウーロン茶
その4 『言論NPO』代表・工藤泰志さん:救援・甘いもの・ウーロン茶
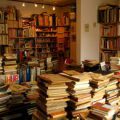 その3 富岡隆夫さん・雑誌編集長
その3 富岡隆夫さん・雑誌編集長
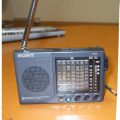 林先生-地震と停電のなかで
林先生-地震と停電のなかで
 その2 仙台在住の主婦・小林(古城)三千代さん
その2 仙台在住の主婦・小林(古城)三千代さん
 その1 匿名
その1 匿名
投稿者について
ChenYan: 会社経営者 1960年北京生まれ。 1978年に大学に進学して日本文学を専攻した。卒業後に日本語通訳などをして、1989年に日本へ留学し、ジャーナリズム、経済学などを専攻し、また大学で経済学などを教えた。 2003年に帰国し、2010年まで雑誌記者をした。 2010年から会社を経営している。 主な著書は、「中国鉄鋼業における技術導入」、「小泉内閣以来の日本政治経済改革」など多数。