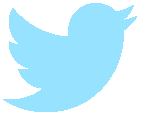その3 富岡隆夫さん・雑誌編集長

「どうもどうも!」
脳外科病棟から一般病棟に移った富岡隆夫さんは、私を見るなり顔をほころばせてそう言った。この「どうも」という言葉は、感謝や謝罪、不満なども表すことができる独特な日本語である。
「もう夫は顔を見ても誰か分からなくなってきているし、あまりお話もできないんです。でもあなたのことは分かって、とても嬉しそうです」奥さんは傍でそう言った。
その3 富岡隆夫さん・雑誌編集長 本
富岡さんは数ヶ月前手術を受けるために入院した。手術そのものは成功したのだが、おそらくある期間降圧剤を服用し忘れたためか、その後脳出血を引き起こし、言語障害と半身麻痺が残りベッドの上で生活する日々となった。
今私の目の前にいるのは、あの、毎週箱いっぱいの本を自宅に宅急便で送っていた編集長その人なのか?
富岡さんは病室のテーブルで新聞を1枚1枚めくっていた。その姿は昔私が彼の仕事場を訪れた時と同じだ。ただ、仕事場で新聞をめくっていた彼は、ついさっき私を目にしたときのようなほほ笑んだ表情だった。時には紙面を遠ざけて読んでいたので、私は横で「きっと老眼なのだろう」と思ったものだ。今の彼はというと、機械的にページをめくるだけで、掲載されている写真や見出しについても何も言葉を発しない。私が傍にいることも全く意識していないようだった。「夫はまだ文字を理解できているのかしら?」奥さんはひとり言のように呟いた。
中国よりも日本の雑誌編集長の方が格段にやり手、そんな印象を私は持っていた。富岡さんのデスク前にいる副編集長たちはそれは厳しく、編集者が提出したものに誤字脱字があろうものなら大声でどなりつけた。誤った表現や構成があやふやな文だったら言わずもがなだ。でも富岡さんはといえば、編集部の一番奥のデスクで新聞や本を読んで、ゆったりと構えている様子だった。
編集長としては、政財界はじめ各界の人たちとの面会にとても忙しくしていた。日本の雑誌編集長の多くが自らも筆を執る。通常、巻頭に寄せる言葉は富岡さんによるものだった。それは他のどの記事をも凌駕した、雑誌の方向性をクリアにするようなものである必要があった。彼のデスクには《戦国策》《史記》や、古代・現代小説が山積みされており、彼は古い資料の山からも現代社会に通用する珠玉のエッセンスとなる言葉を探し出しているのではないか、と私は思っていた。
「どうも・・・」富岡さんは頭を悩ませ呟いた。おそらく筆が進んでいないのだろう。しばらくすると、「この中国の作家ですが、私の引用方法は正しいでしょうか」富岡さんは私に尋ねた。彼の原稿用紙は縦書きの、1ページに200マスしかないタイプだった。行間のスペースはたっぷりあり、そこには何度も書き改めた跡が残っていた。私が中国文学に詳しくないことを彼は知っていたはずだが、それでも尋ねてきたのだった。探し出した言葉や引用する故実にピタリとはまる表現を考えだせた、そんな時彼はとても嬉しそうにしていた。副編集長たちはそんな彼の記事に敬服してはいたが、忌憚なく意見を飛びかわすことで表現はますます磨かれていった。編集長の表現が典型となって、編集者や記者がみんな同じような表現をすれば問題ない、というどこかの状況とは違っていたのだ。富岡さん自身も何度も推敲を重ね、文章を練り上げていった。
私が日本の雑誌を手にする度に巻頭の言葉を熱心に読むのは、そこに全精力を傾けている編集長たちの姿が垣間見えるからだろう。しかしこの頃では多くの雑誌で、編集長がそのプレッシャーに耐え切れず、学者や専門家による文章に取って代わられている。だからこそ私は彼の、いち早くテーマを定め、歴史的考察を深め、かつ現代的なセンスを持ち合わせた職業人としての記者精神に敬服してやまないのだ。
富岡隆夫さん・雑誌編集長 春餅
北京で食べる春餅

(写真)北京で食べる春餅
富岡さんのお宅を訪問させていただいたこともあった。そのとき奥さんは桶に盛ったすし飯と新鮮ないくらを食卓に出してくれた。そのいくらは私が幼いころに口にした肝油と同じくらい大きくて、きらきらと輝いていた。他にしその葉などもあしらわれていたと思う。富岡さんはまず海苔の上に薄めにご飯を、それからいくらをのせた。そしてアイスクリームコーンのような上が太くて下は細い形に巻いてかぶりついた。
私は北京で食べる春餅と同じように、上も下も同じ太さに巻いて、その“日本の手巻き寿司”を食べてみた。「どうも、王さん」と富岡さんは笑いだしたが、特に何を言うでもなかった。それからだいぶ経ってから、私は手巻き寿司とは上が太くて下は細い、ご飯がこぼれないような形にして食べるものということを知り、日本の生活の端々を細かく見てこなかった自分を省みると同時に、富岡さんがなぜあのとき一言教えてくれなかったのか、とも思った。もしかすると彼は中国人が春餅を食べるように手巻き寿司を食べる、それもまたよし、と思ったのかもしれない。
あの日も食後ソファで新聞を広げた。彼の家ではほとんどの一般紙・スポーツ紙を購読していた。私たちは新聞を読んでは語り合い、編集部にいるような、でもいないような雰囲気だった。生活から新聞と雑誌を除いてしまえば何も残らないのでは、とも思えた。話すことも歩くこともままならない今になっても尚、富岡さんは新聞をめくっている。たとえそれが機械的にではあっても。
敬服を帯びた「どうも」、もしくはわずかに不満を抱いた「どうも」、私は彼が新聞をめくりながら一言「どうも」と言ってくれはしまいかとどれだけ願ったろう。しかしその声を聞くことは最後まで叶わなかった。
関連記事:
 その28 清水美和さん : 文革の影響を受けた記者
その28 清水美和さん : 文革の影響を受けた記者
 その27 大野信行さん:リーマンショックをきっかけに
その27 大野信行さん:リーマンショックをきっかけに
 その26 安藤裕康さん : 外交官から転身して
その26 安藤裕康さん : 外交官から転身して
 その25 山名健司さん : 日中が共有できる経験から
その25 山名健司さん : 日中が共有できる経験から
 その24 坂東玉三郎さん : 女形の極みから
その24 坂東玉三郎さん : 女形の極みから
 その23 本田雅一さん : フリーランスジャーナリストとしてのスピリット
その23 本田雅一さん : フリーランスジャーナリストとしてのスピリット
 その22 石島幹也さん:メイクの可能性
その22 石島幹也さん:メイクの可能性
 その21 森下洋子さん : 40数年前の衣装とともに
その21 森下洋子さん : 40数年前の衣装とともに
 その20 後藤雄三さん:環境保護と新エネルギーの可能性、そして困惑
その20 後藤雄三さん:環境保護と新エネルギーの可能性、そして困惑
 その19 野本正明さん : 日立の考えるスマートな次世代都市とは
その19 野本正明さん : 日立の考えるスマートな次世代都市とは
 その18 武田勝年さん:社会貢献の新しいかたち
その18 武田勝年さん:社会貢献の新しいかたち
 その17 渡辺日出夫さん:展覧会場を避難所に
その17 渡辺日出夫さん:展覧会場を避難所に
 その16 早坂裕さん:宮城発・スプレー塗装の革新
その16 早坂裕さん:宮城発・スプレー塗装の革新
 その15 本田勝之助さん : 福島の復興のために
その15 本田勝之助さん : 福島の復興のために
 その14 及川久仁子さん : “千年鉄器”を作り続けて
その14 及川久仁子さん : “千年鉄器”を作り続けて
 その13 栗原小巻さん
その13 栗原小巻さん
 その12 山田洋次さん:あたたかい眼差しとともに
その12 山田洋次さん:あたたかい眼差しとともに
 その11 鈴木さん:神社の宮司
その11 鈴木さん:神社の宮司
 その10 野松先生と車
その10 野松先生と車
 その9 辻元清美さん:国内外の民間パワーを被災地に
その9 辻元清美さん:国内外の民間パワーを被災地に
 その8 斉藤裕さん:「家、企業、都市」の概念
その8 斉藤裕さん:「家、企業、都市」の概念
 その7 普段着の東京:去りゆくネットカフェ
その7 普段着の東京:去りゆくネットカフェ
 その6 光:大地震後に生まれた新しい命 ― 世代を繋いで ―
その6 光:大地震後に生まれた新しい命 ― 世代を繋いで ―
 その5 ワタナベさん :ハンカチ落とし―バブルのあとに残ったものは―
その5 ワタナベさん :ハンカチ落とし―バブルのあとに残ったものは―
 その4 『言論NPO』代表・工藤泰志さん:救援・甘いもの・ウーロン茶
その4 『言論NPO』代表・工藤泰志さん:救援・甘いもの・ウーロン茶
 林先生-地震と停電のなかで
林先生-地震と停電のなかで
 その2 仙台在住の主婦・小林(古城)三千代さん
その2 仙台在住の主婦・小林(古城)三千代さん
 その1 匿名
その1 匿名
投稿者について
ChenYan: 会社経営者 1960年北京生まれ。 1978年に大学に進学して日本文学を専攻した。卒業後に日本語通訳などをして、1989年に日本へ留学し、ジャーナリズム、経済学などを専攻し、また大学で経済学などを教えた。 2003年に帰国し、2010年まで雑誌記者をした。 2010年から会社を経営している。 主な著書は、「中国鉄鋼業における技術導入」、「小泉内閣以来の日本政治経済改革」など多数。