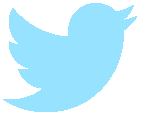第ニ回 壁

(写真)90年代の庶民の足『面的』
1996年8月から始まった長いながい留学生活。最初にぶつかった壁。それはやはり言葉の壁でした。
深圳での短期留学後、一年間必死で中国語の勉強に励みました。今と違い条件は限られてはいましたが、大学の授業、市民講座、家庭教師など利用可能なリソースは全て使い、中国語に触れない日は一日もありませんでした。それでも言葉の壁は高かった。
一人で降り立った北京首都国際空港。当然迎えなどありません。人だかりのタクシー乗り場はまるで戦場。なんとかタクシーに乗り込んだのですが、ここで「最初の壁」の登場です。擦り切れるまで繰り返し聞いたカセットテープの標準的な中国語と人間が話す生きた中国語のギャップは想像を遥かに超えていました。タクシー運転手が話す『儿化』の効いたこてこて北京語、内容の半分も理解できませんでした。
「次の壁」は更に高いものでした。1956年に制定された『普通话』と呼ばれる中国語の標準語は、「北京発音を標準に、北京方言で使用される単語を基礎とし、模範となる現代の口語小説を文法の手本とする言語」とされています。つまり、タクシーの運転手が話していた北京語と標準語はいわば兄弟、比較的聞き取りやすい中国語の範疇に入ります。
その北京語よりも強敵の「次の壁」とは、地方出身者の訛りの強い中国語でした。タクシーに揺られ何とか学校にたどり着きましたが、時間はすでに21時を回っており、事務所は開いていません。仕方なく直接宿舎に向かったのですが、そのフロントのお兄さんの訛りの強さと言ったら……結局ほとんど聞き取れないまま部屋に案内されました。
食堂にも「壁」が聳え立っていました。当時はコンビニなど全くなく、ファストフードのお店もほとんどありませんでした。結局学内外にある食堂やレストランに行くしかないわけです。その時代には電子辞書という便利なものは存在しません。分厚い辞書を片手に一人で食堂に通い、メニューと辞書をにらめっこ。当時のメニューには写真などありませんし、しかも中華料理の多くが、字面からは何なのか想像できないのです。
『宫保鸡丁』?「お宮を保護する?はぁ?鶏が?」
『鱼香肉丝』?「魚と肉か?何の香り?」
結局知っている食べ物と言えば『炒饭(チャーハン)』くらい。毎日毎日メニューと辞書をにらめっこしては、最後に注文するのはいつもチャーハン。そんな私を不憫に思ってくれたのか、ついに食堂のお姉さんが声をかけてくれました。これが美味しいよ、と勧めてくれたのが
『西红柿炒鸡蛋』
「美味い!!鶏卵とトマトを炒めているだけなのに!」
お腹も心も満たされ、とってもご満悦の私。この『炒饭』+『西红柿炒鸡蛋』セットが数日続いたのは言うまでもありませんね。
関連記事:
 最終回 人生の目標
最終回 人生の目標
 第二十四回 目標設定の大切さ
第二十四回 目標設定の大切さ
 第二十三回 伸び悩みは進歩の証拠
第二十三回 伸び悩みは進歩の証拠
 第二十二回 スタートダッシュの大切さ
第二十二回 スタートダッシュの大切さ
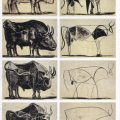 第二十一回 名作『SLAM DUNK』に学ぶ基礎の大切さ
第二十一回 名作『SLAM DUNK』に学ぶ基礎の大切さ
 第二十回 話題をつくろう
第二十回 話題をつくろう
 第十九回 モノマネ学習法
第十九回 モノマネ学習法
 第十八回 好きこそ物の上手なれ
第十八回 好きこそ物の上手なれ
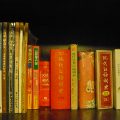 第十七回 語学恋愛論
第十七回 語学恋愛論
 第一六回 街は大きな教室
第一六回 街は大きな教室
 第十五回 学
第十五回 学
 第十四回 北京のおふくろの味
第十四回 北京のおふくろの味
 第十三回 食
第十三回 食
 第十二回 住~学外編~
第十二回 住~学外編~
 第十一回 住~学生寮編~
第十一回 住~学生寮編~
 第十回 留学生の友人
第十回 留学生の友人
 第九回 知己(3)
第九回 知己(3)
 第八回 知己(2)
第八回 知己(2)
 第七回 知己(1)
第七回 知己(1)
 第六回 室友
第六回 室友
 第五回 老師(2)
第五回 老師(2)
 第四回 老師(1)
第四回 老師(1)
 第三回 負けず嫌い
第三回 負けず嫌い
 第一回 私の人生を変えた留学
第一回 私の人生を変えた留学
投稿者について
Yusaku Nishimura: 対外経済貿易大学副教授 2010年6月に中国の経済金融系重点大学である対外経済貿易大学で経済学博士を取得し、同大学国際経済研究院で専任講師として採用される。 2013年1月より同大副教授。日中両国でのコラム執筆や講演活動も精力的におこなっている。 中国の外国人の大学教員の立場は、自国の言葉で教える非常勤講師か、海外の大学教員でありながら中国でも講義する客員教員が一般的。日本人を中国人枠での専任講師として採用するのは極めてまれで、人民日報やChina Dailyなどでも大きく紹介された。
- 大学教育の現場から4「私の学生指導」 BBパートナーリレーコラム「日中コミュニケーションの現場から」第6週 / 0 Comments
- 大学教育の現場から3「第三回 北東アジア学生ラウンドテーブル@国際教養大学」 BBパートナーリレーコラム「日中コミュニケーションの現場から」第6週 / 0 Comments
- 大学教育の現場から2 くまモン座@北京 BBパートナーリレーコラム「日中コミュニケーションの現場から」第5週 / 0 Comments
- 大学教育の現場から1「恋愛観の世代間格差」 BBパートナーリレーコラム「日中コミュニケーションの現場から」第6週 / 0 Comments
- 第一回 私の人生を変えた留学 / 0 Comments