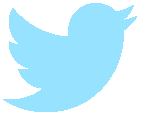特派員のひとりごと第2回 「歴史」をめぐる戦い

突然ですが皆さんは「9月18日」が何の日か知っているだろうか?
私も赴任前は知らなかったが、「9月18日」は、1931年に、満州事変のきっかけとなった、柳条湖事件が起きた日だ。「918」といえば、中国人にはピンとくるが、日本人になじみは薄い。また「7月7日」も、七夕だけではない。日中戦争のきっかけとなった盧溝橋事件が起きた日で、これも中国人なら知っている。
というわけで今回は、中国人と日本人で認識が全く異なる「歴史」の話を述べたいと思う。
中国外務省の報道官は、日本に対してほぼ毎日「歴史を正視せよ」と言い続けている。「9月18日」に何が起きたかを知らない日本人の態度は、彼らから見れば「侵略の過去を忘れ、歴史を正視しようとしない」態度となるのだろう。
この発言からもわかるように、中国は日中間の対立の舞台を、「島の問題」から、「歴史の問題」へと、大きく拡大しようとしている。特に安倍総理が靖国神社に参拝した去年12月以降は、「歴史戦」という言葉が、新聞紙面を飾ることも多くなった。
「歴史戦」とは、簡単に言うと、戦争の加害者であり敗者である日本と、被害者であり勝者である中国、という構図の下で、中国に有利な世論を作り上げようという戦いだ。過去を変えることはできないので、中国側に非常に有利な論理構成なのだが、その歴史戦の舞台は多岐にわたる。
まずは「司法」の場での歴史戦だ。これまでは裁判所が受理してこなかった、日中戦争時の強制連行に対する損害賠償請求訴訟を、今年に入って初めて北京の法院が受理し、同様の訴訟が相次いでいる。中国でも、「司法の独立」が建前だが、政治的な判断が訴訟受理につながったことは想像がつく。
次に、「メディア」を巻き込んだ歴史戦だ。中国外務省は今年に入って、外国人記者向けの歴史問題取材ツアーを、3回も開催している。1回目は遼寧省の捕虜施設などに、2回目は「南京大虐殺記念館」に、外国人記者を招き「歴史を正視」させた。さらに3回目は、吉林省長春市の「吉林省資料館」の取材機会を設け、私もその取材に参加した。
長春市は旧満州国の首都だった街で、日本のお城のような旧関東軍司令部がそのまま残っている。関東軍は終戦時に自分たちの資料を焼却したり、土に埋めたりしたのだが、1950年代に、その資料が地中から発見された。そしてその資料の一部が今回、「日本の戦争犯罪の証拠」として、外国人記者に公開されたのだ。かなり以前に発見された資料が、60年以上も経ったいま公開されるというのも、「歴史戦」の一環とみれば納得がいく。
さらに、「国際社会」を舞台にした歴史戦も展開されている。一例が、1月に完成した「安重根記念館」だ。伊藤博文を暗殺した安重根は、韓国の歴史ではヒーローだが、日本の歴史では犯罪者だ。第三国の中国は、今まで表立って安重根を評価してこなかったが、朴槿恵大統領の提案を習近平国家主席が受け入れ、「愛国の義士」として、急ピッチで記念館を完成させた。「歴史戦」における、韓国との連携が始まったといえる。また、デンマークの女王が「南京大虐殺記念館」を訪問したことも、国際社会を舞台とした歴史戦の一端だ。
では、このように多岐にわたる「歴史戦」の中で、日本は何をすべきなのだろうか?私見だが、自らの立場を繰り返し愚直に説明し、国際社会の理解を得ることが、遠回りに見えて、一番確実な方法なのだろうと思う。
その好例が、4月に日本大使館の堀之内秀久特命全権公使が出演した、香港フェニックステレビの討論番組だ。ほかの出演者がほぼ中国人という「完全アウェー」状態で、堀之内公使は日本の平和主義が戦後一貫していることや、軍国主義化する懸念は不要だといったことを、流ちょうな中国語でジョークも交えながら力説した。テレビ番組の出演は、悪意を持って編集される可能性があるため、リスキーな行為ともいえるが、今回の番組は編集も非常に中立的で、出演する意義は大きかったと思われる。
最後に、「歴史戦」そのものをなくす方法を、提案したいと思う。
そもそも、歴史を正視することは難しい。正視というのは正しく見ることだが、正しいか間違っているかは非常に主観的だからだ。先に述べた関東軍の資料であっても、立場によっては解釈が180度変わってくる。そこで私は、吉林省の資料館で、担当者にこう質問してみた。
「これらの資料は中国側だけ研究したのですか?日本と共同で研究したのですか?」
担当者の答えは、「中国側だけで研究したもので、今後も共同研究の予定はない」というものだった。毅然とした態度だったが、それは学術的な態度というよりは、政治的な態度のように見えた。
共同で歴史を研究し、日中で一つの結論を得ることができれば、歴史戦の火種は消える。しかし、歴史戦の舞台を最大限利用しようとする現在の中国においては、それはできない相談なのだろう。
私は日本人は、過去の行為をもっときちんと知った上で、反省すべき点はしっかり反省すべきだと思っている。一方中国の人には、過去の行為だけを見るのではなく、これからの未来の可能性にも、目を向けてほしいと思う。
過去にこだわりすぎる中国と、過去にこだわらなさすぎる日本。お互いが「正視」する歴史の距離を、一歩ずつ縮めていった上で、歴史戦という不毛な戦いが一刻も早く終わることを、心から望んでいる。
関連記事:
 特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
 特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
 特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
 特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
 特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
 特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
 特派員のひとりごと 第22回 威信をかけたG20
特派員のひとりごと 第22回 威信をかけたG20
 特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
 特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
 特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
 特派員のひとりごと 第18回 突然の失脚劇
特派員のひとりごと 第18回 突然の失脚劇
 特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
 特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
 特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
 特派員のひとりごと第14回 沈んだ「東方の星」
特派員のひとりごと第14回 沈んだ「東方の星」
 特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
 特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
 特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
 特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
 特派員のひとりごと第9回 3年ぶりの25分
特派員のひとりごと第9回 3年ぶりの25分
 特派員のひとりごと第8回 黄色いリボンと傘の革命
特派員のひとりごと第8回 黄色いリボンと傘の革命
 特派員のひとりごと第7回 東南アジア取材記 その2
特派員のひとりごと第7回 東南アジア取材記 その2
 特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
 特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
 特派員のひとりごと第4回 民主と自由
特派員のひとりごと第4回 民主と自由
 特派員のひとりごと第3回 命の重さ
特派員のひとりごと第3回 命の重さ
 特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
投稿者について
Noriaki Tomisaka: 1976年8月27日福井県生まれ(辰年、乙女座、B型) 1994年 京都大学法学部入学 1999年 テレビ朝日入社 朝のワイドショー(「スーパーモーニング」)夕方ニュース(「スーパーJチャンネル」)などのAD・ディレクターを担当 2007年〜 経済部にて記者職を担当 農林水産省、東京証券取引所、財務省などを取材 2011年9月〜 北京・中国伝媒大学にて留学生活を開始(〜2012年夏まで)