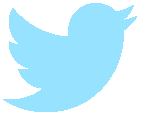特派員のひとりごと第8回 黄色いリボンと傘の革命

9月30日早朝、北京・天安門広場では、厳粛な雰囲気の中、「烈士記念日」の式典が行われていた。
習近平国家主席をはじめ、7人の最高指導部が、「人民英雄記念塔」に献花し、黙とうを捧げる。中華人民共和国の成立という「革命」に、命をささげた烈士たちを追悼する行事で、今年から国家の記念日に格上げされた。国営テレビで全国に生中継されるこの式典こそ、共産党が政権を握り続ける正統性を確認する、重要な行事といえる。
同じころ、遠く南に離れた香港では、本来ならば勉学に励むべき学生たちが、目抜き通りに座り込み、もう一つの「革命」を戦っていた。彼らは中国の国会にあたる全人代が制定した、香港行政長官選挙の方法を不服として、座り込みを始めたのだ。10月1日の国慶節から、金融の中心である「セントラル」を占拠する計画だったが、一部の学生が前倒しで、政府庁舎前の占拠を強行。香港警察は催涙弾で抵抗するなど、一触即発の状況が続いていた。
私が香港入りしたのはこの9月30日。早朝、人民大会堂での取材を終え、その足で香港へ向かった。着いた途端に「失敗した」と思ったのは、まず自分の服装だ。長袖シャツに長ズボン、さらには長袖ジャケットを羽織って香港に到着したのだが、まあ蒸し暑い。さらに言葉は広東語なので、標準の中国語はなかなか通じない。やっとの思いでたどり着いたホテルでは、大陸とコンセントの形がまったく違うことに気づき、あわててフロントでアダプターを借りる羽目に。「一国二制度」とはいえ、「ここは外国だな」と思ったのが、偽らざる第一印象だ。
ホテルに荷物を置き、まずはデモ隊の占拠現場を取材した。普段は歩けない車道のど真ん中を歩き、現場に向かう。近づくにつれ、黒シャツに黄色いリボンの「ユニフォーム」に身を包んだ学生たちが増え、喧騒が大きくなる。シンボルである「傘」を手にした学生も多い。政府庁舎前の大通りには、数万人が集まっていただろうか。ものすごい熱気に圧倒される。ただ驚いたのは、非常に秩序正しくデモが行われていたことだ。食糧や水を配る補給所も設けられ、警察の催涙弾に対抗するため、ゴーグルや雨合羽が整然と配られていた。
彼らは何に反対し、何を求めているのか。足が水ぶくれになるまで歩き、路上に一緒にしゃがみこんで、何十人もの人に話を聞いた。そもそも英国植民地時代、香港人による「民主」は認められていなかった。そのことをもって、新しい選挙制度は、「香港の民主にとって大きな一歩だ」と、中国政府は強調する。しかし、その選挙に立候補できるのは、親中派が多数を占める「選挙委員会」に指名された人物だけだ。そうなると、おのずと中国にものが言えない人物ばかりが立候補することになり、民主選挙の意味がないというのが学生たちの主張だ。
そしてその先に待っているのは、「香港の中国化」だと、一部の学生は強調する。フェイスブックがつながる香港、敏感な政治記事も新聞に載せられる香港、香港を香港たらしめてきたこれらの「自由」が、徐々に失われてしまうことに、学生たちは本能にも近い恐怖を感じていた。
客観的にみて、学生たちの運動が成果を勝ち取る可能性は極めて低いと思われる。中国政府は現時点では、事態の処理を香港政府に任せて、静観を決め込んでいるが、全人代の決定を覆す可能性はゼロに等しい。「座り込み」という不当な手段に屈し、譲歩したとなれば、中国全土で同様の事態が起こり得るからだ。無制限に「民主」を認めることは、すなわち共産党政権への挑戦を許すことになる。それだけは現政権も、絶対に避けたいと思っているはずだ。
ただし、天安門事件の時のように、すぐに強制排除はしないだろう。11月に北京APEC開催を控える中、学生たちを強制排除すれば、国際的な非難は免れない。デモの発生直後、催涙弾を使用し、学生たちに同情する世論を作ってしまった反省もある。香港政府は今後、学生と対話を続けながら、長期戦に持ち込み彼らを疲弊させ、世論を「反学生」に誘導したうえで、大手を振って「排除」に踏み切るだろう。
あらかじめ、「失敗が約束された」“革命”。黄色いリボンと傘の“革命”は、そう運命づけられているのかもしれない。その時「革命」は、単なる「騒乱」と名前を変え、刑事裁判の対象となるのだろう。
それでも私は、今回の行動は、決して無駄ではないと信じたい。一週間取材を続けて、デモ現場の至る所で、学生への応援メッセージが増え続けるのを、この目で確認した。たとえ不十分なものでも、「民主」制度が導入されれば、そこから突破口を見つけるやり方もあるはずだ。学生たちが本気で「自由」を求め、それを大多数の香港市民が支持した。その事実の重みを、香港政府と、大陸の中国政府に刻み付けることができたとすれば、この“革命”には、きっと大きな意味があったということになるはずだ。
関連記事:
 特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
 特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
 特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
 特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
 特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
 特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
 特派員のひとりごと 第22回 威信をかけたG20
特派員のひとりごと 第22回 威信をかけたG20
 特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
 特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
 特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
 特派員のひとりごと 第18回 突然の失脚劇
特派員のひとりごと 第18回 突然の失脚劇
 特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
 特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
 特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
 特派員のひとりごと第14回 沈んだ「東方の星」
特派員のひとりごと第14回 沈んだ「東方の星」
 特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
 特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
 特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
 特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
 特派員のひとりごと第9回 3年ぶりの25分
特派員のひとりごと第9回 3年ぶりの25分
 特派員のひとりごと第7回 東南アジア取材記 その2
特派員のひとりごと第7回 東南アジア取材記 その2
 特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
 特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
 特派員のひとりごと第4回 民主と自由
特派員のひとりごと第4回 民主と自由
 特派員のひとりごと第3回 命の重さ
特派員のひとりごと第3回 命の重さ
 特派員のひとりごと第2回 「歴史」をめぐる戦い
特派員のひとりごと第2回 「歴史」をめぐる戦い
 特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
投稿者について
Noriaki Tomisaka: 1976年8月27日福井県生まれ(辰年、乙女座、B型) 1994年 京都大学法学部入学 1999年 テレビ朝日入社 朝のワイドショー(「スーパーモーニング」)夕方ニュース(「スーパーJチャンネル」)などのAD・ディレクターを担当 2007年〜 経済部にて記者職を担当 農林水産省、東京証券取引所、財務省などを取材 2011年9月〜 北京・中国伝媒大学にて留学生活を開始(〜2012年夏まで)