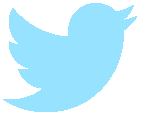特派員のひとりごと 第18回 突然の失脚劇

習近平政権が発足して以降、徹底して進めているのが「反腐敗」運動だ。
上はかつての最高指導部の面々から、下は市や村のレベルの役人まで、新聞やテレビでは、連日のように幹部たちの失脚のニュースが流れている。
処分を受けた党員の数は、2015年だけでおよそ3万4000人。
というわけで、たいていの失脚のニュースには驚かなくなっているのだが、移動中の車の中で知ったこのニュースには、久々に驚いた。
スマホの速報ニュースの画面には、こう書かれていたのだ。
「国家統計局長の王保安が、厳重な規律違反の疑いで、現在組織的な調査を受けている」
なんと、失脚したのはGDP(国内総生産)などの重要統計を担当する国家統計局長で、しかも、数時間前まで、目の前にいた人物ではないか…
突然の失脚劇の日付は1月26日だった。
その1週間前、1月19日に王局長によって発表された2015年のGDP成長率は、6.9%と、7%を割り込み、天安門事件の影響を受けた1990年以来の低水準となった。これまで世界経済を引っ張ってきた中国の成長に「かげり」が見え始めたとして、世界各国のメディアは大きく取り上げたが、それが王局長には気に入らなかったのかもしれない。GDPを発表したわずか一週間後に、メディア向けの記者会見をもう一度開くと言ってきたのだ。
午後3時から統計局の会議室で開かれた会見では、王局長は終始上機嫌だった。会見開始前には、メディアのテーブルを回って一人一人と握手をし、会見中は中国経済について、大演説を繰り広げた。習近平国家主席の言葉を引用し、様々な政策について語る王局長の姿をみて、「統計局長なのに、まるで首相気取りだなあ」と思ったのが、いまでも記憶に残っている。会見後も、報道陣のぶら下がり取材を気さくに受けていたが、取り巻きに促されて部屋を出て行った。その際の一言は、意味深にもこんな言葉だった。
「これから会議があるので、私はもう行きます」
失脚が発表されたのは、それからわずか2時間後のことである。
統計局長の失脚の理由は、まだ明らかになっていない。ただし、証券会社で幹部を務めていた妻も調査を受けているというから、インサイダー取引がらみの話かもしれない。いずれにしても、ただでさえ低い中国の統計の信頼度が、また下がってしまったのは、まぎれもない事実だ。そして、自信満々だった統計局長の突然の失脚は、いみじくも、今年の中国経済の先行きを、暗示しているように思えた。何しろ、今年の中国経済は、不安要素のオンパレードなのだ。
まずは、乱高下が続く上海の株式市場だ。去年1月に3200ポイントから始まった上海総合指数は、6月には5200ポイント近くまで上昇した。しかし、そこからは下り坂で、今年の2月5日の終値は2763ポイントと、半値近くまで値下がりしている。まさにジェットコースターだが、そんな上海の株式市場について、とある政府高官は、「実体経済を全く反映していないから、気にするだけ無駄だ」と言い放った。投資家に「株主」といった意識は希薄で、どこまでも「ばくち」感覚なのかもしれない。そんな上海市場が、世界経済を一喜一憂させるのだから、大変な時代になったものだ。
さらに、不安定な人民元の為替レートも、中国経済の不安要素だ。去年8月に、政府が定める人民元の基準値を、市場の実態に近づける制度が導入されたが、それ以降、人民元安が大幅に進行した。そのため、大規模な元買い介入が行われたとみられ、世界一の規模を誇る中国の外貨準備高も、大幅に減少している。世界の基軸通貨の座を狙う人民元だが、その道のりは決して平たんとは言えないだろう。
そして最も大きな不安要素が、不動産の在庫の積み上がりと、鉄鋼や石炭などの生産過剰だ。政府は過剰な生産能力の調整を進める予定で、その過程で数万人の失業者が出る可能性も指摘されている。李克強首相は「大衆による起業、大衆によるイノベーション」をスローガンに掲げ、インターネットなどを利用した新たな産業が勃興することで、それらの失業者たちを吸収できるとしている。
しかし、本当にそんなバラ色の解決策があるのだろうか?
私が去年取材した、広東省で零細工場を経営する男性は、苦しい胸の内をこう明かしてくれた。
「40を過ぎてとても新しい仕事なんてできない。先が見えなくても、この仕事をつづけていくしかない」
一つだけ言えるのは、これから中国が経験するだろう改革は、
昔の日本で流行ったキャッチコピーのように「痛みを伴う改革」になるだろうということだ。
「みんなが貧乏」だった計画経済の時代から、「先に富める者が富む」改革開放の時代へと、中国経済は猛スピードで駆け抜けてきた。
その過程で、富める者と貧しい者の格差はどんどん開いていったが、それでも「次は自分の番」との思いが、社会に満ち溢れていた。
しかし、もうそのスピードは期待できない。統計局長は変わっても、経済の実態は何も変わらない。
2016年も、習近平政権は、難しいかじ取りを迫られ続けることになる。
関連記事:
 特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
 特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
 特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
 特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
 特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
 特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
 特派員のひとりごと 第22回 威信をかけたG20
特派員のひとりごと 第22回 威信をかけたG20
 特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
 特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
 特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
 特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
 特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
 特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
 特派員のひとりごと第14回 沈んだ「東方の星」
特派員のひとりごと第14回 沈んだ「東方の星」
 特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
 特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
 特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
 特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
 特派員のひとりごと第9回 3年ぶりの25分
特派員のひとりごと第9回 3年ぶりの25分
 特派員のひとりごと第8回 黄色いリボンと傘の革命
特派員のひとりごと第8回 黄色いリボンと傘の革命
 特派員のひとりごと第7回 東南アジア取材記 その2
特派員のひとりごと第7回 東南アジア取材記 その2
 特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
 特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
 特派員のひとりごと第4回 民主と自由
特派員のひとりごと第4回 民主と自由
 特派員のひとりごと第3回 命の重さ
特派員のひとりごと第3回 命の重さ
 特派員のひとりごと第2回 「歴史」をめぐる戦い
特派員のひとりごと第2回 「歴史」をめぐる戦い
 特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
投稿者について
Noriaki Tomisaka: 1976年8月27日福井県生まれ(辰年、乙女座、B型) 1994年 京都大学法学部入学 1999年 テレビ朝日入社 朝のワイドショー(「スーパーモーニング」)夕方ニュース(「スーパーJチャンネル」)などのAD・ディレクターを担当 2007年〜 経済部にて記者職を担当 農林水産省、東京証券取引所、財務省などを取材 2011年9月〜 北京・中国伝媒大学にて留学生活を開始(〜2012年夏まで)