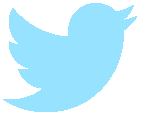特派員のひとりごと 第22回 威信をかけたG20

9月2日に到着した杭州の街からは、普段の賑わいが全く消えていた。マクドナルドも、ケンタッキーも、地元の食堂も、ほとんどの店が閉店している。主要道路の交差点には、警察の車両が停まり、銃を持った警官が辺りを見回している。不審者の侵入を防ぐためだろうか、マンホールまでがシールで封鎖されていた。この地で開催される重要会議、G20(=主要20か国・地域)サミットを控え、厳戒態勢が敷かれていたのだ。
「G20の期間中に旅行に行って杭州市民の身分証を見せると、全国どこの観光地でも入場料が無料らしいよ」
真偽のほどは不明だが、現地のドライバーが教えてくれた情報だ。大気汚染を防ぐために杭州市周辺の工場は全て閉鎖され、一般のオフィスもすべて休日となった。突然の連休が与えられた市民には、旅行に行くことが「奨励」されているのだという。
もちろん、我々マスコミも、自由に移動することはできない。ホテルに入る際には「安全検査」、移動のバスに乗る際には「安全検査」、どこへ行っても、「安全検査」…「取材じゃなくて、安全検査にきたみたいだ」というのは、各国のマスコミ共通のグチである。
「やりすぎ」なくらい気合が入っていた理由は、やはり習近平国家主席が込めた強い思いにあるだろう。
「現在の状況下で、G20は国際経済協力の場としての役割をより大きく発揮すべきだ」
習主席は会議で何度も強調した。そもそもG20サミットは、2008年にアメリカで起きたリーマン・ショックをきっかけに創設された。未曾有の大危機に対して、先進国が手も足も出ない中、4兆元の公共投資で世界経済を支えた中国は、「救世主」としてもてはやされた。自らを「世界最大の発展途上国」と位置付ける中国は、これまでの先進7か国=G7中心の世界秩序を、作りかえることを目論んでいる。そのためにも、中国が存在感を示せるG20という場所を、G7に代わるものに、仕立てあげたい思惑があるのだろう。
また、開催地の杭州も、習主席には思い入れの深い場所だ。習主席は40代後半から50代前半の、まさに脂の乗り切った6年間を浙江省のトップとしてこの町ですごし、中央政界で駆け上がっていくための重要なステップとした。開幕式では「この街の山も草木も、風土も人情も、知り尽くしている」と彼自身が述べている。「自らの地盤に、大イベントを誘致したい」という思いは、古今東西、どこの政治家でも同じなのだろう。
そんな習主席の思いをみな、わかりすぎるほどわかっているから、「どうしても失敗できない」という思いばかりが強くなる。経済分野を担当するある日中関係筋は、「中国のどの官庁に行っても、G20が終わるまではほかの仕事はできないと、けんもほろろに突き返される。仕事にならないよ」とぼやいていた。
「失敗は許されない」から、どうしても記者の管理もきつくなる。特にいうことを聞かない外国記者ならなおさらだ。今回G20に先立ってB20というビジネス界のトップを招いたフォーラムがあったのだが、そこでひと悶着があった。取材を許された記者たちが、さらに2つに選別され、外国記者らは、習主席の演説会場に入れないことが判明したのだ。その演説が目当てなのに、入れないという虚脱感…記者たちは、何時間も映画館のような場所に押し込められ、何もすることがなかった。イライラして担当者に怒りをぶつける外国記者もいたが、もちろん何も解決しない。事前の告知をより徹底すれば、このようなすれ違いは起きないのだろうが、その辺の段取りはまだ苦手なのだろう。
会議自体は、習主席が恐れていた「南シナ海」の問題が大きく取り上げられることもなく、無難に幕を下ろした。首脳宣言は相変わらず総花的だが、G20という会議の性質上、それは仕方がないのかもしれない。むしろ首脳たちが直接会って、様々な話題について意見交換をすることが大切なのだろう。中国のマスコミは翌日から「大成功」を、大々的に宣伝している。
ただ、私自身にとっては、残念なことがいくつかあった。一番残念だったのは、G20に合わせて実施された日中首脳会談だ。安倍総理と習主席が握手する場面の背景に、両国の国旗がなかったのだ。日本に対して仲の良いところを見せると、弱腰と見られることを恐れての、国内向けの対応なのだろうが、世界を相手にしているG20の舞台でそんなことをやるのは、あまりにも器が小さいのではないだろうか?
また、テレビ朝日の中継の途中に、音声が乱れるという場面もあった。中国当局による妨害があったかどうかはわからないが、都合の良いところだけ見せるのではなく、ありのままの姿を見せるだけの度量の大きさを、中国当局には求めたいと思う。
「面倒くさい国ですね」
安倍総理の同行で、東京から取材に来ていた記者がつぶやいた言葉が印象的だ。たしかに今は、「面倒くさい国」だが、少しずつでも風通しが良い国になってくれることを、願ってやまない。
関連記事:
 特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
 特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
 特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
 特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
 特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
 特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
 特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
 特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
 特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
 特派員のひとりごと 第18回 突然の失脚劇
特派員のひとりごと 第18回 突然の失脚劇
 特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
 特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
 特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
 特派員のひとりごと第14回 沈んだ「東方の星」
特派員のひとりごと第14回 沈んだ「東方の星」
 特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
 特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
 特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
 特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
 特派員のひとりごと第9回 3年ぶりの25分
特派員のひとりごと第9回 3年ぶりの25分
 特派員のひとりごと第8回 黄色いリボンと傘の革命
特派員のひとりごと第8回 黄色いリボンと傘の革命
 特派員のひとりごと第7回 東南アジア取材記 その2
特派員のひとりごと第7回 東南アジア取材記 その2
 特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
 特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
 特派員のひとりごと第4回 民主と自由
特派員のひとりごと第4回 民主と自由
 特派員のひとりごと第3回 命の重さ
特派員のひとりごと第3回 命の重さ
 特派員のひとりごと第2回 「歴史」をめぐる戦い
特派員のひとりごと第2回 「歴史」をめぐる戦い
 特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
投稿者について
Noriaki Tomisaka: 1976年8月27日福井県生まれ(辰年、乙女座、B型) 1994年 京都大学法学部入学 1999年 テレビ朝日入社 朝のワイドショー(「スーパーモーニング」)夕方ニュース(「スーパーJチャンネル」)などのAD・ディレクターを担当 2007年〜 経済部にて記者職を担当 農林水産省、東京証券取引所、財務省などを取材 2011年9月〜 北京・中国伝媒大学にて留学生活を開始(〜2012年夏まで)