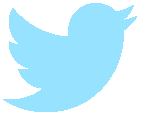特派員のひとりごと第3回 命の重さ

この1カ月の間に、新疆ウイグル自治区の中心都市・ウルムチで、2件の爆発事件が起きた。
1件目はメインターミナルであるウルムチ駅を出てすぐの駅前広場で、2件目は公園近くの朝市で発生。いずれも人が多く集まる場所を狙った犯行で、複数の容疑者がその場で自爆し、死亡している。1件目では2人が自爆し、1人の市民が死亡、2件目は4人が自爆し、39人もの市民が犠牲になった(数字は5月26日現在)。
私は1件目の事件が起きた直後に、ウルムチに入って取材をした。駅前広場は銃を持った特殊警察が闊歩し、カメラを出して少し撮影するのも、はばかられるくらいの緊張感があった。そこで我々は外の取材をいったんあきらめ、警備の目をかいくぐりながら、周辺の建物を中心に聞き込みを続け、爆発現場の目の前の旅館を取材することに成功した。2階の部屋の窓ガラスは窓枠から外れ大破しており、衝撃の激しさを物語っていた。旅館の主人は、血まみれで運ばれていく女性を目撃したという。 この1件目の事件は、習近平国家主席がウルムチ市を視察した直後に起きた。完全にメンツをつぶされた習近平指導部は、「テロリストを断固として打倒する」という声明を発表。事件の早期解決と再発防止を誓っていたが、2件目の事件を防ぐことができなかった。しかも2件目の事件も、習主席が上海の国際会議で高らかと、「アジアの安全観」を打ち出した直後の犯行だ。2度までも、顔に泥を塗られた習主席は、「テロとの戦争」を宣言、なりふり構わずテロ対策を強化する姿勢を示し、まさに「いたちごっこ」の様相を呈している。
新疆ウイグル自治区でここまでテロが頻発する理由として、少数民族であるウイグル族と、漢族の対立が理由に挙げられる。ウイグル族の「自治区」と言いながら、トップは常に中央から派遣されてくる漢族で、ウイグル族は最高でもナンバー2止まり。街中には漢字の看板が乱立し、中華料理の店もどんどん作られている。そのような境遇を不満に思っている一部のウイグル族が、過激なイスラム思想に影響され、テロを起こしているという説明だ。
もちろん、どんな理由があれ、無辜の人を巻き添えにするテロが許されていいはずはない。しかも、このようなテロが起こるたびに、漢族とウイグル族の対立はますます深まっていく。北京でも、人ごみの中にウイグル族がいるだけで、恐怖を感じると、真顔で語る漢族の知り合いは多い。特に屋台でスイカや羊の串焼きを売っている人たちは、刃物を持っていることが多いから、彼らがこちらに向かってこないかと、気が気でないのだという。
こうした偏見が、また差別を産み、そしてさらなるテロの悲劇を生む。まさに「負のスパイラル」だ。テロリストたちは自らの「命の価値」を顧みず、せっせと「負のスパイラル」を大量生産している。自らは「ジハード」が終われば天国に行けると思っているのだろうが、死後の世界のことなど誰もわからない。というかたぶん、死後の世界など存在しないだろうから、死んだら死ぬだけのことで、それ以上の意味は何もないのだろう。その上で周りに迷惑をかけ、不幸にしているのだから、全く意味のない人生を送っていることになる。
しかし、テロリストのエゴのために犠牲になる一般市民の人たちは違う。彼らは毎日泣き笑い、一生懸命生活してきた人たちである。彼らの「命の価値」は、決して奪ってはいけない貴重なものだ。日本で事件や事故の報道をするとき、被害者についてどう伝えるかは、記者なら誰しも直面する問題だろう。彼らの生前の姿をしっかりと伝えることで、我々は命の尊さを伝えることができると、私は先輩から教わった。遺族の方の家のピンポンを押すのは、非常に躊躇することだ。しかし、前に述べたような理由があるからこそ、我々は遺族の方に許していただける範囲で、被害者の方の実名を出させてもらい、生前の様子を紹介する。
しかし、中国では事情が違う。今回の事件にしても、犯行を起こしたとされる容疑者の名前は公表されたものの、39人の被害者に関しては、性別も、年齢も、民族も、名前も、何一つ公表されないのだ。人の命は「39」という数字だけで測れるものではない。事件の悲惨さを伝える上でも、被害者の情報を伝える意義は大きい。たとえば被害者がウイグル族であれば、テロリストたちは全く無差別に犯行を起こしたことがわかり、彼らの大義名分も色あせることになる。(ちなみに、南京大虐殺の資料館などでは、犠牲者の方について、非常に細かい資料を用意し、実名を挙げて展示しているので、中国政府としても、TPOで使い分けているのかもしれない)
民族問題が絡んだ事件など、敏感なテーマに関しては、我々外国人記者は、なかなか自由に取材をすることは難しい。ただ、何とか犠牲者の人の肉声を伝わるような、そんな事件報道を目指せればと思う。
関連記事:
 特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
 特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
 特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
 特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
 特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
 特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
 特派員のひとりごと 第22回 威信をかけたG20
特派員のひとりごと 第22回 威信をかけたG20
 特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
 特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
 特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
 特派員のひとりごと 第18回 突然の失脚劇
特派員のひとりごと 第18回 突然の失脚劇
 特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
 特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
 特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
 特派員のひとりごと第14回 沈んだ「東方の星」
特派員のひとりごと第14回 沈んだ「東方の星」
 特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
 特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
 特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
 特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
 特派員のひとりごと第9回 3年ぶりの25分
特派員のひとりごと第9回 3年ぶりの25分
 特派員のひとりごと第8回 黄色いリボンと傘の革命
特派員のひとりごと第8回 黄色いリボンと傘の革命
 特派員のひとりごと第7回 東南アジア取材記 その2
特派員のひとりごと第7回 東南アジア取材記 その2
 特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
 特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
 特派員のひとりごと第4回 民主と自由
特派員のひとりごと第4回 民主と自由
 特派員のひとりごと第2回 「歴史」をめぐる戦い
特派員のひとりごと第2回 「歴史」をめぐる戦い
 特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
投稿者について
Noriaki Tomisaka: 1976年8月27日福井県生まれ(辰年、乙女座、B型) 1994年 京都大学法学部入学 1999年 テレビ朝日入社 朝のワイドショー(「スーパーモーニング」)夕方ニュース(「スーパーJチャンネル」)などのAD・ディレクターを担当 2007年〜 経済部にて記者職を担当 農林水産省、東京証券取引所、財務省などを取材 2011年9月〜 北京・中国伝媒大学にて留学生活を開始(〜2012年夏まで)