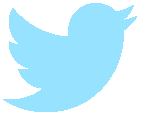特派員のひとりごと第7回 東南アジア取材記 その2

(前回までのあらすじ)
~~ミャンマー・ネピドーで開催された、ASEAN関連会合の取材を終え、北京に帰ろうとした矢先、バンコク支局長に呼び出された筆者。そこで、突然のカンボジア出張を命じられることとなる。~~
「カ、カンボジアですか?」
「そう。変な事件の取材だけど、頑張ってね」
「はあ、事件ですか?」
どうやら、タイで代理出産を通じて多くの子供を設けたとされる日本人男性が、カンボジアにいる可能性があるらしい。簡単に言うと、その男性を探してくれというミッションだ。
国際会議の取材から、奇妙な事件の取材へと、頭の着替えは大変だが、これも少人数で広範囲をカバーする特派員の醍醐味だ。
当然、着る服も足りないので、ネピドーのスーパーで下着を購入。その後、あわただしく空港へと向かった。
移動には予想以上に時間がかかった。朝にネピドーを出発し、ヤンゴンとバンコクで2回乗り換え、プノンペンにようやくついたのは午後11時過ぎ。しかも空港では早速、スーツケースが届いていないことが判明。さらに、深夜にチェックインしたホテルでは、エレベーター内で突然の停電に遭遇し、数分間閉じ込められる事態に…。やれやれ、プノンペン、なかなかの強敵である。
次の朝、仕方なく前の日と同じ服を着て、私たちクルーは取材を始めた。カメラマンはベトナム人、助手はカンボジア人の、3か国混成チームだ。
今回の案件で、日本人男性は、明確に法的な罪を犯しているわけではない。代理出産というのは、他人の受精卵を自らの子宮に入れ、代わりに出産する技術で、不妊治療の一環として行われている。
しかし、明らかに奇妙なのは、生まれた子供の数だ。一説には、男性は代理出産の技術を使って、16人もの子供の父親になっていたという。目的はなんなのか?疑問に思いながら、われわれは男性が登記していた会社住所周辺へと車を走らせた。そこで聞き込みを始めると、すぐに多くの目撃情報が集まった。
「子供を連れて歩いている姿を何度も見た」と、バイクタクシーの運転手。
「日本人のような子供もいたし、タイ人のような子供もいた」と、近所の人。
さらに、近くでハワイ料理店を営む若い女性は、疑惑の男性と、直接話したことがあった。
「男性は、良くも悪くも人畜無害な人という印象だった」と、彼女は話してくれた。
また、子供を連れてくることもあったが、母親らしき女性が一緒にいたことは、一度もなかったという。さらに、職業を尋ねた彼女に、男性は興味深い答えを返している。
「(職業は)さすらいのスナフキンだからって。それ以上は聞いてはいけないような感じだったので、聞くことはやめました」
スナフキンとは、漫画「ムーミン」に出てくる孤独を愛する旅人だ。それだけ多くの子供を持つとされながら、自らを根無し草に例える男性の心に、底知れぬさみしさを感じた瞬間だった。
その後もカンボジアで取材を続けたが、男性を見つけることはできなかった。この原稿を書いている時点で、男性はマスコミの前に姿を現しておらず、タイ警察が求めている事情聴取も、いまだ実現していない。
男性の目的はいまだ不明だ。しかし、私見だが、やはり少し無責任ではないかと感じる部分が大きい。
私にも2人の子供がいる。子育ては、非常に骨の折れる仕事だ。帰りがどんなに遅くても、次の朝早く起こされ、遊んでくれとせがまれる。2人だと、けんかをすることもあるし、公平に扱わないと、どちらかが泣き出すこともしょっちゅうだ。なだめてすかして、子供と一緒に親も成長していくというのが、本来の子育ての在り方だろう。
ただし男性には、そういう気持ちはなかったのではないだろうか?16人もの子供をいっぺんに持って、その子たち一人一人に愛情をもって接することができるとは、到底思えない。
また、子供の外見に対する証言も「日本人風」「タイ人風」と様々で、一致しない。妻とは別の複数の受精卵を使って出産をした可能性もあるが、そこは憶測の域を出ない。子供たちが大きくなれば、きっと自分たちの母親は誰かが、気になるだろう。また、同じ年のころの兄弟が16人もいることに、疑問も感じるだろう。男性は子供たちに、どう説明するつもりなのだろうか?
代理出産技術の進歩は、不妊で悩んでいる夫婦が、子供を持つことを可能にした。そのこと自体は、喜ぶべきことかもしれない。ただし、その技術を安易に利用することは、生命倫理の崩壊につながる恐れがある。テレビゲームのように、簡単に死んだり生き返ったりできる命は、この世にはない。男性には自らの行為ときちんと向き合い、子供に対して責任を取る義務がある。
そして何より大切なのは、代理出産を使って生まれてきた子供たちそれぞれが、かけがえのない命ということだ。彼ら、彼女たちをだれがどのように育てるのかも含めて、きちんとしたアフターケアが必要だろう。
北京特派員のカバー範囲は、かくも広いのである。
関連記事:
 特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
 特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
 特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
 特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
 特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
 特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
 特派員のひとりごと 第22回 威信をかけたG20
特派員のひとりごと 第22回 威信をかけたG20
 特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
 特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
 特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
 特派員のひとりごと 第18回 突然の失脚劇
特派員のひとりごと 第18回 突然の失脚劇
 特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
 特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
 特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
 特派員のひとりごと第14回 沈んだ「東方の星」
特派員のひとりごと第14回 沈んだ「東方の星」
 特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
 特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
 特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
 特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
 特派員のひとりごと第9回 3年ぶりの25分
特派員のひとりごと第9回 3年ぶりの25分
 特派員のひとりごと第8回 黄色いリボンと傘の革命
特派員のひとりごと第8回 黄色いリボンと傘の革命
 特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
 特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
 特派員のひとりごと第4回 民主と自由
特派員のひとりごと第4回 民主と自由
 特派員のひとりごと第3回 命の重さ
特派員のひとりごと第3回 命の重さ
 特派員のひとりごと第2回 「歴史」をめぐる戦い
特派員のひとりごと第2回 「歴史」をめぐる戦い
 特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
投稿者について
Noriaki Tomisaka: 1976年8月27日福井県生まれ(辰年、乙女座、B型) 1994年 京都大学法学部入学 1999年 テレビ朝日入社 朝のワイドショー(「スーパーモーニング」)夕方ニュース(「スーパーJチャンネル」)などのAD・ディレクターを担当 2007年〜 経済部にて記者職を担当 農林水産省、東京証券取引所、財務省などを取材 2011年9月〜 北京・中国伝媒大学にて留学生活を開始(〜2012年夏まで)