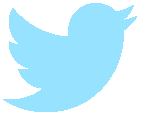特派員のひとりごと第9回 3年ぶりの25分

11月6日、午後9時過ぎ。ひっそりと静まり返る中国外務省の中に、日本大使館の車が入っていった。乗っているのは、東京から出張してきた外務省の幹部や、日本大使館の担当者だ。この日、日本と中国の当事者間で、翌日発表されることになる合意文書を巡って、ギリギリの調整が続けられていた。協議は深夜まで断続的に続き、双方が合意に達したのは、日付が変わった後だとされている。
翌7日早朝、北京空港のVIP搭乗口に姿を見せた谷内正太郎・国家安全保障局長の顔は、どこか晴れ晴れとしていた。帰国後、谷内氏は安倍総理大臣と面会し、訪中の成果を報告。その直後に、「日中関係の改善に向けた話し合い」という文書が発表され、報道各社は「北京APECで日中首脳会談実現へ」と、一斉に速報を流し始めた。
その速報を、私はAPEC会場の一つである国家会議センターで眺めていた。心の中では「ついに来たか」と思いながらも、どこか実感がわかない。いつしか、会場モニターに流れていた中国中央テレビも、日中合意について報じ始めた。欧米の記者たちが、ざわつき始める。しばらくして、岸田外務大臣が会見場に現れ、正式な日中外相会談がセッティングされたと発表した。
「日中関係改善のギアチェンジとしたい」
大臣の言葉をメモしながら、私は自分が北京に赴任したころのことを思い出していた。私が赴任したのは、2013年7月。前年の尖閣諸島国有化により日中関係が冷え切っていたころで、国際会議でも外相、首脳同士が言葉を交わさない状態がすでに当たり前となっていた。そして、2013年12月には、安倍総理が靖国神社参拝を強行。中国側は猛反発し、日中関係は「戦後最悪」と言われるほどに冷え込んだ。
島の問題と、歴史の問題。お互いに譲れない問題を抱えながら漂流する日中関係の中で、北京で開催されるAPECはいつしか、“最後の砦”のように感じられるようになった。私はこの1年間、機会があるたびに、日中の外交関係者に、「APECで安倍さんと習さんは会いますかね?」と尋ねてまわったが、確信をもって「会うだろう」といった人はほとんどいなかった。ただ、この機会を逃すと、日中関係の改善は、大幅に遠のいてしまうという“危機感”は、日中ともに共有していたように感じる。
その危機感の共有から、ギリギリのところで生み出されたのが、今回のガラス細工のような合意文書といえるだろう。
合意文書では、歴史問題について、こう書いている。
『双方は,歴史を直視し,未来に向かうという精神に従い,両国関係に影響する政治的困難を克服することで若干の認識の一致をみた』。
この一文にある「若干の認識の一致」などというフレーズは、日本語としてはほぼ意味不明だが、その思いは十分に理解できる。お互いに「一歩も譲っていない」という主張を行いながらも、玉虫色の解釈ができる、ギリギリの着地点を探したのだ。
ただその後も、日中首脳会談の実現までには紆余曲折があった。
11月8日の日中外相会談で、王毅外相は「日本の平和国家としての歩みが大切だ」と再三にわたって強調した。
翌9日、安倍総理の日程に比較的余裕があったにも関わらず、首脳会談はセッティングされなかった。この時点で、外相会談が不調だったため、首脳会談はお流れになったのでは、という情報も流れている。2人の首脳がようやく顔を合わせたのはさらに翌日、10日の昼過ぎだった。日本の総理大臣と中国の国家主席が正式に会談するのは、2011年12月以来ほぼ3年ぶりのことだ。
2人の会談時間は25分間。通訳がいたことも考えれば、深く立ち入った話ができなかったことは容易に想像できる。しかし、この「3年ぶりの25分」こそが、今回のAPECのハイライトであったと、私は考える。首脳同士が合うことで、日中関係の「ギア」が、大きく動いたということを、お世辞抜きで実感できたからだ。首脳会談が終わった後、澄み切ったAPECブルーの空の下で、いつもの北京の風景が、きのうまでとは全く違って見えた。後ろを向いて走っていた電車がようやく向きを変え、前に進みだした感覚だ。
もちろん、今回の会談はあくまで第一歩に過ぎない。ガラス細工のような合意文書は、玉虫色なだけに、お互いが都合よく解釈できる余地を残している。島の問題にしても、歴史の問題にしても、何も解決したわけではない。
前回、上海APECを主催した2001年、中国はようやく世界貿易機関(WTO)に加盟し、「世界経済の仲間入り」を果たしたばかりだった。それから13年、驚異的な成長を続けた中国は、自らを「大国」と位置付け、アメリカ中心の世界秩序に挑戦するまでになった。APECのもう一つの会場となった北京市北部の雁栖湖(がんせいこ)には、唐代を思わせる巨大な塔も建設され、まさに「東洋の大国」ぶりを、存分にアピールしていた。
とりあえず、首脳どうしが会うことは出来た。ただ、「新しい日中関係」をどう築いていくかに関しては、まだ明確な道筋は見えない。
「強くなった中国と、どう付き合うか?」
今回のAPECは、21世紀の日本に課された大きな宿題の、ほんの1ページ目なのかもしれない。
関連記事:
 特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
 特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
 特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
 特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
 特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
 特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
 特派員のひとりごと 第22回 威信をかけたG20
特派員のひとりごと 第22回 威信をかけたG20
 特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
 特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
 特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
 特派員のひとりごと 第18回 突然の失脚劇
特派員のひとりごと 第18回 突然の失脚劇
 特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
 特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
 特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
 特派員のひとりごと第14回 沈んだ「東方の星」
特派員のひとりごと第14回 沈んだ「東方の星」
 特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
 特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
 特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
 特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
 特派員のひとりごと第8回 黄色いリボンと傘の革命
特派員のひとりごと第8回 黄色いリボンと傘の革命
 特派員のひとりごと第7回 東南アジア取材記 その2
特派員のひとりごと第7回 東南アジア取材記 その2
 特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
 特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
 特派員のひとりごと第4回 民主と自由
特派員のひとりごと第4回 民主と自由
 特派員のひとりごと第3回 命の重さ
特派員のひとりごと第3回 命の重さ
 特派員のひとりごと第2回 「歴史」をめぐる戦い
特派員のひとりごと第2回 「歴史」をめぐる戦い
 特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
投稿者について
Noriaki Tomisaka: 1976年8月27日福井県生まれ(辰年、乙女座、B型) 1994年 京都大学法学部入学 1999年 テレビ朝日入社 朝のワイドショー(「スーパーモーニング」)夕方ニュース(「スーパーJチャンネル」)などのAD・ディレクターを担当 2007年〜 経済部にて記者職を担当 農林水産省、東京証券取引所、財務省などを取材 2011年9月〜 北京・中国伝媒大学にて留学生活を開始(〜2012年夏まで)