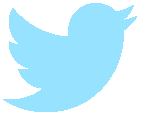特派員のひとりごと第14回 沈んだ「東方の星」

「どうすればいいんだ、説明してほしい!」
6月2日、南京市内のホテルの会議室には、怒号が飛び交っていた。
前日夜、天候不良の中、長江を航行していた豪華客船「東方の星」が転覆してから24時間。
乗客家族の控室として使われていたこの会議室には、200人以上が集まった。
政府の担当者が入れ代わり立ち代わり説明をするが、彼らにも情報がないのだろう。要領を得ない。
「何もわからないのなら、私たちを早く現場に連れて行って!」
あちこちから、すすり泣く声が聞こえる。いつまでに、どういった手段で、現場に連れていってもらえるのか?具体的な提案を求める家族に対して、政府からの回答は、最後までなかった。
そのころ、部屋の大型テレビには、現場で陣頭指揮を執る李克強首相の「雄姿」ばかりが、繰り返し放送されていた。対照的に、家族の怒りや悲しみは、ほとんど放送されることはなかった。
翌朝、しびれを切らした家族たちは、具体的な行動に出た。自力でバスをチャーターし、現場へ向かおうというのだ。我慢強く行政の支援を待つ日本の被害者と違って、行動力の速さと、団結力の強さは、実に中国的だ。家族の安否を一刻も早く確認したいという気持ちに加え、自分たちが動くことで、行政を動かすという計算もあるのだろう。大型バス2台に分乗した家族たちは、政府の制止を振り切り、湖北省の現場へと向かうこととなる。
江蘇省の南京市から、湖北省の現場まで、車でゆうに10時間はかかる。朝10時に出発した家族たちが現場近くの街に着いたのは、夜の8時すぎ。もちろん、現場への道には規制線が張られていて、一般の人は近づくことは出来ない。私はてっきり、その日の夜は現場近くの街に泊まって、次の日に現場に近づけるよう、政府などへ要望するのかと思っていた。しかしここでも、家族の行動は電光石火だった。
「いまから歩いて、転覆現場に近づこうと思っています」
最初に聞いたときは、耳を疑った。あたりは真っ暗なうえ、規制線が張られている中で、どこまで近づけるか保障はない。前の日もほとんど寝ていないだろうし、この日も長時間バスで移動してきたばかりだ。それでも、彼らは行くのだという。
「家族が船の中で生きているかもしれない。今が一番肝心なんです」
南京から追いかけてきた我々も、同行させてもらうことにした。途中、武装警察が行く手を阻もうとしたが、家族たちは一塊になって、大声を上げて突破していった。メディアがいることもあり、武装警察は手荒な真似をせず、家族たちの突破を許した。そこからは、真っ暗な道をひたすら、ひたすら歩き続けた。家族たちは泣き言ひとつ言わず、足の遅い年長者に合わせて休憩を取りながら、少しずつ進んでいった。その歩みが止まったのは、午前3時を過ぎたころ。先回りしていた政府の担当者が、彼らの前に現れ、説得を始めたのだ。
「皆さんの気持ちはよくわかります。今は暗いし、歩いてはとても現場にはたどり着けません。
明日の朝に皆さんを現場に連れて行くことを約束します。だから今日はお休みください」
一部の家族はそれでも現場に向かおうとしたが、ほとんどの家族は政府の提案を受け入れた。疲れ果てていただろうし、翌朝に現場に行くことができるという約束こそ、彼らが夜通し歩いて手に入れた成果だったのだから。ただし、政府の担当者は、その様子を撮影していたメディアには厳しかった。
「現場に行けるのは家族だけです。撮影を今すぐやめなさい。外国メディアは家族の気持ちを利用して面白おかしく騒ぎ立てるだけだ。日本メディアもいるようだが、我々南京市民は、南京大虐殺を決して忘れない。そうでしょう、皆さん」
船の転覆事故の取材で、南京大虐殺を持ち出されるとは正直思わなかったが、担当者は、怒りの矛先を少しでも別に向けたかったのだろう。家族の邪魔をするつもりは毛頭ないので、我々は撮影をやめ、街に戻ることを決めた。救いだったのは、政府の意見に同調する家族がほとんどいなかったことだ。ある家族は、市の担当者には聞こえないように、こっそり話しかけてくれた。
「なんで大虐殺なんだ?意味不明だな。とにかく、ちゃんと取材してくれてありがたかったよ」
その後、中国政府はメディアツアーを組むなどして、一定の取材を認めるようになった。家族たちの悲しみの声も、選別された上だが、報道され始めた。しかし、結果は残酷だった。最終的な生存者はわずか12人で、残り442人は全員死亡。生存者数は当初は14人とされていたが、事故から10日以上たって、急きょ2人減らされた。生存者数がいきなり減るなど、ありえないことで、管理のずさんさが露呈した形だ。
7月1日、事故から一カ月がたったが、中国のマスコミは沈黙を続けている。政府の調査チームが結果を発表するまでは、独自の報道を控えるように、お達しが来ているのだろう。しかし、その裏で、闇に葬られてしまう事実は、本当にないのだろうか?家族にとっても、取材者である私にとっても、事故はまだ終わっていない。
関連記事:
 特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
特派員のひとりごと 最終回「消されたノーベル賞」
 特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
特派員のひとりごと 第27回「共和国」へ
 特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
特派員のひとりごと 第26回「ある朝鮮人男性」の死
 特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
特派員のひとりごと 第25回 オレンジ色の救世主
 特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
特派員のひとりごと 第24回 ネットとリアルをつなぐ人々
 特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
特派員のひとりごと 第23回 人民解放軍の光と影
 特派員のひとりごと 第22回 威信をかけたG20
特派員のひとりごと 第22回 威信をかけたG20
 特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
特派員のひとりごと 第21回 「スコールとリキシャの国で」
 特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
特派員のひとりごと 第20回 「中国的速度」
 特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
特派員のひとりごと 第19回 揺れる「石炭の町」
 特派員のひとりごと 第18回 突然の失脚劇
特派員のひとりごと 第18回 突然の失脚劇
 特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
特派員のひとりごと 第17回 不思議の国の美女たち
 特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
特派員のひとりごと第16回 俳優と皇帝 ー「1つの中国」、2人のリーダー ー
 特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
特派員のひとりごと第15回 天津爆発事故と、中国の安全
 特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
特派員のひとりごと第13回 AIIB狂想曲
 特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
特派員のひとりごと第12回 “遠くて近い国”モンゴル
 特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
特派員のひとりごと第11回 中国経済の“新常態”
 特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
特派員のひとりごと第10回 反腐敗の“光”と“影”
 特派員のひとりごと第9回 3年ぶりの25分
特派員のひとりごと第9回 3年ぶりの25分
 特派員のひとりごと第8回 黄色いリボンと傘の革命
特派員のひとりごと第8回 黄色いリボンと傘の革命
 特派員のひとりごと第7回 東南アジア取材記 その2
特派員のひとりごと第7回 東南アジア取材記 その2
 特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
特派員のひとりごと第6回 東南アジア取材記 その1
 特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
特派員のひとりごと第5回 北と南が交わる場所で
 特派員のひとりごと第4回 民主と自由
特派員のひとりごと第4回 民主と自由
 特派員のひとりごと第3回 命の重さ
特派員のひとりごと第3回 命の重さ
 特派員のひとりごと第2回 「歴史」をめぐる戦い
特派員のひとりごと第2回 「歴史」をめぐる戦い
 特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
特派員のひとりごと 第1回 政治の季節
投稿者について
Noriaki Tomisaka: 1976年8月27日福井県生まれ(辰年、乙女座、B型) 1994年 京都大学法学部入学 1999年 テレビ朝日入社 朝のワイドショー(「スーパーモーニング」)夕方ニュース(「スーパーJチャンネル」)などのAD・ディレクターを担当 2007年〜 経済部にて記者職を担当 農林水産省、東京証券取引所、財務省などを取材 2011年9月〜 北京・中国伝媒大学にて留学生活を開始(〜2012年夏まで)